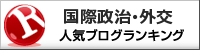11/27The Gateway Pundit<“WHAT THE HELL ARE YOU DOING? HOW DARE YOU?” – Stephen A. Smith GOES OFF in SCREAMING Rant Against Mark Kelly and Democrats’ Calls for Military Sedition: “You Crossed the Damn Line!” (MUST SEE VIDEO)=「一体何をしているんだ?よくもそんなことができたものだ!」―スティーブン・A・スミスがマーク・ケリーと民主党員による軍事扇動の呼びかけに激怒し、激しい非難を浴びせる。「お前は一線を越えた!」(必見動画)>
スミス氏が怒るのはごもっとも。6人の民主党議員は入獄でしょう。
ESPNのスポーツアナリスト、スティーブン・A・スミス氏は水曜日、民主党のマーク・ケリー上院議員が米国大統領に逆らうよう命じた不当な命令について激しく批判し、カメラに向かって叫び、民主党を強く非難した。
スミス氏は水曜日のポッドキャスト「ストレート・シューター」で、ワシントンD.C.での州兵銃撃事件と民主党による軍への裏切り要求について議論し、トランプ氏に対する扇動的な陰謀に加担したケリー氏と民主党の共犯者5人を徹底的に批判した。
ゲートウェイ・パンディットが報じたように、陸軍省は、アリゾナ州選出の民主党上院議員マーク・ケリー氏が、統一軍事法典に基づく不正行為を理由に軍法会議手続きを受けるため、現役に召還される可能性があると発表した。具体的には、ケリー氏は連邦法典18編2387条を含む連邦法違反の疑いで捜査を受けている。同条は「軍隊の忠誠心、士気、秩序、規律を妨害することを意図した行為」を禁じていると、陸軍省は発表した。
ケリー議員と他の民主党議員5人は最近のビデオメッセージで、現役軍人と情報機関職員に対し、トランプ大統領の「違法な」命令に従わない「義務」があると語った。
議員たちは、軍や国家安全保障機関の高官としての経歴を利用し、極めて広範かつ不明瞭な言葉で、指揮系統や米国大統領からの合法的な命令に従わないよう人々に助言した。彼らにそうする義務があると示唆することで、彼らは米国の指揮下にある者たちを脅迫し、合法的な命令に反対させようとした。
これは、大統領の合法的な権限に対する容赦ない法廷闘争の波が続く中で起こったものだが、最高裁判所は大統領の合法的な権限は適切に行使されてきたと圧倒的多数で判決を下している。
米国の議員による違法な命令は、法律に関する知識をほとんど持たずに国に奉仕することを志願した18歳の若者のような素人にとっては正当に見えるかもしれない。
そして、感謝祭前日の水曜日には、ワシントンD.C.で2人の州兵が銃撃されるというテロ攻撃が発生し、一部の民主党員は現在、トランプ大統領がD.C.に州兵を派遣したことが原因だと非難している。
容疑者は、29歳のアフガニスタン国籍のラーマヌラ・ラカンワル氏と特定された。同氏は バイデン氏の不法移民で、2021年の悲惨なアフガニスタン撤退後、バイデン氏の「同盟国歓迎作戦」プログラムの下で入国した。
スミス氏は、この恐ろしい事件の余波を受けて、ポッドキャストのエピソードを民主党への非難に充て、マーク・ケリー氏を怒鳴りつけ、大統領が違法な命令を出したことは一度もないと指摘した。
「上院議員、一体何をしているんですか?カメラに向かって軍人に最高司令官を無視しろと?よくもそんなことができるものです。よくもそんなことができたものです」とスミス氏は言った。「カメラの前で、軍人に最高司令官を無視しろと命令するなんてあり得ません。しかも、その違法な命令が何だったのか、証拠も示していません」
スミス氏はさらに民主党を嘲笑し、「何か違法行為があると思うなら」弾劾のような合法的な措置を講じるよう求め、「いや、くそっ、君らは今までやったことがないわけじゃないだろう。二度も弾劾するなんて!」と付け加えた。
「それで何になるんだ?彼をWHに戻したのか?2020年以降、彼らを放っておけば、もしかしたら彼は民主党をあんな風に脅かすことにはならなかったかもしれない」と彼は付け加えた。

https://www.thegatewaypundit.com/2025/11/what-hell-are-you-doing-how-dare-you/



https://x.com/i/status/1993448787109450201
徐秦賢はXu Qinxianの音訳、 李来珠はLi Laizhuの音訳。
11/27Rasmussen Reports<Thanksgiving 2025: Most Will Celebrate at Home=2025年の感謝祭:大半が自宅で祝う>
米国人のほとんどは、今日、毎年恒例の感謝祭の休日に家族や友人と集まり、3分の2の人は地元でこの行事を楽しむことになる。
ラスムセン・レポートによる最新の全国電話・オンライン調査によると、米国人成人のうち、感謝祭に旅行を計画しているのはわずか26%で、67%は旅行を予定していないことがわかりました。これらの結果は 2022年とほぼ変わりません。


https://x.com/i/status/1993812618172096796

11/26看中国<公开大骂习近平“蠢猪”,日本议员视频疯传(视频)=日本の国会議員が習近平を「愚かな豚」と公然と非難し、その動画が拡散した>

ビデオの中で石平氏の発言している動画はない。参議院議員なのでそこまでは言わないと思いますが。なる前だったら言っていてもおかしくないが、フェイクの可能性あり。
石平氏の動画。長いので中味は確認していません。
https://yutura.net/channel/36634/video/wOrfEKmDr20/
https://yutura.net/channel/36634/video/z385KJ76zI8/
https://www.secretchina.com/news/gb/2025/11/26/1091200.html
11/28阿波羅新聞網<川普幕后重磅表态?日本政府态度大变 华日瑟瑟发抖—WSJ称川普站队北京 日本反应曝光=トランプの裏からの重大態度? 日本政府の姿勢が急変、日中両国が身震い――WSJはトランプが北京を支持と、日本は反応を暴露>WSJは26日、関係筋の話として、トランプ米大統領が今週、高市早苗首相との電話会談で、台湾の主権問題で中国を挑発しないよう助言したと報じた。しかし、日本政府は27日、WSJに対し、この報道内容を否定するよう要請したと発表した。
WSJは、匿名の日本政府関係者と電話会談に詳しい米国関係者の話として、トランプが電話会談で高市首相に対し、台湾について発言する際は口調を和らげるよう助言したが、その助言は非常に微妙なものであり、発言の撤回は求められなかったと報じた。
ブルームバーグによると、木原稔官房長官は27日午前の記者会見で「トランプ大統領は、先ほどの米中首脳の電話会談を含め、最近の米中関係の状況について首相に報告した」と述べ、この件に関する言及を避けた。また、「会談の詳細は外交上のやり取りに関わるため、コメントは控える」と付け加えた。報道内容について真正面の回答はなかった。
しかし、午後になって木原長官は従来の立場を一転し、「報道では、トランプ大統領が台湾の主権に関する問題で中国政府を挑発しないよう助言したとされているが、これは事実ではない」と述べ、報道内容を直接否定した。さらに、日本政府がWSJに対し、報道内容の否定を要請したとも述べた。午前中は言及を避け、午後に明確に否定した理由について、木原長官は「政府として多数の問い合わせを受け、明確にする必要があると判断した」と述べた。
木原の午前と午後の2回の記者会見の間に、匿名の日本政府関係者も報道を否定したが、電話会談の内容については同様に明らかにしなかった。木原は27日、電話会談中、トランプが高市を非常に親しい友人と呼び、いつでも電話をかけてもいいと発言したと改めて強調した。高市はこれに先立ち、トランプが習近平との電話会談について話し合ったと述べていたが、内容については明らかにしなかった。
アポロネットの王篤然評論員は、WSJの評論チームは比較的中立的である一方、ニュース部門は左派的だと指摘した。米国の主要メディアは基本左派で、多くは極左であり、反トランプの立場をとるNYTのようなのも少なくない。ブルームバーグのオーナーであるアンドリュー・ブルームバーグは、親共であるだけでなく、トランプの政敵でもある。そのため、「台湾問題」やロシア・ウクライナ交渉に関する彼の報道は中立的でも客観的でもない。その多くは意図的に誤解を招くものだ。
マードックが所有するWSJやFoxは共和党エスタブリッシュメント支持で、反トランプ。特にWSJはグローバリスト集団だから嘘を流す。
https://www.aboluowang.com/2025/1128/2311965.html
11/28阿波羅新聞網<日媒: 习陷入三重绝境 墙角咆哮=日本メディア:習近平は3重の困難に陥り、コーナーで吼えている>アポロネット王篤若の報道:なぜ習近平はトランプ大統領には頭を下げ、高市には過剰反応したのか? 日本の老舗ゴシップ・政治深掘り週刊誌『週刊新潮』のネット版と日刊ニュースプラットフォーム『デイリー新潮』のネット版は27日、重要な分析を掲載した。習近平は三重の困難に陥っており、国内情勢の安定化のためには「見せしめ」を急ぐ必要がある!
第一に、軍は制御不能、第二に、経済は悪化、第三に、健康状態が懸念される。
日本のメディアは嘆いた:習近平がコーナーで吼えているのは、紅王朝の崩壊を加速させるだけだ–軍内部の抗争、経済崩壊、そして身体崩壊は、まさに三剣が揃っている。
狂人には近づかないことです。
https://www.aboluowang.com/2025/1128/2312168.html
11/28阿波羅新聞網<中国人没了 真相大逆转!日本店发文“求助”:生意好到忙不过来—中国人没了 日本店哀号“快崩溃” 真相大逆转=中国人がいない 真実は逆転!日本の店が「助けを求む」投稿:好調すぎて手に負えない――中国人がいない 真実は逆転!>
中共は、高市早苗首相の「台湾有事」発言に不満を抱き、日本への観光ボイコットを発動した。一方、大分県別府市で創業54年の焼肉店は先日、ソーシャルメディア「X」に助けを求める投稿をした。理由は中国人客の減少ではなく、繁盛しすぎて需要に追いつけないからだ。
飲食店「別府焼肉 春香園」は、11/26の売上高をソーシャルメディアで発表した。98組227人の来店客があったという。また、中国人観光客の減少を冗談交じりに嘆き、店が倒産寸前だと訴え、泣き顔の絵文字を添えて助けを求めるメッセージを掲載した。その後、コメント欄で謝罪し、この投稿が多くの人を誤解させたと述べた。
こういう店が増えるとよい。


https://www.aboluowang.com/2025/1128/2312152.html

何清漣 @HeQinglian 5h
WSJ: トランプは習近平との会談後、高市早苗に電話をかけ、台湾問題に関して言い方を柔らかくし、北京を挑発しないよう促した。これは、米中貿易関係のために、同盟国の地政学上の争いのある立場の核心を制約する意向を反映しているのかもしれない。トランプのメッセージは、日本国内で懸念を引き起こしている。
もっと見る
cn.wsj.comより
何清漣 @HeQinglian 4h
WSJの報道を信じない人もいるため、別の情報源を紹介する:ドイツの声・中国語:ベセント米財務長官は11/25、CNBCのインタビューで「トランプ大統領が釜山での両首脳の歴史的な会談から30日後にこの電話会談を主導した。両国の関係は非常に良好だ」と述べた。
中国外交部の毛寧報道官も定例記者会見で、月曜日(11/24)夕方の電話会談は米国側が主導したと述べた。
もっと見る
dw.comより
横山氏の記事では、世界が左翼化(特にメデイア)している中で、日本の主張をどれだけ取り入れて報じてくれるかです。勿論、主張すべきは主張するのは当たり前ですが。WSJも中共を応援するために意図的に誤報したのかもしれません。左翼メデイアとはそういうものだと思い、めげずに発信を続けることが大事。
記事

「一つの中国」への対応は日中国交正常化から始まった(写真は1972年9月27日、北京を訪問した田中角栄元首相)
はじめに
目次
2025年11月7日の衆院予算委員会での岡田克也氏(立憲民主党・常任顧問)の質問に対する高市早苗首相の答弁が中国の反発を巻き起こし、日中間の外交問題にまで発展した。
岡田氏は、高市総理が1年前の自民党総裁選挙で、「中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言した」ことを取り上げ、これはどういう場合に存立危機事態になると考えたのかと質問した。
高市首相は、「台湾有事について、いろいろなケースが考えられる」と説明した上で、「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースだ」と答弁した。
高市首相の答弁に対して、中国外務省の林剣報道官は11月10日の記者会見で、高市首相が台湾有事は「存立危機事態」に当たる可能性があると国会で答弁したことに対し、「中国の内政への乱暴な干渉で、『一つの中国』原則に深刻に背く」とし、日本側に「強い不満と断固とした反対」を表明し、厳正な申し入れと「強い抗議」を行ったことを明らかにした。
林剣氏は「いかに台湾問題を解決し、国家統一を実現するかは全くの中国の内政だ」と主張。「外部勢力の干渉は許さない」と強調した(出典:産経新聞2025/11/10)。
また、中国の傅聡国連大使は11月18日、国連総会の安保理改革に関する会合で高市首相の発言に触れ、「厚かましい挑発的発言だ」と批判した上で、「国際正義への侮辱であり、戦後の国際秩序の破壊につながる」などと強く反発した。
さらに、「こうした国は安保理の常任理事国になる資格を全く有していない」と述べ、日本が目指す常任理事国入りに明確に反対した。(出典:FNNプライムオンライン)
さて、日中関係の悪化が長期化の様相を呈している。中国外務省は11月14日、日本への渡航を避けるよう注意喚起し、16日には中国教育省が日本への留学を慎重に検討するよう通知し、文化旅行省が日本への旅行自粛するように通知した。
中国政府は11月19日、2週間前に再開したばかりの日本産水産物の輸入を、事実上停止する措置をとった。
また、11月22日から24日にかけて北京で予定されていた民間有識者会議「第21回東京-北京フォーラム」の開催が延期された。
11月16日に中国側の実行委員会から、高市首相の「台湾問題に関して挑発的な発言と武力威嚇」があったことを理由に延期の通知があったという。
宮本雄二・元駐中国大使は、中国側の日本に対する空気感は「大きくは変わっていない」とする一方で、「やっぱり台湾問題は別格」とも指摘。 中国側が内政問題だと主張していることもあり、「強く反応するテーマ」だとみている。
ただ、中国側は「日中関係がどうなってもいいと考えているわけではない」ため、一定期間が経過した後に事態収拾に動くとの見方を示した(出典:J-CASTニュース11月17日)。
以下、本稿では初めに、中国が高市発言に激怒する理由について述べ、次に中国・米国・日本の「一つの中国」原則に対するスタンスについて述べる。
次に、集団的自衛権の行使を限定的に容認する閣議決定の概要について述べ、最後に中国の経済的威圧への対応に関する私見について述べる。
中国が高市発言に激怒する理由
本項は、元経済産業省官僚の古賀茂明氏が「起きないはずの『台湾有事』を自ら起こそうとする高市首相 『どう考えても存立危機事態』は中国に宣戦布告したような大失言!」というタイトルで寄稿したAERAデジタルの記事(2025年11月18日)を参考にしている。
11月10日に行われた衆院予算委員会で高市首相は、11月7日の答弁を撤回しない考えを示す一方で、政府の従来の見解を変更するものではないと釈明した上で、「反省点としましては、特定のケースを想定したことにつきまして、この場で明言することは慎もうと思っております」と「反省」という言葉を表明した。
さて、なぜ、特定のケースを想定したことを明らかにすることを反省するのであろうか。
一つには、秘密漏洩になるからである。なぜなら、敵に手の内を晒すことになり、いざ武力衝突になるというときに日本側が不利になるからである。
もう一つは、台湾有事を具体的に想定した発言は、中国を激怒させるからである。では、なぜ、中国は、高市発言に激怒するのであろうか。
11月10日、中国外務省の林剣報道官が、高市発言に対し、「中国の内政への乱暴な干渉で、『一つの中国』原則に深刻に背く」と述べたように、高市発言は(中国側から見れば)日中間の公的な約束に反するものであるからである。
中国と国交正常化をした1972年の日中共同声明第3項には、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と書いてある。
日中共同声明の詳細は、次項の「日本の『一つの中国』原則に対するスタンス」を参照されたい。
日中間で合意した共同声明は、台湾が中国の領土の一部であるとする中国側の主張を日本側は無条件ではないものの、事実上認めたと外形的に見える。
台湾が中国の領土であることを日本が完全に「認めた」ということになると、台湾に対する中国の武力行使は国際法上内戦の一環(正統政府による反乱政権に対する制圧行動)として正当化され、それに対して他国が干渉することは、中国の国内問題への違法な干渉であり、認められないということになる。
しかし、日本政府や米国政府などは、日本は単に「理解し尊重する」と言っただけで認めるとは言っていないので、この主張は正しくないと主張する。
その際、必ず引き合いに出されるのが、大平正芳外務大臣(当時)の1972年衆院予算委員会における「中華人民共和国政府と台湾との間の対立の問題は、『基本的には』中国の国内問題であると考えます」という答弁である。
「基本的には」と述べているのは、将来中国が武力により台湾を統一しようとした場合は例外であり、我が国の対応については、立場を留保せざるを得ないということだと解釈されている。
しかし、この解釈は、中国に対しては有効ではない。
それを認めたら、台湾が完全に中国の領土であるとは言えなくなるからである。
さて、多くの外交交渉では、どちらか一方が完全に勝者となり他方が完全に敗者となることを避けるため、つまり交渉の決裂を避けるため双方が納得できる玉虫色の結果になることが一般的であるとされる。
後述する「米中の外交関係樹立に関する共同コミュニケ」や「日中共同声明」がまさにその通りである。
「一つの中国」原則に対するスタンスの違い
(1)中国のスタンス
1949年に中国共産党は国共内戦において決定的勝利をおさめ、中華人民共和国を建国した。一方、中国国民党政権は台湾に逃げ込み、中華民国の体制を維持した。
中国共産党は台湾の解放を目指していたものの、実際にはそれを達成する実力を持たなかった。
解放軍は台湾解放に向けた準備段階として1949年10月に福建省沿岸の金門島攻略を目指し上陸したものの、中華民国国軍に大敗を喫し、台湾攻略は遠のいた。
さらに1950年6月に朝鮮戦争が起き、米国が共産主義の拡張を防ぐために台湾海峡に第7艦隊を派遣し、台湾の国民党に対する支援を強化したことで、台湾攻略はほとんど不可能となった。
1954年12月には米華相互防衛条約が締結され、台湾防衛への米国のコミットメントが条約化された。
こうして、中国にとって台湾問題は、統一を完成するという問題であると同時に、冷戦の最前線が台湾海峡となったことで、米国による包囲網にいかに対抗していくかという問題ともなったのである。
台湾を解放することはできないが、しかし大陸と台湾がそれぞれ別の国家として存在するという「二つの中国」を認めるわけにはいかなかった中国は、国際社会で台湾を孤立させることに重点を置くようになった。
その中で重要となっていった論理が「一つの中国」原則であった。
「一つの中国」原則とは「世界には一つの中国しかなく、台湾は中国の一部分である。中華人民共和国は全中国を代表する唯一の合法政府である」という原則的立場のことである。
1971年には国連代表権を中国が獲得し、台湾を国連から追い出すことに成功した。
また1971~72年に起きた米中接近の過程において、中国側は台湾問題を重視し、「一つの中国」原則についての立場を堅持した。
結果的に1972年の上海コミュニケの中では米中それぞれが自国の立場を併記するという形で自国の立場をそのまま残し、さらに口頭了解の形で米国側に譲歩させることに成功した。
(2)米国のスタンス
リチャード・ニクソンが大統領に就任した1969年、中ソの緊張状態は戦争の危険性をはらむほどになっていた。
一方、ニクソン大統領は、米軍のベトナム戦争からの名誉ある撤退という大きな課題を抱えていた。
そのニクソンが政権につくと同時に外交問題のエキスパートとして選んだのが、当時ハーバード大学教授のヘンリー・キッシンジャー氏であった。
キッシンジャー氏はいわゆる「力の均衡」論者で、イデオロギー的な外交を嫌い、また国務省などの専門の外交官を嫌い、徹底した秘密保持と個人的なルートを重んじるタイプであった。
脱イデオロギー的な地政学、バランスオブパワーという考え方は、当時は国民も外交官も馴染みがなく、米国外交の主流を占める考え方ではなかった。
そして、1972年2月21日にニクソン大統領が中華人民共和国を初めて訪問し、毛沢東主席や周恩来総理と会談を行い、2月27日「ニクソン米大統領の訪中に関する米中共同コミュニケ」(上海コミュニケ)を発表した。
そのなかで両国は、平和5原則を認め合い、両国の関係が正常化に向うことはすべての国の利益に合致すること、両国はアジア・太平洋地域で覇権を求めるべきでなく、また他のいかなる国家あるいは国家集団の覇権樹立にも反対することを声明した。
1973年5月に米中両国は正式な国交を樹立する準備のため、北京とワシントンD.C.に米中連絡事務所を設立した。
1979年1月1日の「米中の外交関係樹立に関する共同コミュニケ」で米側は、「アメリカ合衆国は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」(The United States of America recognizes the Government of the People’s Republic of China as the sole legal Government of China.)と共に「アメリカ合衆国政府は、中国はただ一つであり、台湾は中国の一部であるとの中国の立場を認める」(The Government of the United States of America acknowledges the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China.)とし、台湾からすべての武力と軍事施設を撤去する最終目標を確認し、この地域の緊張緩和に応じて台湾におけるその武力と軍事施設を漸減することを声明した。
これは、朝鮮戦争以来米国が一貫してとってきた中国封じ込め政策の大転換を意味する。
1979年1月1日、米中両国が国交を樹立したため、台湾政府は米国との断交を宣言した。
さて、上記「米中の外交関係樹立に関する共同コミュニケ」では、米国は「中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認 (recognize) する」と明記しているが、中国の台湾に対する立場(「中国はただ一つであり、台湾は中国の一部である」)については、単に「認める (acknowledge)」という表現に留めている。
この「承認 (recognize)」と「認める (acknowledge)」という表現の違いが重要な外交的差異である。
米国は中国の主張に完全に同意したわけではなく、中国側の立場を「理解し、それに異を唱えない」という程度の意味合いで解釈されている。
(3)日本のスタンス
ニクソン米大統領が1972年2月、長く対立してきた中国を訪問した。対中政策で米国と足並みをそろえてきた日本は衝撃を受けた。その5か月後に首相に就任した田名角栄氏が中国との国交正常化を急いだ。
1972年9月田中首相が訪中し、周恩来総理との間で日中共同声明を調印し、日中国交正常化が合意された。
日本は、共同声明で「中華人民共和国が中国の唯一の合法政府」と承認し、台湾と断交した。「台湾が中国の領土の不可分の一部」とする中国側の立場について、日本は「十分理解し、尊重」すると記した。
「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」の関連する条文は次の通りである。
第二項 日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
第三項 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項(注1)に基づく立場を堅持する。
さて、2023年4月24日に、原口一博氏より「いわゆる一つの中国と台湾有事に関する質問主意書」が提出された。
質問主意書では、「中華人民共和国政府が自らの立場について表明し、これに対し日本政府が『十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する』と述べた日中共同声明は、台湾が中国の領土の不可分の一部であるという、いわゆる『一つの中国』を日本政府が認めたものであるとの認識は正しいか。正しくないのであれば、日本政府が『一つの中国』を認めない理由は何か」と質問した。
これに対し、同年5月9日に政府は、「台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明第三項にあるとおり、『台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるとの中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重するというものである』」と答弁した。
すなわち、日本のスタンスは、上記の「中国の主張に完全に同意したわけではなく、中国側の立場を理解し、それに異を唱えない」とする米国のスタンスと同じであると解される。
(注1)ポツダム宣言第八項の条文は、「カイロ宣言の条項は、履行せらるべく、又日本国の主権は、本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし」である。従って、ポツダム宣言第8項に基づく日本の立場とは、「カイロ宣言の条項を履行し、台湾と澎湖諸島を中華民国に返還する」と解される。
集団的自衛権行使を限定的に容認する閣議決定
(1)経緯
2007年第1次安倍内閣は、日本の安全保障環境が変化していると捉え、時代に適した実効性のある安全保障法的基盤を再構築する必要があるとの認識から、4月に首相決裁で「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の設置を決定した。
同懇談会は、安倍晋三首相(当時)から提示を受けた4つの類型(①公海における米国艦船の防護、②米国に向かう弾道ミサイルの迎撃、③国際的な平和活動における武器使用、④国連PKO等に参加している他国の活動に対する後方支援)についての提言をまとめた報告書を、2008年年6月に福田首相(当時)に提出した。
同懇談会は2007年8月30日の第5回会議まで開催されたのち、続く福田康夫内閣から2012年の野田佳彦内閣まで開催されず、報告書は棚上げされていた。
ところが、2012年に第2次安倍内閣が発足し、同懇談会は再開された。
2014年5月15日、同懇談会は、「集団的自衛権の行使は認められるべきだ」とする報告書を安倍首相に提出した。
これを受け、政府はさらなる検討を行い、そして、2014年7月1日、政府は、「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を閣議決定した。
これが、いわゆる「集団的自衛権の行使を限定的に容認する閣議決定」である。
(2)閣議決定の内容
前文部分で我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることなどを記述しているほか、①武力攻撃に至らない侵害への対処、②国際社会の平和と安定への一層の貢献、③憲法第9条の下で許容される自衛の措置、④今後の国内法整備の進め方、という4つの柱に沿って、安全保障法制の整備に向けての政府の基本方針を示している。
同閣議決定のポイントは次の通りである。
①武力攻撃に至らない侵害への対処
・離島周辺などでの不法行為に対応するため、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続の迅速化を図るための方策を具体的に検討する。
②国際社会の平和と安定への一層の貢献
・他国軍隊への後方支援では、「武力の行使との一体化」論は前提とした上で、従来の「後方地域」や「非戦闘地域」といった枠組みはやめ、他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」以外での補給・輸送等の支援活動は可能であるとし、必要な法整備を行う。
③憲法第9条の下で許容される自衛の措置
・我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容される。
・憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。
・他国に武力攻撃が発生した場合に、自衛隊に出動を命ずるに際しては、現在の防衛出動の場合と同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する。
④今後の国内法整備の進め方
・実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要であり、政府として、法案の作成作業を開始することとし、準備ができ次第、国会に提出する。
(3)集団的自衛権の行使の限定的容認
上記のように、2014年7月1日、政府は、集団的自衛権は保持するが行使できないとしてきた政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権を限定的に行使することを可能とする新たな見解を閣議決定した。
与党協議では、公明党が過去の政府見解との整合性や、自衛隊の活動の「歯止め」を強く求めたため、懇談会の提言(注2)と比べると、集団的自衛権行使の範囲をより限定した合意となった。
そして、集団的自衛権の行使は、①密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、②国民を守るために他に適当な手段がない、③必要最小限度の実力の行使――の3要件が満たされた場合に限って容認されることになった。
そして、この集団的自衛権の行使3要件が、平和安全法制整備の際に、「存立危機事態」として導入されたのである。
「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(通称:事態対処法)第二条第四項に、存立危機事態は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう、と定義された。
さらに、集団的自衛権の行使3要件が、2014年7月1日に「武力行使の新三要件」(注3)として閣議決定された。
(注2)「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の集団的自衛権の行使の3要件は、①我が国と密接な関係のある外国に対して武力攻撃があり、かつ、②その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、そして③その国の明示の要請又は同意を得て、必要最小限の実力の行使が可能とするものであった。
(注3)武力行使の新三要件:
①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。
(4)平和安全法制の整備
上記の閣議決定を踏まえ、政府は、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始した。
そして、2015年5月14日、政府は国家安全保障会議および閣議において、「平和安全法制」の関連2法案を決定し、翌15日に国会に提出した。
2015年9月19日、平和安全法制関連2法が成立し、同30日に公布された。
中国の経済的威圧への対応に関する私見
2012年9月11日に日本政府が尖閣諸島を国有化した際には、中国税関当局が日本からの貨物に対して通関検査を強化する動きが広がった。
また、中国各地で反日デモが広がって日系スーパーなどが暴徒化したデモ隊に襲撃されたほか、日本人を標的にした暴行でけが人も出た。
日本製品のボイコット運動も全国で展開された。中国政府は反日デモなど抗議活動の一部を容認していた。
尖閣諸島を国有化した後の最初の日中首脳会談は2年以上経った2014年11月10日に北京で開催されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)の際に安倍晋三首相(当時)と中国の習近平国家主席との間で実施された。
また、尖閣諸島国有化後の日中対立は、日中両国が全面的な軍事衝突や関係の決定的な悪化を避けるための外交的・政治的努力を継続したこと、及び米国の関与などにより沈静化した。
ちなみに、米ホワイトハウスのカーニー報道官は9月19日、記者団に対し「良好な日中関係が、地域のすべての人の利益となると確信している」と述べた。
さて、経済的威圧を振りかざす中国に対する具体的対応は次の通りである。
- まず、日本政府は中国からの経済的威圧に対し、感情的な対立を避けて冷静に対応しつつ、主張すべき点は主張すべきである。
高市首相は、「政府の立場は一貫している」と強調しているが、この点は、一貫して堅持すべきである。
前述したが、宮本雄二・元駐中国大使は、中国側は「日中関係がどうなってもいいと考えているわけではない」ため、一定期間が経過した後に事態収拾に動くとの見方を示している。
今、日本は、慌てず冷静に、中国の変化を待つしかない。
- 次に、サプライチェーンの多様化・強靭化である。
小野田紀美経済安保担当大臣は、11月18日の会見で、「すぐ経済的威圧をしてくる所に対して依存しすぎるということはリスクではある」と中国への経済依存に警戒感を示したが、その通りである。
特定の国(中国)への過度な依存を減らすため、生産拠点や調達先を地理的に分散させるべきである。また、販路の多元化を通じた威圧の無力化をはかるべきである。
- 次に、中国の宣伝工作に負けない情報発信を行う。
今、国際社会では国益の対立を背景として宣伝工作(プロパガンダ)が目に見える形、あるいは目に見えない形で熾烈に繰り返されている。
高市首相の台湾有事に関する発言を巡り、中国が国際社会に向けて日本批判の宣伝工作を続けているが、中国の強硬姿勢に同調する動きはロシアなど一部の友好国に限られているもようである。(出典:時事通信社11月24日)
我が国においても、各政府機関、特に外務省が国内外への積極的な情報発信を行うべきであろう。
- 最後に、米国との連携である。
米国のジョージ・グラス駐日大使は11月20日、外務省内で記者団の取材に応じ、高市首相の台湾に関する国会答弁に中国が反発していることについて、「中国の経済的威圧の典型例だ」と指摘し、「我々は首相を支持する。あらゆる手段で反論を続け、可能な限り支援する」と語った(出典:読売新聞2025年11月20日)。
筆者は、今回も尖閣諸島の国有化の際と同じように、米国の力(中国への圧力)を借りてもよいのではないか思う。頼れるのは同盟国である。
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。