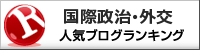2/10The Gateway Pundit<American Color Revolution: How Globalists Used Alinsky to Subvert Our Republic, and How We Save It.=米国のカラー革命: グローバリストがアリンスキーをどのように利用して共和国を転覆させ、そして我々はいかにして共和国を救うのか。>
左翼は邪悪。メデイアはその手先で国民に真実を知らせようとしない。ネットから良質の情報を選んで真実に近づかないと。

アメリカのカラー革命: グローバリストがアリンスキーをどのように利用して共和国を転覆させ、そして我々はいかにして共和国を救うのか。
Mark Cook 氏の許可を得て転載。
アメリカ合衆国は10年以上もの間、グローバリストのエリートたち、すなわちWEFネットワーク、オープン・ソサエティ財団、ディープステートの抵抗勢力、そして彼らの企業メディア同盟者たちによって画策された、計算ずくのカラー革命に耐え忍んできた。その目的は決して「民主主義」ではなかった。国家主権、憲法秩序、そしてアメリカ合衆国そのものを計画的に解体し、国境のないテクノクラート体制における従順な結節点に置き換えることだった。彼らの戦術の多くは、ソール・アリンスキーの『ラディカルのルール』からそのまま受け継がれたものだ。標的を個人化し分極化させる(ルール13)、容赦なく嘲笑する(ルール5)、容赦なく圧力をかける(ルール8)、敵に自らのルールを守らせる(ルール4)、そしてあらゆるネガティブ要素を相手がひっくり返すまで押し付ける(ルール11)。
革命はほぼ成功に近かった。米国民の目覚めによってのみ阻止されたが、自治の心臓部である選挙を国民自らが直接的かつ透明性のある形で管理できるようになるまでは、完全には覆らないだろう。
フェーズ1:制度的捕獲(2008~2015年)
アリンスキー流の組織化を学んだバラク・オバマは、メディア、学界、諜報機関、企業(ESG経由)、そしてNGOへの浸透を加速させた。共和国を守るべきあらゆる機関が、このアジェンダの媒介物と化してしまったのだ。
第2段階:2016年の反発とエスカレーション(2016~2019年)
トランプ氏の勝利は、アリンスキー攻撃の全面的展開を引き起こした。ロシア共謀の捏造、二度の偽りの弾劾、そして大統領とその支持者を「民主主義」に対するファシスト的脅威と罵倒する絶え間ない非難だ。実際、「我々の民主主義」というフレーズは今日まで執拗に乱用され続けており、しばしばアメリカ合衆国が立憲共和国であるという根本的な事実を巧妙に軽視、あるいは抹消するために用いられている。
フェーズ3:2020年の押収 – 盗まれた選挙と疑念の武器化
2020年の選挙は転換点となった。既存の選挙システム――中央集権化された有権者名簿、不透明な電子投票機、大量の郵送投票、選挙事務所への私的資金提供、そして記録へのリアルタイムの一般公開の拒否――は、意図的に悪用されやすい状態に放置されていた。そして、彼らはそれを悪用したのだ。

投票用紙の不正収集、安全対策が不十分な投函箱、集計機のアルゴリズム操作、検証不可能な投票用紙の挿入、そして反証となる証拠の組織的な検閲により、選挙はハイブリッドな秘密作戦と化した。メディア産業複合体は一致団結して「米国史上最も安全な選挙」と嘘をついた。選挙結果に疑問を呈した者は皆、嘲笑され、プラットフォームから排除され、陰謀論者とレッテルを貼られ、さらにひどい仕打ちを受けた。
最も恐ろしい例は、ティナ・ピーターズ氏 (@realtinapeters)だろう。 コロラド州メサ郡の元書記官である彼女は、2021年に郡の投票機を確保して調査し、不正侵入の証拠を探したが、刑事訴追され、当時の腐敗した連邦政府関係者と共謀していた者たちにより州の告発で有罪判決を受け、その後、仕組まれた裁判で懲役9年の判決を受け、彼らに操られた判事の一人によって判決が下された。トランプ大統領が2025年12月に完全な恩赦を出した後も、コロラド州の根深い政権は彼女の釈放を拒否した。彼女は今もなお獄中にある。この事件一つとっても、腐敗は連邦政府だけにとどまらないことが証明されている。それは、旧体制に今も従う州や地方の機関にも深く根付いているのだ。
これがアリンスキーのやり方だった。脅威を個人的なものにし(選挙懐疑論者=「反乱分子」)、彼らを嘲笑し、容赦ない圧力をかけ続け、システムを監査しようとする者を見せしめにしたのだ。
フェーズ4:統合(2021~2023年)
権力を掌握した革命は、法廷闘争、ESG企業への義務付け、大手IT企業による検閲、そしてDEIとジェンダーイデオロギーによる文化の抹消を武器とした。メディアは執行者としての役割を継続し、Twitterファイル、ハンター・バイデンのラップトップ認証の遅延、エプスタイン文書、そしてその後のあらゆる干渉の暴露を隠蔽した。
第5段階:暴露、反革命、そして今後の道(2024~2026年)
仮面は剥がれ落ちた。ツイッターファイル、キャサリン・ヘリッジによるCBSの暴露、機密解除された文書、内部告発者、そして国民自身の目が、その仕組みを暴き出した。トランプの復帰、既存メディアの信頼性の崩壊、そして州レベルでの抵抗の高まりが、流れを変えた。
しかし、選挙制度そのものが敵の手に残っている限り、革命は敗北しない。
出口を示す宣言
アメリカ国民の選挙操作からの独立宣言は、
「Hand Count Road Show」では、問題とその解決策を分かりやすい言葉で明らかにします。
それは、集計を隠す複雑な電子機械、地方の監視を排除する中央集権的な管理、不正を招き入れる無制限の不在者投票、記録への一般公開の拒否、闇資金の影響、偽情報、内部脅威、国内外からの侵入といった、容赦ない不正行為のパターンを特定している。
修正方法は驚くほど簡単で、何世紀にもわたって安全性が証明されており、教育や財力に関係なくすべての国民が検証可能です。
- 郡レベルの有権者登録(ID提示と定期的な対面再確認)
- 手書きの紙投票用紙
- 小規模選挙区(有権者数1,500人以下)
- 国民の祝日に身分証明書を使って直接投票する(厳格な審査を受けた不在者投票を除く)
- 半透明の投票箱
- 投票所でスキャンされた投票用紙の画像
- 投票用紙が移動される前に、超党派の市民チームが投票所でカメラの前で公開集計する。
- 選挙当夜に選挙区レベルの結果を即時発表
- 選挙後2日以内に投票用紙の画像、集計表、保管記録、ビデオを完全公開します。
- 投票用紙の再集計を通じて公民を学ぶ生徒を含む公開監査
これらの方法は過激なものではありません。共和国を築き上げた、透明性が高く、地方レベルで市民が管理する選挙への回帰です。グローバリストが何十年にもわたって悪用してきた攻撃対象領域を排除します。そして、今すぐにでも郡ごと、州ごとに実現可能です。実際、マーク・クック氏がまとめた「進歩的選挙プラットフォーム(PEP)」 は、テクノロジーを適切な方法で活用し、盲目的な義務に基づく不透明で信頼に基づくシステムではなく、透明性と検証可能性を備えたシステムを構築しています。
ハンドカウント・ロードショーは 、この目標を実現するために存在します。公開ブリーフィング、デモ、役人や保安官との作業グループ、そして郡による選挙管理の回復を目指す草の根組織などです。市民の皆様には、宣言をあらゆる場所で共有し、公開イベントや非公開の研修会に参加し、ハンドカウントのパイロットプログラムを要求し、地方自治体の役人に責任を負わせるよう強く求められています。
最終的な真実
2020年のカラー革命が成功したのは、もはや国民が選挙をコントロールできなくなったからだ。メディアを暴露したり、沼地の一部を干拓したり、真の米国民を選出したりする他のあらゆる勝利は、国民のコントロールが回復されるまでは一時的なものに過ぎないだろう。
米国民が、国民の監視の下、手作業で集計された紙の投票用紙を通じて、自らの選挙を直接、実践的に、そして透明性を持って管理するまで、この共和国は破滅の危機に瀕したままです。グローバリストたちは、次の選挙サイクルを待ち、戦術を洗練させ、再び攻撃を仕掛けるでしょう。
反革命はここにある。宣言は書き上げられた。ロードショーは始まった。
https://joehoft.com/american-color-revolution-how-globalists-used-alinsky-to-subvert-our-republic-and-how-we-save-it/


https://1a-1791.com/video/fww1/00/s8/2/U/d/p/Y/UdpYz.caa.mp4?b=1&u=ummtf

https://1a-1791.com/video/fwe2/ff/s8/2/e/d/p/Y/edpYz.caa.mp4?b=1&u=ummtf




ゴールドマン・サックス作成
2/10Rasmussen Reports<Half Think Big Business Has Too Much Influence on Trump=半数は、大企業がトランプ大統領に過大な影響を与えていると考えている>
有権者の間では、企業にとって良いことが一般の米国人にとっても良いことなのかどうかで意見が分かれており、半数はドナルド・トランプ大統領が企業の利益に左右されすぎていると考えている。
ラスムセン・レポートによる最新の全国電話・オンライン調査によると、有権者の50%がトランプ政権における大企業の影響力が強すぎると考えていることが明らかになりました。WHにおける大企業の影響力が不十分だと考える人はわずか10%で、トランプ政権における大企業の影響力は適切だと回答した人は31%でした。
https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/trump_administration_second_term/half_think_big_business_has_too_much_influence_on_trump?utm_campaign=RR02102026DN&utm_source=criticalimpact&utm_medium=email

https://x.com/i/status/2021387555183243414





2/10阿波羅新聞網<不让习喘口气!美军大动作曝光—为台海冲突准备 美方再出利剑=習近平はひと息つく暇なし!米軍の動きが明らかに―台湾海峡紛争に備え、米国は新たな武器を繰り出す>
米国は台湾海峡の新たな事態に備えるため、軍事展開を加速させ、区域外諸国との交渉を進めている。WSJ紙は、米国が今後数年間で最大4隻の原子力潜水艦を西オーストラリア州のスターリング海軍基地に配備する計画で、最初の潜水艦は早ければ2027年に到着する見込みだと報じた。これは明らかに、台湾海峡における米中間の潜在的な紛争に備えた戦略的準備として位置付けられている。
報道によると、西オーストラリア州のスターリング海軍基地は、台湾海峡や南シナ海で緊張が高まった場合、米原子力潜水艦にとって戦場に近い停泊地と「安全な避難場所」を提供するという。オーストラリア政府は現在、将来の米軍展開に対応するため、基地と隣接する整備区域に数十億ドルを投資している。
この動きは、「中国封じ込め」を中核目標とする米豪軍事統合の推進に向けた重要な一歩と見られている。米国は、西オーストラリア州への原子力潜水艦の配備は、台湾海峡と南シナ海への距離を縮めるだけでなく、これまでグアム、真珠湾、そして米国本土に集中していた整備の負担を軽減すると考えている。報道は、米国の造船・整備能力が長らく逼迫しており、海外の整備基地が米軍にとってますます重要になっていると指摘する国防アナリストの見解を引用している。
この配備計画は「AUKUS」の枠組みに組み込まれている。合意によると、オーストラリアは2030年代初頭に米国からバージニア級原子力潜水艦の受領を開始する予定だが、米国造船の遅れにより、納入時期と実現可能性には依然として疑問が残る。報道は、米原子力潜水艦隊の司令官であるリンカーン・レベステック少将の言葉を引用し、紛争で潜水艦が損傷した場合、「戦場への復帰が早ければ早いほど良い」と述べている。また、スターリング海軍基地の地理的条件は、グアムと真珠湾の既存の能力を補完し、米軍がより迅速に戦闘態勢を回復することを可能にすると述べている。
トランプの米国は台湾を守る覚悟があるということ。
https://www.aboluowang.com/2026/0210/2346268.html
2/10看中国<高市早苗胜选后习近平难以启齿的七重困境(图)=高市早苗の選挙勝利後、習近平が直面する7つのジレンマ(写真付き)>
中文がコピーできないので、翻訳して紹介できません。下のURLをクリックして翻訳してお読みください。習の面子から、ドンドン中共とデカップリングできそう。
https://www.secretchina.com/news/gb/2026/02/10/1094815.html
2/10看中国<高市狂胜中共战狼齐出动 胡锡进小粉红遭炮轰(图) =高市の圧勝:中共の「戦狼」が一斉動員、胡錫進と小ピンクが攻撃に逢う(写真)>
胡錫進は高市を「歴史の流れに背いている」と非難し、「アベノミクス」は短期的な偽りの繁栄をもたらしただけで、高市が安倍の政策を採用しても流れを変えることはできないと主張した。
外部は、胡錫進が選挙で示された日本国民の強い民意を無視し、支配者の視点から挑発的で「戦狼」的な発言を書いたと批判した。
ネットユーザーからは、「黙れ!彼らの選挙だ。お前に何の関係があるんだ?」「彼女は首相だ。なぜお前が口出しするんだ?」「民主主義国家は公平だが、お前達の国は違う」「中共はパニックに陥っている!」「真の鉄の女、高市首相を支持せよ!」といった批判の声が上がった。
さらに、一夜のパニックを経て指示を受けたかのような「小ピンク」たちは、9日朝から台湾の様々なソーシャルメディアプラットフォームに殺到し、デタラメな発言を連発した。彼らは、高市首相の勝利後、中共は「手足を伸ばして、日本を片付ける」と主張し、台湾のネットユーザーから激しい反発を受けた。
ある小ピンクがVPNを使ってスレッドに投稿した。「台湾の人々はおそらく知らないだろうが、小ピンクたちは『あなたたち以上に高市の選挙勝利を望んでいる』のだ。単純な話だ。高市の勝利は、日本が親米反中の政策を堅持し、中国が自由に日本を片付けられるようになることを意味する。もちろん、中国は台湾の人々の目の前で容赦なく日本を破壊するだろう。まるでトランプがベネズエラを容赦なく破壊したように。」
このコメントには、台湾のネットユーザーから即座にコメントが殺到した。「中共の得意分野は日本の片づけではなく、普通の中国人への対処だ」「長年にわたり、中国(中共)は誰を破壊してきたのか?それは中国人だったのではないのか?」 「そうだ、そうだ、そうだ。高市が負ければ中国は勝つ。高市が勝てば中国はもっと勝つ!大勝利だ!大賛成だ!」 「月収1500ドルの人たちが心配するようなことじゃないよ。」
中国人は、他人のことより自分たちのことを心配したら。
https://www.secretchina.com/news/gb/2026/02/10/1094811.html

何清漣 @HeQinglian 7h
英国の言論機制、中国語Twitterユーザーの多くが言論の犯罪化を支持しているという事実(香港の黎智英(ジミー・ライ)を例に挙げ、デモの自由に反対する意見も含む)、そしてメディアはもはや公共の道具ではなく、政治動員の道具であるべきだという考えに賛成するのさえもいる。この世界には1984年のような状況が訪れようとしている。
もっと見る
引用
老猿説OldApe @OldApeTalk 12h
英国の学校が保護者に宛てた手紙は、「1984年」の雰囲気に満ちている。よく見ると、行間に「元首」の傲慢な態度が浮かび上がってくる。
ある児童がラマダンの行事への参加に反対し、参加したクラスメートを嘲笑した。
そのため、学校はこれを「人種差別的ハラスメント」とみなし、生徒の行動記録と学校の記録に記録した。x.com/OldApeTalk/sta…
もっと見る
中共の档案と同じ。
何清漣 @HeQinglian 7h
以下の2名(山夫氏を含む)へ:メディアがプロパガンダの道具であるという意見に同意するなら、この認識の始祖はレーニンである。歴史は、この道がどこへ向かうのかを証明している。私の著書『霧鎖中国』では、レーニンのメディアと世論に関する指導思想こそが、中共によるメディア支配の起源であると専門的に指摘した。
皆さん、同じ過ちを繰り返すのを楽しんでいるようですね?地獄で十分な時間を過ごしていないようですね。
引用
一片小小的光明 @jojowheel 17h
これは依然として古典的自由主義の認識である。
しかし、古典的自由主義の立場は今の世界には存在しない。
現代におけるメディアは、政治動員の道具であり、権力構造におけるナラティブ・コントロールの一部であり、いわゆる「製造された同意」メカニズムの一部でもある。
好むと好まざるとにかかわらず、これが現実である。

何清漣 @HeQinglian 2h
香港について。中国の改革開放初期、香港は世界への中国の窓だった。香港の繁栄と自由は中国人の視野を広げ、多くの人が命がけで香港へ不法に越境した。当時、主に中国人で構成される4つの国と政治実体があり、それらは以下のように要約される。香港には民主主義はないが自由はある、台湾には民主主義と自由がある、シンガポールには民主主義があるが自由はない、中国本土だけが民主主義も自由もないと。
もっと見る
何清漣 @HeQinglian 2h
1980年代から2000年代、中国で書籍を出版するのが難しかった頃、香港には出版社を見つけることができた。香港を訪れると、政治的に禁じられた書籍や雑誌を数多く持ち帰ることができた。その後、中国では言論統制がますますレーニン主義的になった。中国の検閲を通過できない本を出版したい場合、香港のような窓口はもはや存在しなくなった。
もっと見る

何清漣 @HeQinglian 4h
中国の言論弾圧政策に賛同する人々は、当局が嫌う出版物を出版したとして涂金燦を逮捕・投獄すべきだと考えているのだろうか?
引用
Zhijun Guo @cool74810120 2月8日
#涂金燦:北京の出版人
罪名:違法営業
現在の状況:裁判を待って勾留中
長年にわたり個人出版や晩年は歴史編纂事業に携わってきた。
著書には『何家棟記念文集』『周舵民主論』などがある。
彼は1989年に「中国はどこへ行くのか?」を執筆した罪で1年間投獄され、08憲章の6番目の署名者となった。
2023年11月末に拘束され、12月末に逮捕された。
2024年6月に、彼が起訴のために移送されたことを知った。#良心犯
もっと見る
西村氏の記事では、ロシアの侵攻当初のキーウ近郊への空挺・ヘリボーン作戦の失敗は、ウクライナなど赤子の手をひねるほど簡単との油断が招いたものではないか。それに対し米軍のベネズエラ奇襲作戦の成功は、事前準備・機密情報漏洩なし・戦闘中の部隊統合運用のすばらしさによるものとの感を持った。何事もなめてかかってはいけない。
また米軍の近代兵器と兵器を操作する兵士の卓越さも称賛されて然るべき。ロシアは両方ともない。経済力がないため、兵器開発に遅れを取っているのでは。中共は、兵器は経済力と技術窃取で進んでいるが、兵士の鍛錬の仕方と腐敗により米軍とはまだまだ差があるように思う。
氏が言うように、プーチン大統領は「力と量で攻めまくれば、短期間では難しくても消耗戦でウクライナは音を上げる」との考えは時代遅れなのを認識し、一刻も早く戦争をやめるべきである。双方もうこれ以上の流血の事態は避けるべき。
記事

米空軍の早期警戒管制機「E-3」のドーム(1月13日嘉手納基地で、米空軍のサイトより)
戦争の天王山で実行されるべき空中機動作戦
目次
2022年2月24日未明、ロシア軍はウクライナ侵攻開始と同時に、全面侵攻の一つとして、ウクライナの首都キーウ近郊の飛行場に空挺・ヘリボーン作戦(空中機動作戦)を実施した。
一方、2026年1月3日未明、米軍がベネズエラにヘリボーン作戦主体の奇襲攻撃を行った。
ロシアの狙いは、キーウ近郊の空港を占拠して、キーウへの地上攻撃と占拠達成に大きく寄与することだった。
これに対し米国は、ベネズエラ大統領を拘束・連行することであった。
この2つの事例から分かるのは、戦争の最大局面で実行される空中機動作戦は、成功すれば大戦果を得られる一方、失敗すれば戦局を急速に悪化させるということである。
ロシアと米国の作戦は規模が異なり、ロシアは空挺とヘリボーン作戦を併用し、米国はヘリボーン主体の作戦であった。
結果は、ロシアの作戦は実行部隊の降着までは成功したが、当初の空挺部隊は反撃で大きな損耗を被り、当初想定された「空輸による増援・重装備投入(エアブリッジ)」は頓挫した。
一方、米国はベネズエラの大統領を捕らえて米国に連れ去るという作戦の目的を達成した。
両国の作戦は、目的・規模・単独作戦か地上作戦との提携か、などの違いがあり、この2つの作戦を比較分析するのは無理な面も多い。
しかし、ロシア軍の真の実力がこの2つの作戦を比較することによって見えてくる面も少なからずある。
そこで、両軍の作戦能力は何が異なっていたのか、どこに差があったのかという点に焦点を当てて考察してみたい。
特に、ロシアのヘリボーン作戦失敗の理由が、そのままロシアによるウクライナ侵攻全体にも当てはまる気がしてならない。
今後、ロシアによるウクライナ侵攻継続に限界が見えてくるのか、そのヒントもここにあるように思える。
両国の空中機動作戦の概要
(1)ロシアの空中機動作戦の概要
ロシア軍は侵攻と同時(2022年2月24日)に、複数の空挺部隊とスペツナズ(特殊部隊)からなる推定数百人規模(700人規模とも)を第1波として、ヘリ20~34機に搭乗させ、キーウ近郊のアントノフ(ホストメリ)空港を空から襲撃し、一時的に飛行場の一部を制圧したとされる。
たった1日で占拠したことは、その時点までは、第2次世界大戦後、歴史的な大成功であったように見えた。
だが、ウクライナ軍は、「IL-76」輸送機などを使ったロシア軍の増派を阻止し、先に降着した部隊を孤立させた。
ウクライナ軍の空港警備部隊と予備の機動打撃部隊が、航空攻撃、砲撃の支援を受け、孤立したロシア部隊を撃破した。
結局、ロシア空中機動部隊は、数日内に壊滅的損耗を被った。
図1 ロシアのヘリボーン作戦(イメージ)

出典:各種情報に基づき筆者作成(以下同じ)
(2)米軍によるベネズエラ奇襲作戦
米軍は2026年1月2日深夜から翌3日未明にかけて、ベネズエラの首都カラカスを中心として作戦を妨害するであろう軍事施設を爆撃・破壊した後に、特殊部隊デルタフォースのヘリボーン作戦によりベネズエラ大統領を拘束・連行した。
この作戦では、米軍の最先端の兵器が投入され、電子戦やサイバー戦が行われ、拘束・連行時に負傷者が多少出たものの、作戦そのものは確実に目的を果たした。
空中機動作戦開始前の事前破壊
(1)空中機動作戦の弱点を除去する作戦開始前の爆撃
空中機動作戦の最大の弱点は、空中機動時と降着時の約1~2時間だ。
この間は戦力が発揮できない時間、つまり戦えないのである。空中機動時に防空兵器で攻撃されれば、攻撃部隊も輸送機なども空中で破壊されてしまう。
降着時に使える兵器は兵士が携行している小銃・機関銃・手榴弾・携行可能な迫撃砲だけだ。時間の経過とともに、部隊の増強、軽戦車など重装備の追送、戦う弾薬の補給をしなければならない。
もしも、戦力が増強される前に戦車などから攻撃され、火砲の砲弾が撃ち込まれれば、対抗できる手段が全くなく破壊されてしまう。
そのため、空中機動の経路上、および降着直後に攻撃してくる部隊や兵器を、航空攻撃やミサイル攻撃で事前に破壊しておかなければならない。
事前に破壊するには、防空兵器、戦車や火砲などの位置、あるいは降着部隊を撃破する機動打撃部隊の位置の情報を入手しておく必要がある。
その上で航空攻撃やミサイル攻撃で、組織的な戦闘ができないように破壊するのである。
図2 降着したヘリボーン部隊への反撃(イメージ)

(2)効果的な事前破壊ができていなかったロシア軍
ロシアは、ヘリボーンの第1波が空港に降着し、ウクライナの空港警備部隊と戦い、それらを退けて、その日のうちに占拠することができた。
このことで、空港を直接警備していたウクライナの少数の部隊や防空兵器は、戦闘機による空爆、ミサイル攻撃、攻撃ヘリコプターからの攻撃により相当の被害を受けた。
作戦開始前の爆撃等の効果が、ある程度あったと考えられる。
しかし、ロシアの大規模空中機動部隊やキーウに北部から迫る地上部隊への対処のために、キーウ周辺に配置されていたウクライナ軍の予備機動打撃部隊と火砲は、爆撃を受けずに残存していた。
ロシアは、作戦を妨害する可能性があるものをすべて破壊していなかったわけだ。また、状況の変化によって妨害する部隊が出現してくれば、それを直ちに叩き潰す準備もできていなかったようだ。
もしも、これらウクライナ軍の予備部隊や防空兵器までも空爆できていたら、ロシアの後続部隊の第2波、第3波が投入され、空中機動作戦は成功していただろう。
(3)ベネズエラ防空兵器等を事前破壊していた米軍
米軍は、電子戦や各種偵察衛星などを使ってあらゆる情報収集を行っていた。そして、開発中の情報共有システム(米空軍を中心としたABMS Advanced Battle Management System:先進戦闘管理システム)から、ステルス戦闘機や爆撃機に対して攻撃目標を提供していた。
この情報は、常に最新のものに入れ替えられる。
米国は得られた情報によって、ロシアとは違い、作戦を妨害する可能性があるものすべてを破壊していた。また、状況の変化によって妨害する部隊が出現してくれば、それを直ちに叩き潰す準備もできていた。
米軍のヘリボーン作戦が全く妨害されなかったのは、反撃の可能性がある防空兵器や反撃部隊を事前に破壊していたからと考えられる。
空中機動、降着、戦力増強中に反撃部隊撃破
(1)反撃部隊撃破の必要性
空中機動、降着および第2・第3波による戦力増強まで、あるいは目的達成(例えば拘束・連行)までは、常に敵地上部隊、防空兵器、航空攻撃などの反撃を受ける可能性がある。
反撃できないように事前に破壊する必要があるが、生き残っている部隊や兵器への対応も準備しておく必要がある。
これに対しては、ステルス戦闘機を保有していれば、空中機動部隊の要求に応じて、迅速に対地攻撃やミサイル攻撃を実施することができる。
敵の反撃に対して、航空攻撃などの攻撃ができなければ、地上部隊との提携までは、空中機動部隊は孤立して戦わなければならない。
(2)ロシアのウクライナ反撃部隊への攻撃
空港に降着したロシアの空中機動部隊は、輸送機による増援も実施できず、数日以内にウクライナ軍の攻撃により壊滅的被害を被ってしまった。
ロシアは、輸送機による増援を阻止する防空兵器を破壊できず、空港に降着した部隊に対して反撃する予備の機動部隊や砲兵部隊を、航空攻撃やミサイル攻撃で破壊することができなかったのだ。
ロシア軍のキーウ近郊への空中機動作戦が、戦争の天王山であったことを考えれば、ロシアは保有数が少ないステルス戦闘機も全機投入し、作戦部隊を近接航空支援すべきであった。
だが、ロシアはステルス機を投入しなかった。その理由は、運用上の制約・リスク判断など複数の要因が考えられるが、ステルス性能が期待するほどではなかった可能性もある。
他方、作戦部隊を電子戦で支援するという計画もあったはずだ。
本来であれば空中機動部隊と地上部隊が提携する計画だったと思うが、地上から参戦していたロシアの電波妨害機は、侵攻初期にウクライナ軍に破壊された。
破壊されなかった妨害機はウクライナ領土に置き去りにされ、ロシア兵は自国へ撤退してしまった。
このため、ロシアの電波妨害機は、ウクライナ軍の指揮機能を妨害し、ロシアの空中機動作戦を支援することはなかった。
近代戦においては、電子戦で情報収集し敵の指揮機能を停止させるために、電波妨害、それも特定の兵器に絞って妨害することは必須である。
だが、ロシアはできなかった。最大の失敗である。
(3)ベネズエラ奇襲作戦中に反撃受けなかった米軍
米軍特殊部隊がベネズエラ大統領を拘束する作戦の間、大統領警護隊による抵抗はあったものの、地上軍機動部隊を投入した米軍ヘリを防空兵器が撃墜したという情報はない。
もし、ベネズエラ軍による反撃が行われたとしても、ステルス戦闘機がリアルタイムでベネズエラ軍の正確な動きを得ていたことから、反撃部隊を容易に撃破できたことであろう。
また、米軍が「EA-18Gグラウラー」電波妨害機を使って、地上部隊の指揮統制、防空兵器レーダーを妨害したことにより、ベネズエラ側は、身動きが取れなかったと考えられる。
米国は作戦を実行する際に、偵察衛星情報や電子戦情報で、そしてリアルタイムに提供できる情報提供システムを使って、ベネズエラの事前に反撃する部隊、反撃の可能性があるすべての部隊を情報収集と分析で確認し、破壊していたようだ。
さらに米国は、ベネズエラの反撃部隊を殲滅するか、残存部隊があっても攻撃できないような電波妨害を行った。
残存部隊へ指揮命令を届けさせないように、またレーダーなどの電子機器が機能しないように妨害していたと考えられる。
両国の空中機動作戦の秘匿
空中機動作戦は、いつ、どこに、どれほどの規模で実施するかについて、敵に絶対に知られてはならない。
具体的には、空中機動作戦実行前に、輸送するヘリや輸送機がいつどこの空港に集められるか、軽戦車(空挺戦車)や空挺兵の搭載がいつどこで行われるかなどだ。
これらのことを敵の偵察衛星に発見されてはならないのである。
ロシアの空中機動作戦が行われることは、侵攻前日の2月23日には、ウクライナは米国情報機関から知らされていたという。
ただ、大規模なのか小規模なのかは判明していなかったらしい。ウクライナは、完全に準備することはできなくとも、関係部隊に情報を流し、ある程度の準備はできていたであろう。
米軍のベネズエラ奇襲作戦では、ベネズエラ軍関係部隊は全く対応が取れなかったことから、ベネズエラには米軍の作戦が漏れていなかったと考えられる。
ベネズエラとしては、各種防空兵器をロシアから購入して準備していた。したがって、米軍が「ベネズエラの周到に準備した防空網をかいくぐって空中機動の奇襲作戦を実施する」とは思ってもいなかっただろう。
さらに、ロシアはウクライナ戦争で手一杯であり、ベネズエラに情報提供できるほどの余裕はなかったのかもしれない。
ロシアの空中機動作戦について、ウクライナは直前ではあったが事前に知っていた。一方、ベネズエラは可能性を認識していてもロシアなどから情報提供はなく自らも察知できなかったと考えられる。
作戦の成否は情報・保全次第
ロシアがウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を暗殺する計画について、ウクライナはかなり警戒していたとみられている。
実際、ウクライナの大統領府顧問は侵攻から2週間で12回以上の暗殺未遂があったと発表している。
また、「我々は非常に強力なインテリジェンスと防諜ネットワークを持っている」「ロシアの情報機関の連邦保安局内にも内通者がいて、その情報で未然に防ぐことができた」とも語っている。
ロシアは、ウクライナ侵攻と同時にキーウに潜入し、ウクライナの大統領を暗殺するか、拉致して連れ去ろうとした可能性がある。
しかし、ロシア軍の空中機動作戦の失敗もあり、未遂に終わったのではなかろうか。
一方、米軍はベネズエラの大統領を拘束しようとした特殊部隊に負傷者は出たものの、短時間に大統領を拘束し、米国本土まで移送してしまった。ほぼ完璧と言える成功である。
私は、米国のサイバー専門家、通信情報収集機関からの情報、工作員の情報、特に大統領周辺の最新情報が役に立ったのではないかと考えている。
ウクライナのゼレンスキー大統領は、2022年7月にロシアの工作にかかわったということで、ウクライナの検事総長と情報機関の保安局長官を解任した。
その理由は、両氏が管轄する機関の職員60人以上が、侵攻するロシア軍の作戦に協力した疑いがあったからだという。また、それまでに国家反逆の疑いで、650件を超える数の捜査が進められていると説明した。
ウクライナ国内には、ロシアの大量の工作員が潜入していたようだ。しかし、侵攻前後にはその存在の多くが解明されて拘束されたとみられる。
戦争においては、潜入工作員に関する情報収集と工作員に情報を与えない保全の重要性がよく分かる例である。
非正規戦による事前潜入と工作が思うようにいかなかったのも、ロシアの空中機動作戦が成功しなかった一因なのだろう。
戦況をなかなか好転できないロシア
ロシアのウクライナ侵攻以前、ロシアの軍事力は米軍と同レベルか、あるいは近づきつつある、一部では米軍を超えるという見方もあった。
だが、この4年間のウクライナ戦争の実態から、それは幻想であったようだ。
空挺・ヘリボーン作戦は、戦争で最も重大な局面で実施される。その成否がその後の戦争遂行にきわめて重要な役割を果たす。
もしも、ロシアの侵攻当初のキーウ近郊への空挺・ヘリボーン作戦が成功していれば、キーウは陥落していた可能性がある。
一方、米軍のベネズエラ奇襲作戦がもし失敗していれば、米国のドナルド・トランプ大統領は世界中から強い批判を受け、大統領の尊厳は失墜していたかもしれない。
このような最重要場面での作戦を実行するためには、最大の軍事技術を用い、最高レベルの軍事作戦を立案しなければならない。
今回、米国とロシアの作戦を比較し、軍事技術や軍事作戦能力の差がかなりはっきりしたと思う。
その差は、米国の情報と兵器を使うウクライナとロシアとの関係にも当てはまるはずだ。すでに4年を超えたウクライナ戦争でロシアが戦況を好転させたければ、この差を縮める必要がある。
時代遅れになったロシアの戦い方
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナ戦争実行の決断にあたって、軍事パレードに登場する兵器、パレードの威容を見て、「素晴らしい軍隊だ。旧ソ連時代の軍隊が復活し、米軍と比肩する軍隊だ」と自信を持ったに違いない。
しかし、米軍とロシア軍の戦闘能力の差、つまり、戦ってみなければ分からない目には見えない部分の兵器の性能、宇宙空間を使った情報戦、電波妨害や敵情解明に力を発揮する電子戦、新たな兵器を生かす将軍たちの作戦・戦術能力等は理解が不十分だった可能性がある。
両国の空中機動作戦を分析してみて分かるのは、侵攻当初のロシアの空中機動作戦は半世紀も前の戦法のようであり、米軍のベネズエラ奇襲作戦は近代兵器が遺憾なくその能力を発揮した「2026年最新の戦法」だったことだ。
プーチン大統領は、自国軍の能力を完全に見誤って戦争を開始したのではないか。
米欧の兵器と情報を十分ではないにせよ供与されていたウクライナ軍についても見くびっていた可能性がある。
ロシアは、力と量で攻めまくれば短期間でウクライナを占領でき、たとえ短期間では難しくても消耗戦でウクライナは音を上げると思っていたのだろう。
その考えをおそらく今も持ち続けているに違いない。しかし、ベネズエラでの米軍の作戦は、その考えが時代遅れであることを証明してしまった。プーチン大統領はそのことを認識し、一刻も早く戦争をやめるべきである。

米空軍の早期警戒管制機E-3(冒頭の写真は胴体の上についた円盤の部分、米空軍のサイトより)
良ければ下にあります
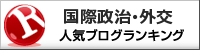
を応援クリックよろしくお願いします。







![]()