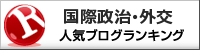11/26The Gateway Pundit<US Military Deployment in Latin America Isn’t Just About Venezuela, But to Push Russia, China and Iran Out of the Western Hemisphere (VIDEO)=米軍のラテンアメリカ展開はベネズエラ問題だけでなく、ロシア、中国、イランを西半球から追い出すためでもある(動画)>
ベネズエラ攻撃は麻薬取引阻止だけでなく、世界の不正選挙の拠点潰し。
西半球をめぐる戦いが始まった。
2年10か月前、私がTGPに寄稿するようになる約45日前に、私は「南米の混乱」という個人ブログに記事を書き、 「手遅れになる前に、米国はいわゆる『裏庭』に細心の注意を払ったほうがよい」と警告した。
1,034日前、世界が今日よりもずっと暗いように見えた頃、私はこう書きました。「地獄のバイデン政権がラテンアメリカに対して、甚だしい災厄とも言える外交政策を実行していると言っても、誰も驚きはしない。『Roubinette』はあらゆる面で大惨事であり、この外交政策は彼の狂った政策の要となっている。」
しかし、「cone Sur」におけるすべての出来事がバイデン一家のせいというわけではありません。この状況には、組織的な責任も一部あります。ここ数十年、南米亜大陸はほとんど注目されていません。9.11以降、大局的な視点から見ると、南米亜大陸は取るに足らない存在になったようです。
ある意味、私はブラジルのリオデジャネイロに住んでいるので、「西半球の重要性も真剣に考慮した90度の方向転換を望んでいる」と書くのは、自分勝手な議論だった。
[…]基本的な生存の知恵は、私たちが自分のすぐ近くの地域をとても大切にすべきだということを示唆しています。それは人々に対しても、そして国に対しても当てはまります。」
しかし今、ドナルド・J・トランプが政権に復帰し、米国がラテンアメリカを再び主要な勢力圏として取り戻そうとしていることは疑いの余地がない。
ラテンタイムズは次のように報じた。
「新たな報告書によると、カリブ海における米国の作戦は、ベネズエラ政権を権力の座から排除することを目的としている可能性があるが、中国とロシアを西半球から排除することも目的としている可能性がある。」
フォックス・ニュースは、エリック・シュミット下院議員の発言を引用し、「自国の利益は自国の半球で尊重されるべきだ」と述べた。同ニュースは、米国が独裁的なニコラス・マドゥロ大統領をはじめとする高官が率いていると非難している、カルテル・デ・ロス・ソレスをテロ組織に指定したこと、CIAの秘密作戦の漏洩、そして独裁的なニコラス・マドゥロ大統領への懸賞金を誇示するビラ投下の可能性など、最近の動きは、政権に対する心理作戦の一環と思われると指摘した。
読んでください:イラン、ラテンアメリカでの存在感を保つためにベネズエラのマドゥーロを支援している。

https://x.com/i/status/1993034832411345346
一方、NewsNationの記者ケリー・マイヤー氏は、米南方軍(サウスコム)が、近日中に起こりうる地上攻撃に備えて、感謝祭とクリスマス休暇中の休暇を制限していると報じた。マイヤー氏は、地上攻撃の可能性は「今後10日から2週間以内」に発生する可能性があるとの情報筋を引用した。
同時に、統合参謀本部議長は月曜日にカリブ海諸国を訪問する予定だ。ニューヨーク・タイムズ紙は、事情に詳しい2人の関係者の話として、ダン・ケイン統合参謀本部議長の訪問理由は感謝祭を前に兵士たちに感謝の意を表すためだと報じた。
https://www.thegatewaypundit.com/2025/11/us-military-deployment-latin-america-isnt-just-about/




ケイティ・ロジャース女性記者はトランプの健康状態について好ましくない記事を掲載した。トランプ大統領は「2017年の大統領就任1年目と比べて、公式行事の予定は減っており、国内旅行も大幅に減っているが、海外旅行は増えている」と書いた。


11/26Rasmussen Reports<Voters Still Not Sold on Trump’s Plan for 600,000 Chinese Students=有権者は依然としてトランプ大統領の60万人中国人留学生受け入れ計画に納得していない>
ドナルド・トランプ大統領が提案した、中国からの留学生60万人が米国の大学に入学することを認めるという提案は、有権者の抵抗に遭い続けている。
ラスムセン・レポートによる最新の全国電話・オンライン調査によると、米国の有権者の43%がこの提案を支持しており、これは 9月の41%からわずかに増加した 。そのうち13%は、これほど多くの中国人留学生を米国の大学に受け入れることに「強く支持」している。反対は44%で、そのうち24%は「強く反対」している。






11/27阿波羅新聞網<高市逆转?惊爆和川普在直升机上谈妥机密—中国疯狂宣传高市早苗改口 矢板明夫:美日机密早在直升机上谈妥=高市は逆転?衝撃報道:トランプとヘリコプターで秘密協議――中国、高市早苗の言い方を変えたのを大々的に報道、矢板明夫:日米間の秘密協議はヘリコプターで>中国は、日本の「存立危機事態」に関する発言に対し、天地を覆うほどの外交的報復措置を開始した。高市早苗首相が「台湾の法的地位を定める立場にはない」と表明した今回の発言は、中国政府によって「言い直し」と広く報道された。インド太平洋戦略シンクタンクの矢板明夫事務局長は、トランプ大統領の前回の訪日時に、高市が空母ジョージ・ワシントンの視察に同行したとき、二人は米軍のヘリコプターに乗り、着陸前に40分間旋回し、「機内では多くの重要な事項が話し合われた」と指摘した。
日米首脳会談の再現映像からは、ヘリコプター離陸後の一連の興味深い展開が明らかになった。矢板明夫は、記者たちは当初、ヘリコプターが東京から横須賀へ向かうと想定していたが、実際には仙台へ向かったと指摘する。記者たちは皆、別の基地へ向かっているのではないかと疑っていた。ヘリコプターには10数人ほどしか乗れず、トランプの隣に座っていた高市は騒音が大きかったため、耳元で話し合わなければ互いの声が聞き取れなかったという。
日米首脳間の秘密会談は、おそらく全て英語で行われたと思われる。矢板は、高市はかつて米議会で補佐官を務めていたため、日常的な英語でのコミュニケーションには問題がないだろうと見ている。そのため、2人がヘリコプター内で台湾問題を議論したのではないかとの憶測も飛び交っている。
ニュートークのコラムニスト、陳文甲は、トランプの行動は特に巧妙だったと考えている。トランプによる日本支持は、当初トランプ自身が表明したものではなく、駐日米国大使のグラスを通じて表明された。グラスは「我々は日本を支持する」と述べた。大使は一国を代表するので「非常に念入りで手が込んだやり方」だった。

矢板明夫は、トランプ米大統領が日本を訪問した際、高市が空母ジョージ・ワシントンの訪問に同行したことを指摘した。二人は米軍のヘリコプターに乗り、着陸前に40分間も旋回した。「機内では多くの重要な議題が話し合われた」 (画像:YouTubeのスクリーンショット)
高市首相が「台湾の法的地位を定める立場にはない」と表明したのはサンフランシスコ条約に書いてあることを説明しただけ。中共の言う「言い直し」ではない。
https://www.aboluowang.com/2025/1127/2311470.html
11/26阿波羅新聞網<赖清德怒吼:台湾绝不臣服中共=賴清徳、台湾は中共に屈服しないと怒って叫ぶ>中共は台湾に対する言葉と軍事による脅迫を強め、中華民国の管轄権を弱め、台湾を併合しようとしている。 26日、中華民国総統の頼清徳は、2つの主要な国家安全保障行動計画を発表し、民主的な台湾を守るため、戦力強化と非対称戦能力を向上させるため、1兆2500億台湾ドルの国防予算の追加を提案した。ワシントン・ポスト紙への寄稿で、頼清徳は、台湾は中共の侵略を抑止するために国防能力を継続的に強化していく。
https://www.aboluowang.com/2025/1126/2311234.html

何清漣 @HeQinglian 6h
WSJ:「自らを『ネズミ人間』と呼ぶ若い世代が、中国の消費チャートを書き換えている」。ますます多くの若い中国人が、狭い部屋に閉じこもり、社交を避け、長時間ベッドに横になってスマホをスクロールする「ネズミ人間」になることを選んでいる。 「寝そべり」と「低欲求」のライフスタイルの拡大は、消費主導の経済成長を促進する中国の取り組みを複雑化させている。
もっと見る
cn.wsj.comより

何清漣 @HeQinglian 4h
👇 この投稿は、中国の若年層の就職難によって引き起こされた「ネズミ人間」(若者の失業)現象について言及している。世界最大の大国である米国の状況は以下の通り:米国労働統計局が11/20に発表した月次データによると、25歳以上で学士号以上の学位を持つ失業者数は9月に190万人を超え、全米の失業者数の4分の1を占め、1992年の統計開始以来、最も高い割合となった。
US Trading
もっと見る
引用
何清漣 @HeQinglian 12h
WSJ:「自らを『ネズミ人間』と呼ぶ若い世代が、中国の消費チャートを書き換えている」。ますます多くの若い中国人が、狭い部屋に閉じこもり、社交を避け、長時間ベッドに横になってスマホをスクロールする「ネズミ人間」になることを選んでいる。 「寝そべり」と「低欲求」のライフスタイルの拡大は、消費主導の経済成長を促進する中国の取り組みを複雑化させている。
https://cn.wsj.com/articles/%E8%87%AA%E7%A7%B0-%E8%80%81%E9%BC%A0%E4%BA%BA-%E7%9A%84%E5%B9%B4%E8%BD%BB%E4%B8%80%E4%BB%A3%E6%AD%A3%E5%9C%A8%E6%94%B9%E5%86%99%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%9B%BE%E6%99%AF-4d189dd8?mod=cn_hp_lead_pos1
阿古氏の記事で、先ず言いたいことは、30年も中国を研究していて、早くから中国のリスクを見抜き、国民に警鐘を鳴らすことができなかったのか?小生は1997年から8年間中国にいて、いやというほど中国の厭らしさ、「騙すほうが賢く、騙されるほうが馬鹿」というのを見てきました。それで国会議員やその秘書に中共のリスクを伝えてきましたが、殆ど信じて貰えなかった。東大の研究者の肩書があれば、小生なんかより遥かに信じて貰えたでしょう。それを今頃になってリスク管理を説くのは遅すぎでしょう。小生は2014年からブログを書き始め、メインは中国関連でスタートし、今は米中中心としています。
阿古氏は、日本はトランプの米国から自主独立の姿勢をより鮮明にすべきと考えているようですが、核も持たない、憲法9条で自衛隊の行動が軍でないため制約を受けている中で、どのように日本の安全を確保していくのか聞きたい。日本の周りには中共だけでなく、ロシア、北朝鮮など核を持った狂国があるというのに。核保有と憲法改正に賛成しますか?日高義樹氏に以前聞いた話で、「米国では、軍事を知らないエリートはいない」と。阿古氏が学界のエリートと思っているなら、もっと軍事について勉強したら。
記事
11月7日の衆議院予算委員会における高市早苗首相の「存立危機事態」に関する答弁に中国政府が反発し、日本への渡航自粛要請を出すやいなや、日本行きツアーの中止や留学プログラムのキャンセルなどが相次ぎ、日本行きの航空便も減便されている。19日、中国政府は水産物の輸入を停止する方針を日本に示した。
高市首相がどのような経緯で答弁を行ったのか、その内容が妥当であったのか、あるいは、そもそもどのような条件が「存立危機事態」に該当するのかなど、日本国内では活発な議論が行われている。
日本国内でのこうした議論は非常に重要だが、残念ながら、中国政府がその意義を理解するはずがない。意義があると感じる人がいても、厳しい言論統制下においては、そのような姿勢を示した人は処罰される。
しかし、中国政府による言論空間の遮断を意識した上で、日本のリスク管理や国益について考え、議論しようとする人が日本にはほとんどいない。私はそのことに危機感を持ち、この文章を書いている。

〔PHOTO〕gettyimages
現在の日本における中国理解はあまりにもお粗末な状態だ。政府、国会議員、メディア、国民の各層において、中国の動きを捉える上で重要な情報、中国政府とその関係機関による言論統制の特徴、彼らが作り出すナラティブ(語り)を把握できていない。
しかし、その責任は研究者にもある。なぜなら、日本の中国研究者が見るべきところを見ていないし、書くべきこと、言うべきことを表現していないからだ。
中国研究者として少しでも責任を果たすべく、私は日中関係の緊張に関連して、以下の3点を強調したい。
- 中国政府のナラティブには意図がある。それに煽られると日本は国益を損なう。
- 日本にとっての正論は現在の中国政府には通じず、日本は中国のナラティブを覆すナラティブを生み出す必要がある。
- 人間性の破壊が深刻なレベルにまで及んでいる中国と同じ土壌で闘おうとせず、弱みを握られることを避け、淡々と日本自らの目的と利益を見据える。
- 中国政府のナラティブには意図がある。それに煽られると日本は国益を損なう。
高市首相のこれまでの中国への姿勢を考えれば、遅かれ早かれ、中国の反発を引き起こすというシナリオは描けるし、中国政府は高市首相の言動を予想していたはずだ。
10月31日に、APEC首脳会議に出席するため韓国を訪問中に、高市首相は習近平国家主席と約30分間、首脳会談を行った。比較的和やかな雰囲気で行われたように見えるこの首脳会談から1ヵ月も経たないうちに、中国政府は日本を一気に奈落の底に突き落とすかのように、数々の経済制裁をかけ始めた。
その上、外務省の金井正彰アジア大洋州局長と中国の劉勁松・外務省アジア局長が18日に協議した際には、劉氏が両手をポケットに入れたまま、金井局長を見下すかのようにして話している様子を中国国営中央テレビが報じた。
その前には薛剣駐大阪総領事が、高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁に対し「汚い首は斬ってやるしかない」と自身のX(旧ツイッター)に投稿した。21日には在日本中国大使館が、国連憲章の「敵国条項」により、中国は安全保障理事会の許可なしに日本を軍事攻撃できるとまで、公式Xで主張した。
あまりにも、居丈高で荒唐無稽な主張に世界中の人々が憤るというよりも呆れているのではないかと思う。
しかし、日本はこうした中国政府の言行を決して額面通り受け取らず、日本を煽るために意図的に行なっているととらえ、必要最小限の抗議を行うにとどめた方がよい。それは、中国の関係者にはこうせざるを得ない状況があるからだ。
日本への制裁は、経済的な相互依存関係を考えれば、中国にも大きな損失及ぶ。それでもやらざるを得ないのは、国内には現政権の失政に対して不満が渦巻いており、中国政府は外に敵を見出すことで矛先の方向を変えようとしているのだ。
極度に権力を集中させる権威主義国家の言論環境は、日本のそれとはまったく異なる。言論統制の下、多くの人が監視や検閲を受け、家族を人質に取られるような形に追い込まれるなど、恐怖を感じながら生活している。民主主義国では考えられないような形で不当な罪を科され、投獄されている人もいる。統制下にあるため、こうした実態の多くは語られておらず、大半の日本のメディアも研究者も把握できていない。あるいは、ある程度把握できていても、中国政府の圧力を恐れて、積極的には伝えていない。
- 日本にとっての正論は現在の中国政府には通じず、日本は中国のナラティブを覆すナラティブを生み出す必要がある。
思考経路や意識形態のまったく異なる中国政府と日本の常識をもって向き合っても、通じるはずがない。中国政府やその関係者の発言や行動の一つひとつに憤る世論に反応するのではなく、大局を見て国益をとらえ、政策を打ち出すべきだ。
特に、私は次の3つのナラティブを打ち出すことで、中国のナラティブに抵抗することが重要だと考えている。
(1)軍国主義復活を覆すナラティブ
中国は度々、国際機関の場を使って日本が軍国主義を復活させようとしていると批判している。
11月21日には国際原子力機関(IAEA)の理事会で、中国代表の李松氏が高市政権が「非核三原則」の見直しを否定しない姿勢に懸念を示し、高市政権の安全保障政策が「軍国主義」の復活を招きかねないと述べた。このように日本を威圧する方法で、国際社会の支持を得ようともくろんでいる。
日本が行うべきことは、中国のナラティブを根底から覆すようなナラティブをつくることだ。日本は抑止力を重視しているが、防衛組織の指揮・統制において、シビリアンコントロール(国民の代表者である文民による統制)を確実にしていることを強調する。
実際にこれは民主主義国家に不可欠な制度であり、防衛組織が暴走するのを防ぎ、防衛力を政治や民意に基づいて運用していることをていねいに説明すべきであろう。そして、日本は口だけでなく、実際にシビリアンコントロールを確実にするための具体策を打ち出さなければならない。
「非核三原則」の見直しについても、決して方向性が決まっている訳ではなく、開かれた言論環境でさまざまな意見を交わし合い、徹底的に議論することを強調すべきであろう。
(2)民主主義のナラティブ
1972年、日本は中華人民共和国と国交を正常化したことによって、台湾(中華民国)との公式な外交関係を解消した。しかし日本は、非政府間の実務関係として台湾との関係を維持するという「曖昧戦略」を採用してきた。つまり、台湾と中国の法的地位に関して、日本に直接関与する余地はない。
一方で、中国政府は日本の政治家らが述べる「台湾有事は日本の有事」という言葉尻をとらえ、日本は「内政干渉」しているとして大々的に批判を展開している。日米同盟を結んでいるのだし、日本の領土や領海で武力衝突が起きた場合、日本政府が何らかの措置を講じ、日本を防衛しなければならないのは当たり前であるが、中国政府が日本の側に立ってナラティブを作ることは考えられない。
こうした中国のナラティブに対抗し、日本の立ち位置を説明する際に、私は日本が民主主義国家であること、その前提で他国との関係を構築する必要があることを強調すべきだと考える。民主主義の原則に基づくなら、中国と台湾がどうあるべきかについては、当事者である中国と台湾の人々が議論して決めるのであり、一部の権力を持つ人間が独占的に判断すべきではない。
外務省のホームページの「よくある質問集」問10の回答(https://www.mofa.go.jp/mofaj/comment/faq/area/asia.html)には、「政府としては、台湾をめぐる問題が両岸の当事者間の直接の話し合いを通じて平和的に解決されることを希望しています」と書かれているが、さらに一歩踏み込み、中国と台湾の人々の意思が尊重されるためには、中国が国家権力による言論統制をやめ、人々が自由に議論できる開放的な言論環境が必要であることを明確にすべきだろう。
これは日本にとって内政干渉ではない。戦後日本が並々ならぬ努力を重ねて作り上げた民主主義を存続させることは、日本にとって死活問題である。民主主義を普遍的な価値とする国際秩序を、権威主義が脅かす構造を何としても変えなければならない。
(3)自主独立のナラティブ
日本はアメリカと同盟関係を結んではいるが、自主独立の姿勢をより鮮明にすべきだ。特に、民主主義を後退させているトランプ政権とは適切な距離を取り、アメリカに依存しすぎない体制を整える必要がある。
防衛費の増額についても、決してアメリカの圧力に屈する形で行ってはならないし、そのように見られないように、日本として何に重きを置き、何を目的に、どの部分を増額するのかをわかりやすく説明すべきであろう。
防衛関係は機密情報が多いとして、必要な情報公開を行わないならば、「国家安全の優先」を言い訳に言論統制を続ける中国と変わらなくなる。特に、急激に予算が膨らむセクターというのは利害関係が複雑で、会計監査も不十分になりやすい。より一層、国民とのコミュニケーションを図る努力をすべきだ。
- 人間性の破壊が深刻なレベルにまで及んでいる中国と同じ土壌で闘おうとせず、弱みを握られることを避け、淡々と日本自らの目的と利益を見据える。
私は大学入学以降、30年以上かけて中国研究を行ってきたが、ここ数年、中国の言論・思想の統制と経済状況の悪化は相当深刻なレベルにまで達していると強く感じる。
監視や検閲は隅々にまで及び、5〜6人で社会問題について読書会を組織するだけでも、警察が尋問にやってくる。バーやカフェ、小さな活動拠点で行われるフェミニズム、同性愛、労働問題、貧困問題、環境保護などを扱う活動にも警察は目を光らせており、組織力のある人物は徹底的にマークされる。
10月にはおよそ30名の非公認教会(家庭教会)である「シオン教会(錫安教会)」の牧師・教職者が一斉に拘束された。ウイグル、チベット、モンゴルなど少数民族への弾圧、香港の凋落ぶりは指摘するまでもないだろう。
当事者のプライバシーと安全に関わるため、ここで詳しく書くことはできないが、何人もの私の友人や知人が精神を病み、自殺に追い込まれ、不当に財産を奪われたり、冤罪を科されたりもしている。
さまざまな制限を受け、リスクがあっても自分らしく思考し、行動しようとする知識人やジャーナリスト、活動家たちから得られる情報は貴重であるが、彼らの安全や精神状態への配慮を慎重に行い、信頼関係を着実に築くことができなければ、彼らとの交流や情報交換を円滑に行うことはできない。情報統制の壁の中と外で、複数のニックネームやペンネームを使い分けながら活動することが多い彼らの動きをとらえるのが、難しい側面もある。
さらに、情報機関などとつながっている「両面人」(表と裏の顔を使い分けて行動する二面性を持つ人物)を見抜く力がなければ、情報機関の観察対象として「泳がされて」しまったり、間違った情報を鵜呑みにしてしまったりすることもある。権力側から金品をもらったり、特別な待遇を与えられたりして情報の収集や分析にあたる人物もいる。彼らは立場の弱い状況にあり、狙われてしまうことが多い。
例えば、資金不足や借金に苦しんでいる、家族の病気に悩んでいる、家族や友人が監視下に置かれている、不倫などの問題を抱えているといった状況である。虚栄心がある、媚びへつらいをする、確固とした信念がなく考えが揺らぎやすいなど、性格を読まれて、誘い込まれる場合もあるだろう。日本に関わる中国の政策担当者の暴言や失礼な振る舞いにも、こうした裏があるかもしれない。
私は、人間性の破壊が深刻なレベルにまで及んでいる中国と同じ土壌で闘おうとせず、弱みを握られることを避け、淡々と日本自らの目的と利益を見据えることが重要だと考える。
例えば、国レベルで見れば、ウクライナではエネルギー業界をめぐる約1億ドル規模の巨額汚職事件が発覚し、この捜査を受けて、エネルギー大臣や司法大臣らが辞意を表明・職務停止となった。
米国は長らく、ウクライナが効果的な汚職対策と改革を実行することを、支援継続の重要な条件としており、ウクライナ国内の汚職による政治的混乱が、トランプ大統領などによるロシア寄りの和平案を受け入れさせるための「弱み」として利用されるかもしれない。
世界の多くの国で政治家のエゴや自国優先主義が顕著になる中、国内の混乱や分断が利用されないように、鋭い分析力と表裏を使い分けた戦略によって、日本の弱みにつけ込んでくる浸透工作に断固として立ち向かわなければならない。
個人レベルにおいても同じことが言える。中国共産党政権の過酷な環境で苦しむ人に同情し、リスクがある中でも良心と勇気を持って行動しようとする人々をさまざまな形でサポートすることが権威主義国家の基盤を崩し、日本の民主主義を守ることにつながる。さらに、この厳しい状況の下では、権力に擦り寄り、嘘と欺瞞に塗れた生活を送っている人もいるという現実を、できるだけ冷静かつ客観的にとらえ、対策を考える必要もある。
戦後、日本人が享受してきた民主主義と自由、そして平和はこれからも無条件で続くわけではない。自らが意識してリスクを管理し、方向性を定めていかなければ、知らず知らずのうちに進みたくない方向に進み、取り返しのつかないことになる。日本人は今こそ、「平和ボケ」の状態から脱却しなければならない。
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。