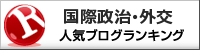10/31Rasmussen Reports<Trump Approval Index Month-by-Month Trump Approval Drops One Point in October=トランプ大統領支持率月次推移 トランプ大統領の支持率は10月に1ポイント低下>
トランプ大統領の支持率を日々追跡していると 、日々の変動に囚われすぎて全体像を見失ってしまうことがあります。より長期的な傾向を見るために、ラスムセン・リポートは月ごとの数値を集計しており、トランプ大統領の任期中の結果は以下のグラフでご覧いただけます。


https://x.com/i/status/1984389666175320340



https://x.com/i/status/1869020748838588638

「北極圏の霜害」は「Arctic Frost作戦」のこと。



10/31希望之声<身不由己的釜山会!习近平低头念稿、笔误成预言?川普一笑 北京暗涌!=自分の思いどおりにならない釜山会談!習近平はうつむいて原稿を読むだけ、筆の誤りは予言?トランプは笑い、北京は暗澹!>
筆の誤りは、人民日報が習近平と書くところを習近虎と書いた。ピンインが全然違うのにありえない話。トランプ・習会談は4時間の会談時間を取っていたのに、1時間40分で終わったのは、習がメモ以外のことを言えないと判断したからでは。
アレンジされて出てきた?習近平の本心と違う出演
この会談では台湾問題には触れられなかった。一見戦略的な抑制のように見えたが、実際には中共内部のより根深い政治的現実を反映していた。なぜ習近平は沈黙を守ったのか?なぜ会談はあっさりと終了したのか?答えは釜山ではなく、北京にある。
ベテランメディア専門家の郭君は、この会談は習近平の自発的な選択ではなく、迫られて出てきたものと考えている。彼女は「エリートフォーラム」での分析で、次のように指摘している。
中共四中全会後、北京の外交・経済貿易政策決定権は密かに移行した。公式報道は、過去2年間頻繁に使われてきた「敢闘」や「東の台頭、西の衰退」といった表現に代わり、「経済建設に注力する」ことと「協議を通じて安定を促進する」ことを異例にも繰り返し強調した。
こうしたトーンと方向性の変化は、外交がもはや習近平自身ではなく、党内の「党維持派」で構成される一時的な権力中核によって支配されていることを示している。このグループの主たる任務は、闘争ではなく、「出血を止めること」、つまり経済の安定、安定した外国投資、社会の安定化である。跪いてでも、経済の安定化が最優先課題である。
さらに、「トランプ・習会談」以前から、中共内では米国との交渉において2つの路線が既に形成されていた。
名目上は、何立峰副首相が中国代表団を率いていたが、実際には、米国との貿易・経済に関する文書協議の実質的なリーダーは、世界貿易機関(WTO)の元中共常駐代表である李成剛だった。李成剛は今年4月、中国に異動で戻り、米国との貿易・経済交渉の首席交渉官に任命された。表向きは習近平よって任命された形だが、彼は商務部やWTO代表団で長年勤務し、2000年代から2010年代にかけて主に国際貿易交渉を担ってきた。この系列の人事は、朱鎔基・温家宝時代のテクノクラート路線をほぼ踏襲しており、「WTO加盟」「技術的合理性」「対外開放」を重視している。そのため、政治的な分類において、李成剛は多くのウオッチャーから「改革派テクノクラート」とみなされており、その政策スタイルは習近平国家主席が率いる「政治安全保障派」とは対照的である。
トランプ・習会談のわずか数週間前、新華社通信は突如として異例の「任免公告」を発表し、李成剛が「解任された」と報じた。この発表は4月の古いデータに基づいており、本来は行政手続きの補足記録に過ぎないはずだったが、交渉の重要な局面での発表は特に微妙なものだった。数日後、李成剛は「首席交渉官」としてマレーシアに再登場し、ベセント米代表と並んで会談に出席し、何立峰と米代表の間に立った。つまり、李氏は実際には解任されていなかったということだ。
北京の政界では、この「解任したが解任なし」の報道は、中共内の権力闘争の副産物だと一般的に考えられている。
中共四中全会の前夜、米国に対して強硬姿勢で対峙すべきかどうかという問題に関して、党内に二つの路線が浮上した:一つは、習近平と何立峰が主導し、レアアース、半導体、そして軍事圧力を交渉材料として引き続き利用し、「東の興隆、西の衰退」という構図を永続させるという路線である;もう一方は、李成剛を代表とする「党の維持派のテクノクラート」が主導し、一時的な譲歩を犠牲にしても鄧小平流のプラグマティズムへの回帰を主張し、外国投資と輸出を安定させ、経済の完全な崩壊を防ごうとしていた。
「李成剛の解任とその後の復帰」という劇は、まさに2つの路線が並行して現れ、この相互牽制的な状況を反映したものである。この瞬間から、北京の政界において、これらの交渉における主導権はもはや習近平の手に握られていなかったことは明白であった。
両路線間の最も具体的な意見の相違は、レアアース問題において生じた。
10/9、中共商務部は「世界レアアース・ロングアーム管轄権」の発足を発表し、輸出規制の範囲を拡大し、段階的な施行に向けて準備を進めた。これは習派の典型的な強硬戦略である。しかしその2日後、ベセント米財務長官は、中国がレアアースを政治的武器として利用した場合、米国は代替案を全面的に実行すると警告した。この報道を受け、ロンドン金属取引所のレアアース先物は12%急落し、中国のレアアース関連株も軒並み下落した。
わずか3日後、北京は「新たなレアアース輸出規制の実施延期」を発表し、「詳細な計画を検討中」と述べた。事情に詳しい当局者によると、この決定は習によるものではなく、新設された「中央経済貿易調整チーム」の緊急介入によるものだった。金融システム系と改革派長老が率いるこのチームは、商務部よりも高い意思決定レベルを持っている。これは、習近平が重要な経済貿易問題と対米戦略に関する最終決定権を部分的に失ったことを意味する。
経済貿易に関する意思決定権の委譲は、彼の外交主導権も失わせた。 10月中旬、李強は訪米中に「米中関係は夫婦が言い争うようなものだ。意見の相違はあっても、依然として緊密な関係を維持している」と述べた。
この発言は汪洋の過去の発言に基づくもので、習の言い方とは違っている。
習近平政権発足から10年以上が経ち、中共の外交システムが公式の言説において「和して同ぜず」という比喩を用いたのはこれが初めてである。これは、かつて強調されていた「敢闘」とは対照的な、柔らかなトーンである。これを受けて、外交レトリック全体が著しく軟化し、プロパガンダシステムでは「安定」「協力」「互恵」が強調されるようになった。
こうした変化はすべて、同じ結論を導き出している:習近平は名目上は国家主席、党総書記、中央軍事委員会主席の地位にとどまっているものの、もはや自分で決定を下す権限は失っているのだ。 「トランプ・習会談」において、習近平は文書に署名するためカメラの前に姿を現すよう強要されただけだった。
これで、釜山での会談における習近平の異様に落魄した表情と、台湾問題への言及を避けた理由も説明できる。これは戦略的な抑制によるものではなく、この内部権力闘争において習近平に実質的な決定権がないためだ。彼は依然として権力の座に就いているものの、ペンと銃は奪われている。
これらすべては、四中全会以降、中共が「ポスト習近平時代」に入り、真の意思決定者が既に変化していることを示している。
https://www.soundofhope.org/post/909145
11/1阿波羅新聞網<重大破局!五角大楼夺南海?共军坐等挨揍—美菲组建特遣队 加强南海战备 反制中共=大ブレイクスルー!国防総省が南シナ海を掌握?人民解放軍、座して殴られるのを待つ ― 米比、南シナ海における備えを強化し、中共に対抗するためタスクフォースを結成>

2025年10月31日、国防総省は、米国とフィリピンが南シナ海をはじめとする地域の防衛強化のため、新たな合同タスクフォースを結成したと発表した。写真は、5/30にシンガポールで開催されたシャングリラ対話において、ピート・ヘグゼス米国戦争長官(左)とジルベルト・テオドロフィリピン国防長官が会談している様子。
国防総省は10/31(金)、米国とフィリピンが南シナ海を含む地域における協力強化と軍事態勢強化のため、新たな合同タスクフォースを結成したと発表した。
この発表は、マレーシアのクアラルンプールで開催されたASEAN国防相会議において、ピート・ヘグゼス米国戦争長官とジルベルト・テオドロフィリピン国防長官の会談後に行われた。
南シナ海、台湾、尖閣は米国にとっても重要。
https://www.aboluowang.com/2025/1101/2299100.html
10/31看中国<传钟绍军母亲被抓 空军司令马晓天被调查(图)=鍾紹軍の母が逮捕の噂、空軍司令官馬暁天は調査対象(写真)>四中全会後、中共高官失脚のニュースが相次いでいる。報道によると、空軍司令官の馬暁天が逮捕されたという。さらに、習近平の側近である鍾紹軍が国防大学の政治委員を辞任した後、その母である張淑娟が調査のために連行されたと報じられている。軍紀検査委員会が鍾紹軍の母を調査したという事実は、鍾の復帰の可能性がないことを示しているとアナリストたちは見ている。中央軍事委員会弁公庁主任が3人相次いで軍の中核的かつ最も信頼される地位から失脚したことで、習近平は真に孤立無援の状態となっている。
習はどう見ても銃口を握っていないように見える。
https://www.secretchina.com/news/gb/2025/10/31/1090132.html

何清漣 @HeQinglian 7h
ある話は、やはり言葉で述べた方が良いし、写真を残しておくのも良い。米中関税戦争の当初に私が述べたことを繰り返したい:この関税戦争は、両国の国力、指導者の決意、両国国民の痛みに耐える力の勝負である。米国は、トランプ陣営を除いて、今回は基本的に敗けたと評価している。米中の力という観点から言えば、米国が勝てなければ敗けという考えだ;ロシア・ウクライナ戦争にも同じ論理が当てはまり、NATOが勝てなければ敗北である。
もっと見る

何清漣 @HeQinglian 3h
あらゆる計算をした後、一つ忘れていたことがある。それは、中国の貿易黒字に主に寄与している国はどこかということである。これは中国の外貨準備の主要な源泉の一つである。
引用
玄门上品 @suanguaa 3時間
返信先:@HeQinglian
中国が米国市場を失えば、中国の国際貿易は崩壊するのか? ― データが真実を物語る
最近、ネット上で「中国が米国市場を失えば、中国の国際貿易は終焉する」という発言が広まっている。まるで中国の対外貿易の生命線が完全に米国に握られているかのように、はらはらするように聞こえる。しかし、データは嘘をつかない。現実は全く逆である。中国の対外貿易構造は、多くの人が想像するよりもはるかに強固で多様化している。
もっと見る
何清漣 @HeQinglian 4h
トランプ政権の不在を補うため、100人以上の米国地方自治体関係者がCOP30に出席へ https://rfi.my/C92A.X via @RFI_Cn
1月にWHに戻ったトランプ米大統領は、米国がパリ協定から再び離脱すると発表した。しかし、「America Is All In」の代表・・・・。
もっと見る
rfi.frより
高濱氏の記事では、左翼の氏にしてはキチンと高市首相を評価している。海外メデイアが悪く言っていないから、悪く評価できないのかもしれませんが。
トランプはマッドマン・セオリーを演じていて、相手に出方を読ませないようにしている。意図的にふるまっている部分が多いのでは。トランプはこういうタイプだと思わせておいて、違う行動を採る。「不確実性」こそが彼の持ち味。でも、言論の自由と民主主義の擁護は本物と思う。民主主義を主張していたバイデンの法執行機関の武器化や、アークテイック・フロスト事件の報道を見るたびに左翼オールドメデイアの酷さを思います。
日本はまだオールドメデイアを信じるのが多い。米国左翼メデイアのNYTやWP、CNNを翻訳して紹介しているだけなのに。参政党の主張に耳を傾け、既存メデイアの主張と比べたらよい。
記事

米海軍横須賀基地に停泊中の米空母「ジョージ・ワシントン」上で演説するトランプ大統領の隣に立つ高市首相(10月28日、写真:AP/アフロ)
借りてきた猫のようだったのは高市効果か
敵対国、同盟国を問わず、外交交渉では「ディール外交」「数値目標」を前面に押し出してきたドナルド・トランプ米大統領にとって、今回の訪日は一味違っていた。
ホワイトハウスに外国首脳を招き入れて行う首脳会談の冒頭の公開場面では言いたい放題、ハチャメチャな発言をしてきたトランプ氏。
だが、迎賓館赤坂離宮で行われた首脳会談ではまるで「借りてきた猫のように神妙な面持ちだった」(米シンクタンクの上級研究員K氏)
むろん、高市早苗首相が冒頭の挨拶で、トランプ氏によるタイ・カンボジア国境紛争やイスラエルとハマスのガザ地区紛争の仲介を褒めちぎり、世界平和への貢献を称賛したこともあり、ご満悦だったことは言うまでもない。
高市氏の「褒めちぎり作戦」は見事功を奏したわけだ。
これに応えたのか、トランプ氏が何と、高市氏に「何か質問や疑問、要望、日本を支援するためにできることがあれば、いつでも知らせてほしい。必ず応える」とまで言ったのには、日本側も驚いたに違いない。
トランプ氏は、さらに故・安倍晋三元首相から高市氏の話を聞いていたと振り返り「あなたは偉大な首相になるだろう」とまで言い放った。
トランプ氏が初対面の高市氏に好印象を持ったことだけは間違いない。
象徴的な成功、戦略的スタートと評価
欧米メディア、特に米メディアはトランプ氏と高市氏との首脳会談をどう評価したか、整理してみる。
ポジティブに見た報道・論調は以下の通りだ。
- AP通信は会談後、トランプ氏が「この同盟こそが強さの極みだ」と述べたことを報じた。
(For Japan’s new leader, the key to connecting with Trump could be a Ford F-150 truck)
- 英ファイナイシャル・タイムズ(FT)紙は、両首脳が「新たな黄金時代を迎える」と発言したことを紹介し、日米同盟の象徴的強化として評価した。
(Donald Trump and Sanae Takaichi promise ‘golden age’ for US-Japan alliance)
- ワシントン・ポスト紙は両国がレアアース・重要鉱物のサプライチェーンで協力する枠組みに合意した点を捉え、「中国に対抗する戦略的パートナーシップを深化させた動き」として注目した。
(Trump signs rare earth minerals deal with Japan ahead of China meeting)
一方、懸念を示したのは、以下のメディアだった。
- 英ガーディアン紙は、高市氏が就任したばかりで、「トランプ氏および米国との関係をいかに築くかは重大な外交試金石だ」と報じ、同時に「防衛費や貿易・投資といった具体的負担が日本側に問われる」との見方を示した。
(Donald Trump and Japan’s Sanae Takaichi sign agreement to ‘secure’ rare earths supply)
- 英ロイター通信は、「会談内容には具体的数値や実行スケジュールがまだ不明瞭だ」と指摘、米側が日本に対して一定の期待・要求を持っており、日本政府がその期待に応えられるかどうかを見極める必要がある、と論じている。
(What’s on the agenda for US-Japan talks?)
だが、総合的にみると、米メディアは今回の首脳会談を「象徴的には成功」かつ「戦略的には前向きなスタート」と評価している。
ただし、以下のような2つのリスクが並存している点に触れている。
- 日本の実行力(特に防衛費・投資・供給網強化)への懸念
- トランプ政権自体の変動性や要求型外交スタイル
自由で開かれたインド太平洋構想
今回のトランプ氏の訪日を見るにつけ、同氏にとって日本は、「安倍晋三の国」だったということをつくづく感じる。
大統領に最初に当選した直後、いち早く会いに来た外国首脳は安倍氏だった。初対面から気が合った。
世界の多くの指導者が気まぐれなトランプ氏との対立を避けようとしたのに対し、安倍元首相はトランプ第1期政権中に20回の会談、32回の電話会談、そしてゴルフを5ラウンド一緒に回った。
後述するマイケル・グリーン氏によると、トランプ氏は、2017年に明確なアジア戦略の構想を持たずに政権に就いた。
そのため、「自由で開かれたインド太平洋」構想を採用するよう説得したのは安倍氏だという。
同構想は、今や(ジョー・バイデン政権を挟んで)トランプ政権のアジア戦略の主柱になっている。
米国のアジア外交研究では当代屈指の専門家、マイケル・J・グリーン戦略国際問題研究所(CSIS)上級顧問・シドニー大学米国研究センターCEO(最高経営責任者)は、トランプ氏が今回の訪日で最も期待していたのは、高市氏のアジアにおける役割だと見ている。
同氏は、「フォーリン・アフェアーズ(Foreign Affairs)」最新号に「Asia’s Trump Problem: The Region Lacks Leaders who Connect with the President」というタイトルで論文を書いている。
要約すれば次のようになる。
安倍氏は米国の力が日本の国益に不可欠であることを理解し、それを形作るためにかなりの成功を収めた。
そしてトランプ氏の最初の任期中、アジアの指導者たちは彼の例に倣った。
インドのナレンドラ・モディ首相は2019年、テキサス州にトランプ氏を招き、5万人のインド系在外住民の前で演説を行った。
オーストラリアのスコット・モリソン首相とワシントン駐在のジョー・ホッキー大使は、マイク・ペンス副大統領およびトランプ氏の国家安全保障チームと緊密な関係を築き、対中戦略と南太平洋への関与に関する足並みを揃えた(肩書きは当時)。
左派出身でトランプ大統領のパートナーとは考えにくい韓国の文在寅前大統領でさえ、北朝鮮との外交を促進するために米国大統領の側に立った。
高市が安倍後のアジアを引っ張る可能性
グリーン氏はこうも書いている。
しかし、トランプ大統領の2期目において、アジアの指導者たちはトランプ氏との同盟関係を維持することに苦慮している。
2020年に病気のため辞任し、2022年に殺害された安倍氏の穴を埋めるべく名乗り出る者はいない。
トランプ大統領のこの地域へのアプローチは、いくつかの点で、1期目よりもはるかに「アジア第一主義」戦略に似ている。
中国の軍事的・経済的脅威が増大する中で、アジアの指導者たちが消極的な姿勢を見せる理由はそれだけではない。
安倍晋三というトランプ氏の盟友を失ったアジアは、米国との関係においてどこか迷走しているように見える。
その役割を、安倍氏の後継者であり、多くの点で彼と共通の考えを持つ高市早苗氏が担う可能性もある。
ただし、10月10日に連立パートナーだった(保守中道の)公明党が政権離脱したため、彼女の政治的将来は不透明だ。
しかし、トランプ政権第2期目において、これまでのところ安倍氏に匹敵するほど米国大統領との関係を進展させたアジアの同盟国の指導者は存在しない。
その結果、米国のアジア戦略は依然として混乱しており、アジアの指導者たちは中国に対する安全保障の強化など、米国とのパートナーシップの恩恵を十分に享受できていない。
(Asia’s Trump Problem: The Region Lacks Leaders Who Connect With the U.S. President)
もしトランプ氏がその役割を本当に高市氏に期待しているとすれば、今回の初対面で高市氏はトランプ氏のお眼鏡にかなったのだろうか。
少なくとも第1次テストはパスしたように見える。
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。