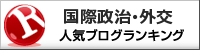https://x.com/i/status/1989242174974689717




福島氏の記事では、中共外交部の人材の劣化が薛剣のような外交官を産みだしたと。薛剣のようなジャパンスクールだけが問題ではなく、盧沙野はフランスで物議を醸し、趙立堅は英語でTwitter発信をしていて問題になっていたから、やはり戦狼外交が常軌を逸した外交の元、もっと言えば習近平の姿勢に問題があると言える。鄧小平の韜光養晦路線の方が西側諸国を誑かし続けることができ、賢いやり方と思うが、習近平は父の仇の鄧小平路線を引き継ぐことは出来なかったのでしょう。西側にとっては中共の悪を見れて、幸いだった。
日本は中共外交部だけを見るのでなく、中共全体を見るようにしないと。共産主義は悪の塊。歴史が証明している。そうでなければソ連は崩壊しなかった。中共打倒が世界平和の元。中共経済を良くしないよう、西側がデカップリングするのが肝要。
記事

「首を斬り落とす」暴言を吐いた中国の薛剣・駐大阪総領事=2024年2月27日撮影(写真:共同通信社)
(福島 香織:ジャーナリスト)
高市早苗首相が11月7日の衆院予算委員会の答弁で、中国による台湾の海上封鎖が発生した場合の事態認定を巡り「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースだ」と発言した。
これは台湾有事に際し、日本が集団的自衛権を行使できるという立場を明確に発信したもので、日本の首相が台湾有事に関してここまで踏み込んだ発言をするのはおそらく初めてだろう。この発言に対し日本の野党やリベラル派メディアは、当然大反発し、発言を撤回しないのか、と追及した。
中国の脅威から日本の安全をどのように担保するかというテーマについて、日本で多様な意見が議論されることは大いに結構だ。だが、ここで興味深いのは、この高市発言に絡んできた中国の駐大阪総領事、薛剣の発言だ。
駐大阪総領事、薛剣の暴言
チャイナウォッチャーの間では、すでに下品かつ攻撃的な反日暴言で有名な戦狼外交官の薛剣は8日、SNSのXで、この高市発言を報じる朝日新聞記事の引用ポストで「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟は出来ているのか。」と暗殺をほのめかすような投稿を行った。
さらに薛剣は9日、再びXに「『台湾有事は日本の有事』は日本の一部の頭の悪い政治屋が選ぼうとする死の道だ。」と投稿。「敗戦国として果たすべき承服義務を反故にし、国連憲章の旧敵国条項を完全忘却した余りにも無謀過ぎる試みだ。」などと投稿。
このXでの発言が、日本人だけでなく世界の良識的な世論から大反発をくらった。
日本政府報道官は10日、この薛剣発言を「極めて不適切」と非難し、直ちに投稿を削除するよう要求したと表明。また、薛剣が度重なる不適切な発言を行っていることを十分認識しているとも述べた。
薛剣は投稿を削除するも、謝罪する様子はない。また、中国外交部の林剣報道局長は10日、「(薛剣の)個人発言は、台湾を中国領土から分離し、武力による台湾海峡への介入を扇動する誤った危険な言論に向けられたものであり、一部の日本の政治家やメディアがこれ(投稿内容)を意図的にあおり、世論を混乱させ焦点をそらそうとしているのは無責任である」と薛剣を擁護した。
それどころか「日本の指導者がこのほど国会で公然と台湾問題に関する誤った発言を行い、台湾への武力介入の可能性を示唆し、中国の内政に粗暴に干渉した」と指摘し、「すでに日本側に厳正な交涉と強い抗議を行った」と述べ、責任のすべてを高市発言にあると言わんばかりの態度をとった。
このため、高市発言の是非論争をすっ飛ばして、この中国外交官の非常識な態度が今なお炎上を続け、今や自民党だけではなく一部の野党も薛剣を「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」に指定して国外退去を求めるべきだと主張している。
日本人だけでなく良識的な国際世論も薛剣を批判しており、グラス駐日米大使は「高市首相と日本国民を脅迫している」と批判、台湾外交部の蕭光偉報道官は「このような脅しは文明法治国家の言論の限界を超えるだけでなく、一国の首脳に対してあまりに軽々しく不当だ」「彼ら(中国)の好き勝手な覇権的心理をまざまざと示すものだ」と非難した。
当たり前だろう。日本では安倍晋三元首相が実際に暗殺され、米国ではトランプ大統領が暗殺未遂を経験しているこの時代に、冗談でも外交官の立場にある人間が言っていい言葉ではない。
なぜ、このような暴言を吐く人物が総領事なのか
そして中国において、要人、政治家の暗殺というのは実際、冗談ではなく頻発している。習近平は何度も暗殺未遂に遭っているとされ、暗殺をおそれていると言われている。李克強元首相の水泳中の急死も、暗殺だという噂も根強い。
しかも、安倍暗殺事件の本当の犯人は山上徹也被告ではなく、中国が陰で糸を引いている、などという陰謀論が一部で出るくらい、中国では要人暗殺がしばしば起きていると信じられている。
57歳の、本来なら分別盛りの外交官が、こういう発言をした場合、世間は様々な憶測をするだろう。一つは、中国なら本当に高市暗殺をやりかねないのではないか、外交部内、あるいは党中央内にそういう空気があるのではないか、という陰謀論。そしてもう一つは、中国はこんな暴言を吐くような低レベルの外交官を日本に派遣するくらい、日本を軽んじている。あるいは、本当に外交部は人材不足で、劣化しているのかもしれない、という想像だ。
私はこの中国外交部劣化説が、今回の事件の本質だと思っている。
習近平政権になって、鄧小平時代から継続してきた外国との摩擦を避ける「韜光養晦(とうこうようかい)」路線から、攻撃的ないわゆる「戦狼外交」に転換したことはご存じだろう。
韜光養晦とは、野心や才能を隠してより大きな実力を養うという意味で、いわば能ある鷹は爪を隠す式で、米国などの先進国から資金や技術の支援をうけながら経済発展を遂げ、大国化してきた中国の改革開放時代の外交戦略だ。このころの外交官は流暢な英語と洗練された物腰、知的なウィットで欧米外交官、政治家たちを魅了し、各国政府を中国への協調路線に導くのが任務だった。
だが習近平が中国トップに就任したのち、すでに中国は十分に大国となり、その実力を隠す必要はなく、むしろ誇示し、米国はじめ先進国から舐められないようにするべきだという考えに転換した。
そうした外交転換がより顕著になったのは2017年ごろだ。その年に公開された中国の愛国解放軍宣揚映画『戦狼 ウルフ・オブ・ウォー』にちなんで、この呼び名が定着した。
このころ、いわゆる戦狼外交官たちが海外のメディアやSNS上で西側の外交官らしからぬ攻撃的でときに下品な言葉で外国の政府関係者や外交官とバトルを演じてみたり、あからさまな上から目線で、あたかも相手の無知を叱りとばすような言動で、中国の一方的な主張を展開したりしていた。
そして、そうした戦狼外交官ほど出世するようなムードになっていった。たとえば、趙立堅はパキスタン大使館勤務時代にスーザン・ライス元大統領補佐官とウイグル問題に関してSNS上で罵倒合戦をして注目をあびた後に、外交部報道官、報道局長という出世コースにいきなり乗った(だがなぜか、2023年に左遷させられた)。
戦狼姿勢に転換して一番出世したのはもちろん中国外交のトップに君臨している王毅・外相(兼中央外事工作委員会弁公室主任)だ。ほかにも華春瑩、劉暁明、盧沙野といった外交官が戦狼外交で知られ、順調に出世街道を歩んでいる。
そして、こうした戦狼スタイルが外交部の主流になってくると、従来の洗練された協調型外交官が排除されてきた。
有能な外交幹部が次々と失脚
最近、国内外の有識者がショックを受けたのは、なんといっても劉建超・元党中央対外連絡部長(中聯部長)の失脚だろう。彼の突然の失踪、失脚については、このコラム欄でも解説したことがある*1。
*1:中国の外交担当高官がまた「失踪」、今度は劉建超が拘束?英米派にして知日派、習近平に排除されたか
彼はかつての欧米人が好きなタイプの外交官で、英語が流暢で洗練された物腰と知的なウィットにとんでいた。謙遜し、親しみやすそうに見えて、最終的には目的を達成する韜光養晦型の手ごわい交渉ができるタイプの人物だった。その実力は、習近平も認めており、「キツネ狩り」作戦担当外交官(規律検査委員会国際協力局長、海外逃亡の汚職官僚を指名手配し、逃亡国政府に対し中国に引き渡すように交渉する)に抜擢したほとだ。
彼は昨年初めごろまでは、確実に次の外交部長に就任すると欧米外交官の間でみなされていた。おそらく本人もそのつもりであったろう。外交部長ポストは、習近平の抜擢により駐米大使から外交部長にロケット式に出世した秦剛が元フェニックスTV女性キャスターとの不倫疑惑で失脚した後、外事工作員会弁公室主任の王毅が兼務していた。
もし、英米通の劉建超が外交部長になれば、戦狼外交でジャパンスクール出身の王毅と違い、欧英米と阿吽(あうん)の呼吸で協調、交渉できるようになると欧英米外交官はその日を待ち望んでいたのだった。
だが、彼は今年7月末、国外出張から帰国したところを拘束された。劉建超に関する公式報道は皆無だが、9月30日に劉海星が新たな中聯部長として着任しており、劉建超が粛清されていることは確実だ。
劉海星は北京外語大フランス語学部卒業で、フランス駐在、欧州局長、党中央国家安全委員会弁公室をへて、中聯部長となった。中聯部長というのは政党外交を担うのだが、共産党≧国家の中国において、ときに外交部長より重視される。それがなんとも小物感が漂う、外交部王道ではないタイプが就任したことで、外交部全体の能力レベルが低下している印象を受けた。
秦剛、劉建超と習近平が抜擢した英米通の有能な若手外交官が続けて失脚したのは、実は習近平の単なる気まぐれだけでなく、王毅によるライバル排除の可能性が指摘されている。
外交トップ王毅にコンプレックス?
中国の外交政策の方向性を決定するのは、党中央外事工作委員会。この主任はもちろん習近平、副主任は李強首相、そして国家副主席の韓正ほか、国家安全部、中央宣伝部のトップらが委員に名を連ねる。
だが委員会メンバーたちは外交素人であり、実際の外交政策をまとめ、習近平らに提示するのは外事工作委員会弁公室主任の王毅である。王毅は外事委弁公室主任と外交部長を兼任している。
外交部長は外交実務を統括するポジション。つまり、王毅は外交政策方針と政策実務すべて統括しており、中国外交を実質掌握しているといっていい(もちろん、最終的には習近平が決める)。
だが、これは本来分担すべき仕事を一人が全部抱えこむという点で、かなりのオーバーワークである。しかも従来、外交トップは米国との交渉経験をもつ英米派が務めていたこともあって、ジャパンスクールの王毅には荷が重いといわれていた。
日本やアジア諸国を主に相手にするジャパンスクールの外交官は、一般に英米の手ごわい国との交渉で鍛えられてきた外交官より能力が劣るとみなされがちだ。日本は中国の気持ちを勝手に忖度してくれるし、対アジア諸国交渉の相手国は中国にとってはもともと属国で格下相手だ。
一方、対英米交渉では、単純な戦狼外交では勝てない硬軟織り交ぜたテクニックが求められる。楊潔篪も秦剛も劉建超も、英米派は、表向きは洗練された雰囲気で、時に戦狼型の姿勢を打ち出しても、緻密で労力を惜しまない交渉能力を持つ外交官との評価が高い。
王毅には、そうした英米派に対するジャパンスクールならではコンプレックスがあり、英米派の若手外交官の急激な出世に脅威を感じて、粗探しをして、習近平にチクり失脚させてきたのではないか、というわけだ。そのせいで、有能な外交官ほど出世しにくくなり、外交部全体のレベルが落ちてきたのではないか。
強気の高市首相への期待
王毅のジャパンスクールコンプレックスや外交部内権力闘争が原因、というのは与太話として聞き流しておくとしても、薛剣の暴言、ふるまいをみると、やはりジャパンスクール外交官のレベルは低い、というのは本当かもしれない。
それは、日本に対してはいくら暴言を吐いても、日本は「遺憾」や「抗議」を口先でいうだけで、御しやすい外交相手とみなされている部分はあろう。
薛剣の暴言は今に始まったことではないのに、今回、特に国際世論も一緒になって反発しているのは、日本の今の政権が高市政権だからであろう。つまり、暴言をいくら吐いても曖昧(あいまい)な笑みを浮かべて、ことなかれ主義でやり過ごそうとする従来の日本政府とは一味ちがうはず、という期待が国内外にあるのだ。
ここは、この期待に高市政権は応えるべきではないか。薛剣駐大阪総領事をペルソナ・ノン・グラータとし、日本から退去いただこう。それが、中国外交の劣化を食い止めてあげる、という意味でも、両国にとってプラスとなろう。
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。