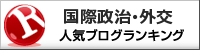7/2希望之声<欧美俄异动!美副总统被紧急召回白宫=ヨーロッパ、アメリカ、ロシアに異常な動き! 米副大統領は緊急にWHに呼び戻された>情報筋によると、米欧露の3大政治実体は7/2(火)に特別な動きをした。ペンス副大統領はエアフォース2でニューハンプシャーに行く予定であったが緊急に取消した。WHは、当局がペンスを緊急に呼び戻したと説明したが、その理由は拒否した。 同時に、EUとロシアも同じように異常な行動に出た。
欧州連合が急に安全理事会を招集し、ロシアのプーチン大統領も当初の計画を取り消し、緊急に国防相と会談し、安全会議を開いた。
日本は情報が取れているか?パチンコマネーに汚染されている大臣は早く更迭してほしい。

NYT記者のLuke Rudkowski
https://www.soundofhope.org/gb/2019/07/02/n3002899.html
7/3阿波羅新聞網<白宫贸易顾问纳瓦罗:美中贸易谈判回到正轨=WH貿易顧問のナバロ:米中貿易交渉は正しい方向に戻る>WH貿易顧問のピーターナバロは本日、「トランプ大統領と習近平主席が先週末に会談してから、米中貿易協議は正しい方向に進んでいる」と述べた。
しかし、WH国家貿易委員会(White House National Trade Council)会長でもあるナバロは、「中国の通信機器メーカーである華為に対するワシントンの態度は軟化したものの、華為は米国での5Gワイヤレスネットワークの展開には依然として参加できない」と述べた。

https://www.aboluowang.com/2019/0703/1310112.html
7/3阿波羅新聞網<左批宗教迫害右打社会主义 彭斯:美国因为自由而强大=宗教迫害を批判する一方、社会主義とも闘う ペンス:アメリカは自由かつ強大である>ペンス副大統領は、30日の夕方に“信仰と自由の連合(Faith and Freedom Coalition)”でスピーチをした。 中国等の宗教迫害に対し、ペンスは「米国政府は世界中の人々の良心と宗教の自由のために戦い続ける」と保証した。
WHのウェブサイトで発表された原稿によると、ペンスは「ニカラグア、ロシア、イラン、そして中国での宗教迫害に対し、米国は厳しい姿勢を示している」と述べた。 また「今の政府は、世界中の人々の良心と信教の自由のために引き続き発言し、闘い続けることを約束する。我々はこの理想を堅持する」と約束した。
ペンスは「社会主義ではなく、自由こそが米国を世界の歴史の中で最も強い国にしたこと。それは社会主義ではなく、自由こそが奴隷制を終わらせ、二つの世界大戦に勝利できたことだ」と指摘した。 ペンスは「米国が社会主義国になることは決してないだろう」と強調した。

https://www.aboluowang.com/2019/0703/1310087.html
7/3阿波羅新聞網<外媒:川普约见金正恩 中共又震惊又恼火=外国メディア:トランプが金正恩と会い中共はショックといらいら>雑誌“国益(The National Interest)”は7月1日の分析記事で「トランプ大統領の突然の訪問は、金正恩に口を開いて笑わせ続けたが、一部の人々は笑うことができなかった。中共が非常にショックを受けていることはほぼ確実である。トランプが金正恩と会うことについて中共は全く気付いていなかったことは明らかである」と述べた。
どうして中共が完全に暗闇の中にいるのか? まず、トランプのツイートが中共に信号として送られ、北京の助けを借りずに金正恩と直接交渉できることを見せた。
“国益”の記事によると、「トランプが中共の撒き餌の影響を受けていないことは称賛に値する。 トランプは外部に、金正恩との関係がどんなに良いか、形がどのように変わろうとも、常に金正恩に優しい言葉をかけてきた」と語っている。
トランプが北朝鮮の土を踏んだのは、目標が核兵器の武装解除ではなく、北朝鮮への中共の影響を削ぐことであれば、これは非常に正しい一歩である。
米国では、金正恩は悪辣と思う人が多いかもしれないので、 トランプが金正恩を何故友達呼ばわりするのかと思う人もいる。トランプが金正恩を称えるのは、プーチンを称えるのと同じで、米国の戦略上、中共を孤立化させるためには、非常に有意義であることを知っておくべき。
https://www.aboluowang.com/2019/0703/1310092.html
7/2@niftyニュース<米国防総省報告、中国の対日浸透工作に言及 「日中友好を掲げた政治戦争」>
中共の対日侵略に手を貸しているのは日本のデイープステイトである財務省(旧大蔵省)とメデイアなのかと思っています。ここを打破しない限り、日本は前に進めないのでは。安倍首相は今参院選で憲法改正できる政党かそうでない政党かを争点にするようですが、消費税凍結もできないようでは財務省に対し脆弱としか思えません。トランプの方が強い。でも、トランプもデイープステイトをなかなか潰せないことを考えると、安倍首相も厳しい点数をつけるのは酷なのかも。替わりがいないのも問題。首相公選にすれば、今のメデイアに洗脳されている国民では真面な政治家を選ぶ保証もありません。衆愚政治の結果が待っているような気がします。
7/2の6チャンネル『ひるおび』に津上俊哉が出ていて、「北朝鮮とトランプが板門店で会えたのは習近平のお蔭と中国報道官が発言した。習への忖度かもしれないが」と言っていました。一党独裁の共産国家で忖度だけで発言できないのは津上も中国に長くいたから分かっている筈。必ず上部と擦り合わせて発言している。流石中国に思い入れが強い元通産官僚のことだけはある。上述の中国語の記事とは正反対でしょう。小生は中国語の記事の方が正しい見方と思っています。もう北京に北朝鮮のことは頼まないで、自分達で解決するという強い米国の意思を感じます。中共からしか情報が取れないと、中共のプロパガンダを鸚鵡返しに繰り返すだけ。みっともない。加藤氏の記事もそう。ニュースソースが中共だから、中共の思惑に沿って書いているだけ。「中国民主化研究とは中国共産党研究である」とは名ばかりで、民主化についての思いはさっぱり感じません。そもそも、自国内市場を閉ざしている中国に「保護主義云々」とか、公然と技術窃取を認めた国に「相互に尊重し」とかは言ってほしくありません。中共には“reciprocity”と言う言葉はないでしょう。「お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの」が価値観なので。こう言うことも含めて書かなければ日本の読者には伝わらないでしょう。
記事

Photo:The New York Times/Redux/AFLO
G20習近平談話から読み取れる3つの思惑
G20大阪サミットが閉幕した。
「中国民主化研究とは中国共産党研究である」という立場を取る本連載にとって、国内的には抑圧的、対外的には拡張的な態勢を見せてきた習近平国家主席(以下、敬称略)率いる中国共産党が、G20という国際舞台をどう活用し、自らの権益を主張していくのかを検証する作業は重要である。中国は自らが他の多くの新興国と共に所属し、参加してきたG20という舞台を戦略的に重視してきた。西側先進国で構成されるG7よりも、多くの非西側新興国を含めたG20のほうが国際社会全体の利益や願望を代表していると提唱してきた経緯がある。
習近平が同サミットにて発表した談話の次の部分には、昨今における中国共産党指導部の基本的認識と立場が凝縮されているように思える。
「G20は主要な先進経済体と新興市場経済体を集めており、その経済総量は世界の90%近くを占める。我々は異なる発展の段階にあり、いくらかの問題において利益の差異や観点の摩擦が存在するのは正常なことである。大切なことは、パートナーシップの精神を掲げ、相互に尊重し、信任する態度に基づいて平等に協商し、同じところを求め、異なる点は残し、摩擦を管理し、合意を拡大することである。大国間でそれができれば、自らの利益に符号するだけでなく、世界の平和と発展にも有利に働くであろう」
この段落から読み取れる習近平の思惑は3つある。
1つに、物議を醸してきた米中貿易戦争を強く意識している点である。発展の段階が異なること、故に違いや摩擦が生じることは正常であることを強調することで、関連諸国の貿易戦争への懸念をなだめようとしている。
2つに、貿易戦争において米国に対して一歩も引かないという立場を取ってきた中国共産党であるが、そうはいっても米国との国力や影響力のギャップを考慮したとき、やはり基本的には米国との関係を安定的に管理したいという点である。ここには、中国国内経済への悪影響も懸念されている。
3つに、米国との関係を安定的に管理したいとはいうものの、習近平の国内的メンツ、中国共産党としての対外的野心、大衆の間で高まるナショナリズムなどを考慮したとき、米国という超大国と対等な地位で勝負するのだという明確な意思が表れている点である。
上段落における「相互に尊重」「平等に協商」という表現は、まさに中国が目下、米国との貿易戦争を戦うなかで形成してきた基本的立場である。中国は、相手国に自らの核心的利益を尊重させ、平等な立場で交渉を行うという「大国」としての立場や様相を、ますます全面的に押し出してきているということである。その意味で、今回のG20においては、中国の対米意識が色濃くにじみ出ていた。
習近平がG20を通して得た2つの外交的成果と1つの課題
一方で、冷戦終了後、世界で殆ど残っていない社会主義国家であり、その国力からしても米国と相当程度の開きがある現状下において、中国とて一国だけで米国に挑んでいけるとは考えていない。ここで出てくるのが、習近平政権が発足して以来展開されてきた「お友だち外交」である。アジアインフラ投資銀行(AIIB)、一帯一路、新興国や途上国と手を組んで主催する各種国際会議(筆者注:上海協力機構、アジア相互協力信頼醸成措置会議、中国・アフリカ協力フォーラム等)を通じて「お友達」を作り、引き連れながら米国や西側が主導してきた国際秩序・システムを自らに有利な方向へ持っていこうとする外交戦術を指す。
今回のG20サミットを通じて、習近平は「20強のイベントに参加した」(王毅外相兼国務委員)が、お友達外交を象徴する3つの多国間外交として、(1)中ロ印三国首脳会談、(2)BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)首脳会談、(3)中国・アフリカ首脳会談に出席している。(1)、(2)における習近平の以下の主張は、まさに昨今の中国共産党指導部の思惑と立場を露呈しているといえる。
「昨今、保護主義、一国至上主義の台頭はグローバル情勢の安定に対して深刻な影響を与えている。と同時に、新興市場国家と広範な発展途上国が生存のために依存してきた国際秩序に、軽視できないマイナスの影響を及ぼしている。中国、ロシア、インドは今こそ然るべき国際的役割を担うべきであり、3ヵ国及び国際社会の根本的、長期的利益を守るべきである」
「BRICs諸国は自らのことにしっかり取り組み、発展の強靭性と外部からのリスクに抵抗するための能力を増強すべきである。我々はBRICs経済、政治的安全、人文交流という3つの分野における協力をバランスよく推進すべきである」
これらの主張からは、(1)中ロ印と西側主導の秩序を調整していく(筆者注:中国はこの狙いと行動を「国際関係の民主化」「世界多極化」と称し、G20サミットを通じて随時呼びかけていた)ための戦略的枠組みだと捉えていること、(2)BRICsがそのための補強的・延長的枠組みになり得ること、(3)それらの枠組みをあわよくば“ブロック化”し、その過程で「政治的安全」、すなわち西側、特に米国の自国への政治的浸透(筆者注:いわゆる「和平演変」がその典型)を防止しようとしていることが伺えるのである。
上記以外に、習近平にとって外交的成果といえるものが2つ、外交的課題といえるものが1つ残ったと筆者は考えている。
最初の成果が対米関係である。本連載でも随時検証してきたように紆余曲折を経たが(参照記事:劉鶴・国務院副総理が対米交渉「決裂」後に語った本音)、少なくともトランプ大統領との会談にこぎつけ、米中首脳が比較的良好な関係を保持している現状をG20という国際舞台でアピールできた意味は小さくない。それだけではなく(今後どう状況が展開するかは未知数ではあるものの)、トランプ側から「米国はこれ以上、中国製品に対して追加課税をしない」という「確約」を得たこと、米国企業による華為技術(ファーウェイ)への輸出禁止を一部解除することの2点を、今回の米中首脳会談で達成できたとして、習近平政権は自国世論に対して大々的にプロパガンダしている。
今後、再び交渉が決裂したり、米国側が「確約」を変更してきたりするリスクは十分に考慮していると思われるが、それでも習近平政権としてこのタイミングで対米貿易交渉の進展を内外に示したかったのであろう。
「してやったり」香港問題は目立たず
次の成果がG20の合意内容に関するものである。筆者自身、毎回G7、G20が迫るたびに中国の政府官僚や体制内学者と議論することでもあるが、近年、彼らはこれらの国際会議において(1)世界経済低迷の原因を中国経済、特に過剰生産能力、国有企業問題、構造改革の遅延、経済成長の低迷などに見出され、名指しで批判されること、(2)南シナ海や東シナ海における自らの政策や動向を「拡張的行動」「現状変更」「軍事化」といった文言で、名指しで批判されること、(3)人権問題でその当事者として槍玉に挙げられること、そしてこれらが合意文書や共同声明に盛り込まれることを極度に警戒してきた。
今回G20サミット終了後発表された「大阪宣言」(https://www.g20.org/pdf/documents/jp/FINAL_G20_Osaka_Leaders_Declaration.pdf)を読む限り、そういう事態にはならなかったようだ。過剰生産能力は議題には上がったものの、中国が名指しで批判されることはなく、南シナ海や人権問題に関しては宣言そのものにすら含まれていない。特に後者に関しては、昨今、香港情勢がこれだけ荒れている状況下で(参照記事:香港デモ現場ルポ、習近平が「香港200万人抗議」を恐れる理由)、G20の主要議題として扱われなかったことは、習近平にとっては「してやったり」で、外交当局者は自らの成果だと認識しているに違いない(筆者注:日中首脳会談では、安倍首相から習主席に対して、引き続き「一国二制度」の下、自由で開かれた香港が繁栄していくこと、いかなる国であっても、自由、人権の尊重や法の支配といった国際社会の普遍的価値が保障されることの重要性が指摘されており、サミット開催期間中に行われた2ヵ国間協議では議題として上がったケースもあった)。
トランプ大統領板門店訪問で生じた習近平の懸念
最後に外交的課題であるが、それは北朝鮮問題である。習近平はG20サミットでトランプと会談をする直前に平壌へ飛び、初の公式訪問を実行した上で金正恩委員長と会談をしている。北朝鮮情勢安定化への関与、外交的孤立への懸念と対策、対トランプへの外交カードの準備といった思惑があったのだろう。
米中首脳会談において、習近平はトランプに金正恩との会談を続けることを支持した。それが朝鮮半島の安定化と非核化に資するという立場を踏襲している。とはいうものの、トランプのツイートに端を発し、そこから電撃的に板門店での初の米朝首脳会談が実現し、自らがいまだ通商問題で「対抗」しているトランプが、米国の現職大統領として初めて北朝鮮の地を踏んだ経緯を、習近平は複雑な心境で眺めていたに違いない。北朝鮮情勢が自ら掌握できない状況下で推移し、同問題において主導権を失うなかで、南北融和や米朝接触が進み、北朝鮮問題解決の実質的キーマンが北朝鮮・韓国・米国の3ヵ国だという国際世論と地政学的局面が形成されてしまう事態を、習近平は懸念している。
この懸念は、電撃的なトランプの北朝鮮訪問をきっかけに、今後より一層、前のめりで日朝首脳会談の実現に向けて動くにちがいない。日本の安倍政権にとっても、他人事ではなかろう。
(国際コラムニスト 加藤嘉一)
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。