6/4阿波羅新聞網<外媒:中国陆军医院前实习生亲历活摘器官=外国メディア:中国陸軍病院の元インターンは生きた臓器の摘出を経験した>“ニューヨーク・ポスト”は、6/1《元病院勤務者:中国の反体制派は臓器摘出による処刑》の記事を掲載し、中国の瀋陽陸軍総合病院のインターンが臓器摘出を手伝わされた経験を明らかにした。
記事は、「中国の臓器移植のシステムは単なる殺人ではなく、エスニッククレンジングであるかもしれない。当時の江沢民党書記長が法輪功を迫害した後に、中国の臓器移植ビジネスにおける多くの新鮮な臓器の供給源は法輪功学習者である。
少しずつ、中共の狂気がメデイア等に明るみに出てきています。漢民族の異常性と、共産主義の異常性が相俟って発現するのですから、人格破壊や精神破壊のレベルは相当なものになります。日本人は彼らに工作を受けて来て、どうして簡単に彼らの言うことを信じるのでしょう。嘘の南京事件を虐殺と言い、事実の天安門事件は無いことにする、所詮プロパガンダと言うことに気付かなければ。野党政治家と日本のメデイアは中共の手先です。自分の目と頭をフル回転させないと。

https://www.aboluowang.com/2019/0604/1297618.html
6/4阿波羅新聞網<三十年声犹在耳: 六四亲历者回忆枪响时刻=30年前の音がまだ耳に残っている 6月4日の目撃者は銃の発射の瞬間を思い出す>
音声は中国語、7分23秒の内、事件発生の部分は5分くらいから https://www.aboluowang.com/2019/0604/1297625.html
6/3看中国<独家:30年前一位日本青年拍下的六四前照片(组图)=独占:30年前に日本人の若者が撮った6月4日の写真>下のURLをクリックして写真をご覧ください。
https://www.secretchina.com/news/gb/2019/06/03/895707.html
6/3希望之声<新书《揭穿》:“激进化的”媒体想要摧毁川普 却毁了自己=新刊“仮面を剥ぐ”:「急進的な」メディアはトランプをダメにしたいと思ったが、メデイア自体を台無しにした>6/4に正式に出版される新刊、“Unmasked – Big Media War Against Trump”の共著者、Brent Bozell (Media Research Center)によれば、「この本は主流メディアが如何にトランプ大統領をダメにしようとしたか、だが結果は却ってメデイア自身をダメにしてしまった」と述べた。 この本に記録されているメジャーなメディアが犯した間違いと彼らが捏造したフェイクニュースを読んでほしい。本当に自壊の前兆が読み取れる。
米国メデイアも左翼シンパでしょう。国境を無くすのが良いと考えるグローバリストです。中共のチベット、ウイグルを見れば、世界統一政府ができれば異端は悲惨な目にあわされるのが理解できるはずです。トランプは「米国は永遠に社会主義国にはならない」と言ったのは正しい。人権を尊重しない、自由もなければ民主的でもない共産主義を後押しするのは人類に対する犯罪です。メデイアは自覚的か無自覚なのかは分かりませんが、直観が働いていないという事です。
 https://www.soundofhope.org/gb/2019/06/03/n2931490.html
https://www.soundofhope.org/gb/2019/06/03/n2931490.html
WSJ記事では父ブッシュの時代から(というか戦前から)米国人は中国人の本性を理解して来なかったという事です。「豊かになれば民主化する」というのは間違った考えです。それにやっと気づいたという事でしょう。
広岡氏の記事では、習近平が第二の長征を宣言したとあります。以前にも書きましたが、毛沢東の時代の貧しさと、今の豊かな時代とでは民衆の忍耐力に相当の開きがあります。大衆が蜂起しようとしても、治安警察や解放軍を掌中に収めているのですぐに鎮圧されるでしょうけど。やはり、関税だけでなく、金融制裁、軍事制裁(石油供給遮断等)もやって、経済崩壊させるべきです。債務が膨れ上がっている中国に経済ブロック化できるだけの能力があるとは思いません。
細川氏の記事は実務をこなしてきた経験から、日本企業に対する警告が含まれています。日本企業は真剣に対応し、中国へ味方することは止めないと。レアアースの問題は長期的には南鳥島の開発をすれば良いと思うのですが。
WSJ記事

筆者のジェラルド・ベーカーはWSJエディター・アット・ラージ *** 1989年春に天安門広場で学生が行った民主化デモには忘れがたい場面がいくつもある。もちろん、流血の事態に至った悲惨な結末もその一つだ。人民解放軍の戦車の前に武器も持たず、落ち着いた様子で立ちはだかった勇敢な男性の悲痛な姿もそうだ。
しかし、米国人にとっておそらく最も強烈な映像は「民主の女神」像だった。民主の女神は学生が制作した間に合わせの像で、毛沢東の肖像画と霊廟(れいびょう)の真向かいに設置された。学生運動の指導者らは米国の「自由の女神」のレプリカではないと主張したが、そのよく似た姿を米国人が見逃すことはなかった。トーチを高く掲げる女性像は、自由な空気を求める世界中の人々の権利と願いを後押しする役割が米国にあることを想起させた。
自由という普遍的な権利のために戦ってきたという米国なら、容赦ない弾圧にさらされている自分たちと連帯して立ち上がってくれるだろう――。当時の中国の学生たちがそう期待していたとすれば、その期待は見事に裏切られた。 ジョージ・H・W・ブッシュ大統領は当初、中国政府による弾圧を非難し、中国への武器輸出を停止するなど制裁を発表した。しかし、米政権は早い段階で、天安門事件を対中政策の転換点にしないことを決定していた。米国は公式の反応として、基本的に何も起きなかったかのように振る舞うことが明白になった。天安門事件のほんの数日後、ブッシュ大統領は「今こそ米国にとって、極めて重要なこの関係の重要かつ永続的な側面を見据えるべきだ」と発言したのだ。いつも通りの関係を続けるという政府の決定はワシントンで猛反発を招いた。議会では民主党議員と一部の共和党議員が対中制裁を要求し、中国に対して対決姿勢を強めるよう求めた。
世界(中国を除く)は今週、天安門事件の30周年記念日を迎えるが、当時の米国の態度は今でも間違っていないと言えるだろうか。中国の虐殺者たちへの寛大な対応は2つの主張に基づいていたが、結果としてそのどちらにも欠陥があった。 一つ目の主張は現実の政治に基づく主張だ。当時、中国は米国にとって、冷戦の最大の敵だったソ連の力を抑えるために極めて重要な存在だった。しかも1989年春の段階では、ソ連が崩壊し始めたことは明らかになりつつあったが、数カ月後のベルリンの壁崩壊まで予想する声はワシントンにはなかった。
ところがその後、三つどもえのチェスの中で中国が果たした役割は米国にとって役立つものではなくなった。2年後、ソ連が完全に消滅し、それから数年後には米国の覇権を長きにわたって脅かす大きな動きが中国で生じ始めた。
今になってみれば、当時の米国の自制を正当化する2つ目の主張もうわべの議論のように思える。ブッシュ政権内では、大統領を批判する勢力がまさに訴えていた人権上の進展を達成するには関与の継続が不可欠だと考えられていた。大統領はそれをこう表現した。「人間には商業的な動機があるのだから、中国だろうとその他の全体主義国家だろうと、民主主義への移行は止めようがなくなる」。外交上の礼節を維持することで中国共産党内の「改革派」を後押しできるが、政治的および経済的に中国を孤立させれば「強硬派」を盛り立てるだけだ――。それが米国の考えだった。
過去30年の出来事を振り返ると、1989年の中国政府の行動を大目に見ようというこの米国の姿勢が大きな成果を挙げたとは言い難い。そしておそらく、経済や政治、外交の各分野で中国が繰り返すますます強硬な振る舞いに対しても同様のことが言えるだろう。 米国がより断固とした対応を取っていれば事態が大きく変わっていたかどうかは誰にも分からない。当時、中国の潜在的経済力は既に解き放たれていた。米国が中国を孤立させようとしたとしても、この30年で中国の経済成長は着実に実現されただろう。それに中国と対立して封じ込めるより、受け入れようとしたことは正しかったという説得力のある主張もある。
ただ、より開かれた民主的で自由な社会への移行を後押しするという狙いからすれば、中国政府の行為を許すという30年前の米国の決断は目も当てられない失敗だ。 (The Wall Street Journal/Gerard Baker)
広岡記事
1934年、国民党軍と戦っていた中国共産党軍10万人は拠点としていた江西省瑞金の地を放棄し、壮絶な行軍を始めた。約2年の歳月をかけ1万2500kmを移動して陝西省延安にたどり着いた時、残っていたのはわずか2万人とも3万人とも言われている。この長期にわたる行軍の中で、毛沢東は共産党における指導権を確立した。
中国近現代史におけるハイライトの1つ、「長征」と呼ばれる出来事である。無残な敗退戦だったとの見方もあるが、中国では長征を歴史的偉業と位置づけている。形勢不利の中でも持久戦に切り替えて耐え忍んだことが反転攻勢のきっかけとなったことは間違いなく、この出来事は中国共産党のDNAに深く刻まれた。

(写真:akg-images/アフロ)
5月20日、長征の出発地を訪れた習近平国家主席は「今こそ新たな長征に出なければならない」と国民に呼びかけた。米中貿易交渉は行き詰まり、対立が激化している。米国との争いの短期決着は諦め、持久戦に持ち込むとの宣言とも取れる。
天安門事件後は「豊かさ」で国民の不満を抑え込む
このままの展開が続けば、待ち受けるのは経済や技術のブロック化だ。問題はそれが中長期的に必ずしも米国にとって有利に働くとは限らない点にある。次世代通信技術では中国は世界最先端の地位を確立した。国家規模でのビッグデータやAI(人工知能)活用においても、プライバシーなどの壁をクリアしなければならない民主主義国家に比べて中国が有利だ。弱点である半導体などの技術分野も急ピッチで追い上げている。中国がブロック経済圏を確立してしまえば、技術的にも経済的にも米国の影響力はむしろ失われる。
一方の中国にも弱みはある。今日6月4日は1989年に起きた天安門事件からちょうど30年に当たる。民主化を訴える学生への武力行使は、中国共産党にとっては消し去りたい記憶だ。節目を迎える中で、海外メディアによる天安門事件についての記事が目立つ。肝心の中国国内における民主化運動は下火だが、それも経済的な豊かさがあってこそ。天安門事件以降、中国共産党は経済成長を以前にも増して追求し、国民に豊かさを享受させることで、一党独裁体制の安定を図った。
民主化への動きが下火になっている現状は、そのもくろみが現段階ではうまくいっているということだろう。ただし今後、貿易戦争による経済の混乱が拡大し、長期化すれば、現在の政治体制への不満が噴出しかねない。それは中国政府にとって最も避けたい展開だろう。
激しさを増す米中の貿易戦争。「新長征」を呼びかけた習国家主席はこれを共産党の存続をかけた戦いと位置づけたのかもしれない。だとすれば、両国の争いが容易に収まることは考えづらい。日本経済への影響もさらに大きなものになりそうだ。
細川記事
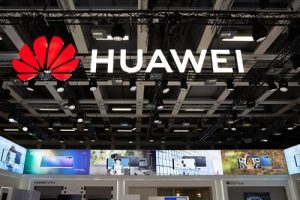
「ファーウェイ問題」はこの先どう展開するのか(写真:ユニフォトプレス)
中国の華為技術(ファーウェイ)への事実上の禁輸という米国が出した切り札によって、世界で激震が続いている。ファーウェイの任正非CEO(最高経営責任者)は強気の姿勢を崩さないが、背景にはファーウェイが既にこの米国の動きを早々に察知して早くから手を打ってきたこともある。
2月5日の本稿でもこの事態を予想していたが、ファーウェイもこの頃既に米国の動きをつかんで動いていた。購買の責任者が日本企業などに“サプライヤー詣で”を熱心に繰り返し、供給確保に奔走していたのである。
■参考記事:米国は中国ファーウェイのサプライチェーン途絶に動く
ただ、ファーウェイは平静を装っているものの、半導体設計大手の英アームとの取引停止のインパクトは大きい。ファーウェイが強気でいられるのは同社子会社ハイシリコンからの半導体供給があるからだが、米国由来の技術を含むアームの技術がこの半導体設計に使われており、半導体生産に打撃を受けるのは明らかだ。
またハイシリコンが半導体生産を委託している主たる委託先は台湾積体電路製造(TSMC)である。今のところ、これまでどおり供給を続けることを表明している。しかし実態はファーウェイからの要求と米国の圧力の間の板挟みで、双方から“踏み絵”を迫られる悩ましい状況に置かれているようだ。仮に米国から「利敵行為」と見なされれば、自らが米国の制裁対象にもなりかねないリスクを負っている。
トランプ大統領はファーウェイで“取引”するのか?
一方、トランプ大統領がファーウェイへの制裁も中国との取引の対象になり得ると言及して波紋を呼んだ。恐らく市場への安心材料として株価対策の面もあるのだろう。
トランプ大統領には昨年、中国通信大手ZTEへの制裁を習近平主席との取引に利用し成果を上げた成功体験がある。だが、ファーウェイ問題の根深さを見誤ってはいけない。
昨年8月の記事「米中は『貿易戦争』から『経済冷戦』へ」でも指摘したが、トランプ大統領と「オール・アメリカ」を分けて考えるべきだ。
「オール・アメリカ」とはワシントンの政策コミュニティーを形成する、米国議会、シンクタンク、諜報機関、捜査機関、などを指す。中長期的な視点で対中警戒感を強め、昨年10月のペンス副大統領の“新冷戦”宣言ともいうべき対中演説がその代表例だ。ファーウェイへの警戒感の震源地でもある。
他方トランプ大統領は自らの選挙戦にしか関心がなく、取引による短期の成果を求めている。彼にとってファーウェイ問題も取引材料の一つにすぎない。それをさせないのが「オール・アメリカ」の考えていることだ。オール・アメリカにとっては昨年、トランプ大統領がZTEを取引の材料にされたことは、「悔しい汚点」なのだ。そのため今回は、議会共和党主流も含めて黙っておらず、トランプ大統領に取引をさせないだろう。
「オール・アメリカ」のシナリオは明確だ。
懸念ある中国企業に対しては次の3段階で締め出そうとしている。
- 第1段階:米国の政府調達から排除する。米国政府が「買わない」「使わない」
- 第2段階:米国の民間企業に「買わせない」「使わせない」
- 第3段階:部材を「売らない」、製品を「作らせない」
ファーウェイについては、昨年8月に第1段階、そして今回は第2、第3段階に突入した。ファーウェイ以外についても、監視カメラの中国企業ハイクビジョンや人工知能(AI)企業など数社が今後、第1段階から第2、第3段階への移行対象として名前が挙がっている。先般、米国土安全保障省が、中国製ドローンが収集した映像データに中国当局がアクセスする可能性がある、と警告した。ドローンのトップ中国企業DJIも、第1段階の対象になる候補として名前が挙がっている。
こうした一連の動きはトランプ大統領に関係なく、ワシントンの「オール・アメリカ」として根深い動きであるため、トランプ大統領による関税合戦の取引とは一線を画して考えるべきだ。
サプライチェーンの次は「研究開発ネットワークの分断」
こうした米国の動きに対して、部材を供給する日本企業も、米国の規制に違反しない範囲で、どうファーウェイとの関係維持を図れるかを模索している。もちろん今後の成長を考えて、ファーウェイとの取引は大事なビジネスチャンスだ。しかし同時に、米国企業が手を引いた穴を埋めるような“漁夫の利”ビジネスには要注意である。仮に米国から見て、「利敵行為」「背信行為」と映れば、制裁対象にもなり得ることを経営者は現場にも徹底すべきだろう。
企業として注意すべきことをいくつか指摘したい。
米国の規制で「再輸出規制」がある結果、日本企業が供給する製品に米国製の技術、製品が25%以上含まれる場合は、米国の規制がかかることは、ようやく知られるようになってきた。
問題はそれにとどまらず、研究開発にも及ぶことだ。その際の落とし穴は「みなし再輸出」である。
ファーウェイとの関係強化のためにファーウェイとの共同研究をしている日本企業も多い。その際、米国由来の技術が含まれていれば、ファーウェイへの技術移転として「みなし再輸出」の規制対象になることはあまり知られていない。
さらに、米国の2019年度国防権限法により、米国の大学が懸念ある中国企業からの資金提供を受けたり、共同研究したりすれば国防総省の予算を受けられなくなる。この結果、米国の大学はファーウェイとの共同研究も打ち切っている。これが日本の企業・大学にも影響するのだ。
ファーウェイなど米国から見て懸念のある中国企業との共同研究を行っている日本の企業、大学は、米国の大学からみると、問題視される可能性がある。その結果、米国との共同研究に支障が生じる可能性が否定できない。経営者は輸出には注意を払っていても、研究開発部門のことは技術者任せになっているケースも少なくないだろう。
こうした米国の動きは「サプライチェーンの分断」だけではなく、「研究開発ネットワークの分断」にもつながりかねないインパクトがあるのだ。
中国が「軍民融合」をうたっていることから、民生技術の軍事転用には厳しく目を光らせることになることも指摘しておきたい。日本企業も輸出に際し、軍事用途に使われないよう用途確認を行うことに一応なっているが、企業の現場では形式チェックだけで形骸化している面も否めない。しかし、少なくともファーウェイ向けに対しては形骸化が許されない。日本企業も社内の輸出管理のあり方を再チェックすべきだろう。我々は80年代の東芝機械ココム事件の怖さを忘れてはならない。
また共同研究も成果が軍事転用されることのないよう歯止めが必要だ。
レアアースは中国の切り札になれるのか?
こうして米国が対中の切り札ともいえる「ファーウェイ・カード」を切ってきたことに、中国はどう反撃するのか。
「中国がレアアースで米国をけん制」との報道が飛び交っている。5月20日に習近平主席が江西省の磁石メーカーを視察訪問して、「重要な戦略資源だ」と強調したことに端を発して、対米輸出規制をほのめかした共産党機関紙の論評記事、国家発展改革委員会の声明発表と続いた。
磁石メーカーの視察訪問に対米交渉の責任者である劉鶴副首相を帯同させたのは、米国をけん制するためのメッセージだろう。同時に、対米弱腰外交と批判する共産党内の保守強硬派へのアピールの面もあるようだ。逆に言えば、米国によるファーウェイに対する事実上の禁輸措置に対して、有効な対抗策を打てないことへの裏返しでもある。これ以外に対抗カードになりそうなものが見当たらないのだ。
ただ一旦ここまでほのめかすと、習近平政権としても単なる国内向けのアピールにとどまらずに、実際にカードを切らざるを得なくなる可能性があることは懸念される。
レアアースを“十羽ひとからげ”に見る日本のメディア
日本の報道を見ていると、レアアースを十羽ひとからげに捉えて、中国が世界の生産量の7割を占めることや、米国のレアアースの輸入の8割を中国に依存していることが強調されている。だが、これでは表面的な理解しかできない。
レアアースは、環境規制の緩い中国での生産コストが安いのでシェアが高いだけで、中国が輸出規制すれば、価格が高騰し、他国の企業が代替供給できるため、レアアース規制は中国の強力な武器にはならないという主張もある。中国は世界の生産量は7割を占めていても、賦存(ふそん)量は世界の3~4割であることから、これは一面正しい。ただし、これもそう単純ではなく、レアアースの種類ごとに子細に見る必要がある。
中国は相当調べ上げたうえで、もっと焦点を絞った対応を考えているようだ。現在の中国は2010年に日本に対して供給途絶した際と同じではない。中国もこの当時の経験から学んでいる。私は当時、この問題の対処に奔走していた経験から、もう一歩踏み込んで考えてみたい。
まずレアアースは、少なくとも「軽希土類」と「重希土類」に分けて考えるべきだ。
前者はセリウム、ランタンなどガラス研磨、触媒、光学レンズなどに使われるものだが、中国以外の国からの代替供給は可能だ。実際、2010年当時も他国からの代替供給が増えて、その結果、中国の制裁解除後、価格が暴落したという苦い経験を中国はしている。
また供給途絶を受けた日本のメーカーはレアアースを極力使わない技術も開発し、状況は当時から劇的に変化している。現在の米国の対中依存度が8~9割だからといって、単純に壊滅的打撃を受けるというのは早計だ。2010年当時の日本企業と同様に、米国企業も代替供給、使用削減を大胆にするだろう。その結果、中国自身の首を絞めかねない、いわば“もろ刃の剣”なのだ。
他方、重希土類はジスプロシウムなど磁石に使われ、強力な磁性や耐熱性を出すために磁石に添加する。EV(電気自動車)のモーターに使うだけでなく、ミサイルの精密誘導装置や戦闘機のレーダー、ソナー装置などにも使われ、安全保障上の大きな懸念材料だ。これらは中国以外の代替供給ソースは短期的には困難だ。地質上、中国南西部に偏在し、まさにそこに狙いを定めて習近平主席は訪問視察している。
なお、同じく磁石に使われるネオジムは重希土類と軽希土類の中間に位置し、オーストラリアなどでも代替生産可能で、生産拡大の動きは既に出ている。
複雑な要素が絡み合う駆け引きが続く
2010年以降、米中双方で、レアアースを巡る動きは活発であった。
中国は2010年の経験から、その後、日本の磁石メーカーの一部から技術移転を得て、中国自身、磁石生産もある程度できるようになって、交渉力は当時よりは強くなっている。
米国も2010年の中国による供給途絶を受けて、国防上の重要問題とし取り上げられ、国防備蓄も含めてサプライチェーンを確保するための法案が成立している。2018年8月、投資規制、輸出管理など多面的な対中戦略を規定した2019年度国防権限法においても、国防総省が中国からレアアース磁石を購入することを禁止している。それとともに国内のレアアース生産への経済支援を与える法案も可決している。
仮に中国による米国への供給途絶があった場合、どうだろうか。
日本の磁石メーカーも米国への供給に制約がかかるだろう。他方、磁石メーカーにおける備蓄もある程度あるので、しばらくはしのげるかもしれない。ジスプロシウムを使わない磁石の開発もある程度進展している。しかしそれがどの程度実用可能か不透明だ。
2010年からの輸出規制に対しては、日米欧は世界貿易機関(WTO)に提訴して、2014年に中国は敗訴している。それにもかかわらずまた輸出規制を発動すれば、国際的に孤立を招きかねないリスクも計算に入れなければならない。
こうしたさまざまな要素を織り交ぜた米中の駆け引きがまさに行われている。日本の報道にあるような単純な「切り札」ではないのだ。恐らく主要20カ国・地域(G20)大阪会合まではこうした計算が行われ、仮に中国側の動きがあるとすれば、G20後の可能性が高いのではないだろうか。
従って、安倍総理がG20および日中首脳会談でこの問題にどう対処していくかが極めて重要になってくる。
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。

