9/4The Gateway Pundit<Screening and Q&A for Hard-Hitting New Documentary: ‘Hunter’s Laptop—Requiem for Ukraine’= 衝撃的な新作ドキュメンタリー「ハンターのラップトップ ― ウクライナへのレクイエム」上映と質疑応答>
米国社会はDS(FBI、CIA、軍産複合体を含む)や民主党、メデイア等、左翼によっていかに歪められてきたか。腐敗の極み。
2024年9月5日木曜日、受賞歴のある映画製作者イゴール・ロパトノク氏とジャーナリストで弁護士のシモーナ・マンジャンテ・パパドプロス氏が、シカゴのトランプ・インターナショナル・ホテルで新作ドキュメンタリー映画「ハンターズ・ラップトップ ― ウクライナへのレクイエム」の上映会と質疑応答を主催します。
予告編はここでご覧ください:

https://rumble.com/v5demzh-hunters-laptop-requiem-for-ukraine-official-trailer.html
「ハンターのラップトップ ― ウクライナへのレクイエム」は、ハンター・バイデンの悪名高いラップトップをめぐるスキャンダルを掘り下げ、政治腐敗、メディア操作、国際的陰謀の幅広い影響を探る痛烈なドキュメンタリーです。この映画はジョー・バイデン大統領の就任式から始まり、ラップトップの発見に至るまでの物議を醸した出来事と、発見後の出来事へと焦点を素早く移します。
このドキュメンタリーは、内部告発者、ジャーナリスト、弁護士などの重要人物へのインタビューを通じて、特にウクライナとブリスマ・ホールディングスに関するバイデン一族の腐敗の網を暴く。物語は、オリガルヒ、ディープステート、そして重要な情報を国民から隠蔽するためのメディアと大手テクノロジー企業の操作の影響を強調している。
この映画は、受賞歴のある映画監督であり、オリバー・ストーンと頻繁にコラボレーションしているイゴール・ロパトノクが監督とプロデュースを担当しています。ショーン・ストーンがエグゼクティブ・プロデューサーを務め、弁護士でジャーナリストのシモーナ・マンジャンテ・パパドプロスがメインのインタビュアーを務めます。ロパトノクとマンジャンテ・パパドプロスは、上映直後の質疑応答セッションに参加します。
ストーン氏とともに批評家から絶賛された映画『ウクライナ・オン・ファイア』を監督したロパトノク氏は、2020年に当時のトランプ弁護士ルディ・ジュリアーニ氏とトランプ陣営を検閲し、中傷し、破壊しようとした組織的な取り組みを逐一再現する映画を制作した。
「ハンターのラップトップ ウクライナへのレクイエム」では、ロパトノクはマンジャンテ=パパドプロスとともに、ニューヨークポストの記者ミランダ・ディバインからトランプ戦略家スティーブ・バノン、そしてジュリアーニ自身まで、すべての主要人物からインタビューを取っている。この映画は、ラップトップの話を検閲するために組織されたキャンペーンと、メディア、大手テクノロジー企業、司法省がそれを隠蔽しようとした陰謀を記録している。
この映画では、バイデン家の個人的な葛藤や道徳的葛藤、特に、このスキャンダルの被害者であると同時に加担者として描かれているハンター・バイデンについても検証している。ドキュメンタリーが進むにつれて、これらの出来事が、世界的な力関係、民主主義の崩壊、そして誤情報と政治的アジェンダが支配する時代における真実を求める闘いといった、より広範なテーマと結びついていく。
「ハンターズ・ラップトップ ウクライナへのレクイエム」は、最終的に現在の政治システムの完全性、メディアの役割、そして抑制されない権力が民主主義に与える影響に疑問を投げかけ、視聴者に見出しの背後にある不快な真実に立ち向かうよう促しています。
この特別上映は、正統派キリスト教徒連合(COCUS=Convention for the Coalition of Orthodox Christians)の初開催大会の一環として、国際政治戦略家のオルガ・ラヴァシ博士が主催する。
トランプ大統領の元国家安全保障担当大統領補佐官、マイケル・フリン中将がCOCUSキックオフで基調講演を行う予定。
出席者:イゴール・ロパトノク、オルガ・ラヴァシ博士、シモーナ・マンジャンテ・パパドプロス、ジョージ・パパドプロス、マイケル・フリン中将(COCUSの設立大会で基調講演を行う予定)
内容: 映画プレミアとQ&A
場所: トランプ・インターナショナル・ホテルのRebar
https://www.thegatewaypundit.com/2024/09/screening-qa-hard-hitting-new-documentary-hunters-laptop/

https://1a-1791.com/video/s8/2/5/N/6/y/5N6yt.caa.mp4?b=1&u=ummtf
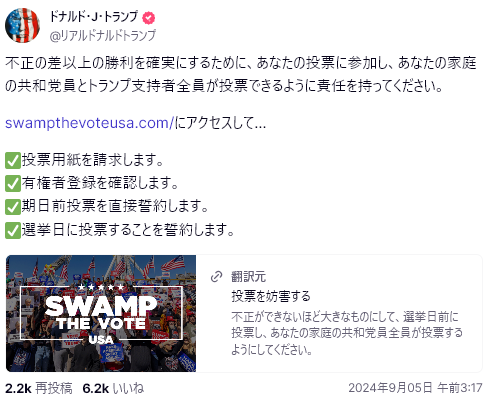

9/4Rasmussen Reports<Harris Can’t Separate Herself From Biden’s Record=ハリス氏はバイデン氏の実績から切り離せない>
カマラ・ハリス氏は現在、ジョー・バイデン大統領の不人気な政策の一部を否定しているが、大半の有権者は、副大統領も自身の失敗の責任を共有しており、バイデン氏の成功の功績も共有していると考えている。
ラスムセン・リポートの最新の全国電話・オンライン調査によると、米国の有権者の32%が、バイデンの政策の失敗についてハリス氏は大いに非難されるべきだと答え、23%はハリス氏もいくらか非難されるべきだと答えた。25%は、ハリス氏はバイデンの失敗についてあまり非難されるべきではないと考え、15%はハリス氏は全く非難されるべきではないと考えている。
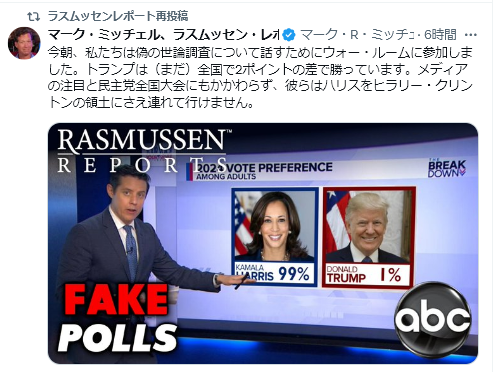
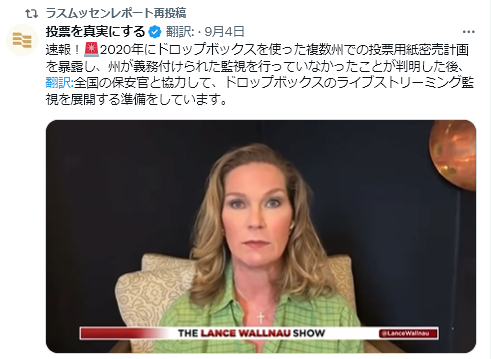
https://x.com/i/status/1831005670918787175

9/5阿波羅新聞網<实锤震动国际!普京公布中共隐瞒证据 赖清德提议激起千层浪—赖清德提议震动国际 俄爆中共卖国实锤证据=そのリアルな衝撃は世界を震撼させた!プーチンは、中共が隠蔽していた証拠を公表し、頼清徳の提議は波紋を呼んだ – 頼清徳の提議は世界を震撼させた ロシアは中共の売国の確固たる証拠を明らかにした>習近平が「無限の友情」と呼ぶ良き兄弟のような友人であるプーチンは、中共に何の面子も与えず、外務省報道官のザハロワは9/3、中共が領土を放棄すると述べた条約を発表した。そして中共はこれを中国人に隠し続けている。
ロシアのこの動きは中共の売国の証拠を世界に公開するに等しい。また、数日前に中華民国の頼清徳総統が行った声明をさらに裏付けるものとなっている。
頼清徳総統は8月末、台湾メディアとの独占インタビューで、「中国が台湾併呑を望んでいるのは領土保全のためではない。本当に領土保全のためなら、璦琿条約で署名したロシアが占領する土地を取り戻したらどうだろうか」と指摘した。頼清徳の声明は国際的に好意的な反応を示し、多くの外国メディアがこれを報じ、中国がロシアに占領された100万平方キロ以上の失われた土地を取り戻すのは、単に侵略しようとする領土36,000平方キロメートルの台湾よりも容易であると指摘した。
頼清徳は、9/2夜に放送されたテレビ番組「雅琴は世界を見る」の独占インタビューで、中国が本当に領土保全を気にかけているのであれば、中国は清朝がロシアに割譲した土地の返還も求めるべきだと明確に指摘した。さらに、「ロシアは現在“最も弱い立場”にあり、したがって、台湾を侵略したいのは領土関係のためではないことは明らかだ」と述べた。
新頭殻の報道によると、頼清徳の発言を受けて9/3、ロシア外務省報道官マリア・ザハロワがメディアの質問に答え、2001年7月 9月16日に調印された「善隣友好協力条約=露中の二国間関係の基本文書」の中で、ロシアと中国は以前の条約に含まれていた相互の領土主張を放棄したと主張した。その後、ロシアと中国は2004年10月14日に「ロシアと中国の国境の東部地域に関する補足協定」に署名、承認し、両国間の国境問題は最終的に解決された。
頼清徳が言及した1858年の「璦琿条約」は、黒竜江省の北、外興安岭の南の60万平方キロメートル以上、烏蘇里江の東約40万平方キロメートル、合計100万平方キロメートル以上の大清帝国の領土をロシアに割譲したことを指す。この条約は当時の清政府によって承認されず、後に1860年に署名された清露北京条約によって確認され、ロシア極東の現代の境界が決定され、それは中国が歴史上最も多くの領土を失った条約であった。ロシアと中国は、それぞれ1991年、1994年、2004年に旧ソ連とロシアとの国境の東部、西部に関して補充協定を締結したが、詳細は国民に公表されず、ブラックボックス操作として批判もあった。
頼清徳の前述の発言は当初台湾のみで放送されたが、思いがけず世界中で広範な反響を呼んだ。日本のベテランメディア人の矢板明夫は、頼清徳の「中共が台湾併合を望んでいるのは領土保全のためではない。そうでなければ清朝の璦琿条約でロシアに割譲された土地を取り戻したらどうだろうか」という発言は「中共にとって痛手だ」、「二重基準を持つ中国に強力な反撃を与えた。」と指摘した。
矢板明夫はさらに、中共当局が土地返還に言及しなかっただけでなく、中共元指導者江沢民政権が1990年代に多くの新たな土地をロシアに与えたと指摘した。納得するのは難しい。
強きには挫ける中国人の二重基準。

https://www.aboluowang.com/2024/0905/2099087.html

何清漣 @HeQinglian 4時間
このニュースから浮かんできた連想は、バイデンは習近平に米国の選挙に干渉しないという約束を要求したが(そして習近平も同意した)、それは失敗に終わり、サリバンはハリスが大統領になればバイデンの対中政策(戦略的曖昧さ)を継続すると面と向かって説明するために北京に行った。
どのように介入するのかは分からない。ドミニオンは華為のソフトウェアを使用しているという人もいる。
引用
陳小平 @xchen156 7h
孫雯が中国工作員として告発の最初の衝撃波:
CNNは水曜日、NYの中国総領事が追放されたと報じた。
NY州のホークル知事は火曜日のイベントで「総領事を追放したいとの意向」を表明した。
もっと見る
何清漣 @HeQinglian 10時間
中国語の記事「ハリスの詩と距離」を見た。着想はよく、トランプは牛乳とパンで生活必需品であり、ハリスは遠く離れた場所というのは間違っていない。気候変動や不法移民の権利はすべて、本国の納税者から遥かに遠く離れている。しかし、もし言っているのが詩であるならば、この詩はあまりにも醜い。 2020年以降、私が見てきたのは、政府がティーンエイジャーに性別変更を奨励し、BLMの破壊・略奪・放火、物価の高騰、社会秩序の急速な悪化、2,000万人を超える不法移民の流入を誇っている。
もっと見る
何清漣 @HeQinglian 12時間
トランプは国民に利益をもたらすため、政府支出(税金)を節約し、市職員のレントシーキング獲得の機会が遮断され、請負業者の金も遮断された。
この事件で、なぜトランプが市の利益集団から嫌われているのかがようやく分かった。
彼とジュリアーニは、ジュリアーニの統治下でNYが第二次世界大戦後最高の時代だったように、法治と治安良好な国際都市になることを望んでいる。
もっと見る
引用
張平 @pingzhang632 20h
1980 年、NYのセントラル・パークにあるウォールーマン・アイスリンクは長年補修せず、床が崩壊し、改修のため閉鎖を余儀なくされた。市政府は当初、300万米ドルを費やして2年で再建する予定だったが、1986年までに1,300万米ドルを費やしたが、完成には程遠い未完のプロジェクトとなった。トランプはトランプタワーからこの混乱を毎日見ていたが、ついには耐えられなくなり、市政府からその仕事を引き受けた(市政府は引き渡す気はなかった)。4か月で完成しただけでなく、市政府の予算も 75 万ドル節約した。それ以来、トランプ・オーガニゼーションは一銭も儲けずにスケートリンクを運営しており、年間数十万ドルの利益は公益事業や慈善基金に寄付されている。
もっと見る

何清漣 @HeQinglian 1時間
孫雯女史の話では、塩漬けアヒルは「祖国という母親」からの善意にすぎず、主な賄賂は金銭だった。 😂
https://bbc.com/zhongwen/simp/world-69320228
感想:優秀な子供を持つ中国人家族は米国政府で働くべきではない。そうしなければ、(賄賂は)防ぐにも防ぎようがない。
bbc.comより
横山氏の記事では、戦争被害についての個人の請求について、日本の裁判所の判断として、「戦争被害受忍論」、「立法裁量論」、「統治行為論」に立脚するのは妥当と考えます。
負けると分かっていて戦争(猪瀬直樹著『昭和16年 夏の敗戦』を読めば分かる)をした政府を持った国民が不幸と言うもの。日本は英米の謀略(もっと言えばスターリンも)に嵌められた自衛のための戦争を戦ったともいえるが、戦争回避のために米国世論を動かすとか、中国から撤退するとか、打つ手はあっただろうにと考えます。
今は中共の野心にどう対抗するかが大問題。放置すれば中共の奴隷になるのは必定。知恵を働かせ、共同で戦うしかない。
記事

米国は蛮行を永遠に恥じ続けなければならない(Hitesh ChoudharyによるPixabayからの画像)
現在放送中のNHK連続テレビ小説「虎に翼」の中で、いわゆる原爆裁判が取り上げられている。
すなわち、ドラマの主人公・猪爪寅子が裁判官として所属する東京地方裁判所の民事二十四部が、広島・長崎の原子爆弾による被害者が提起した、日本政府に損害賠償を求める訴訟を担当することになる。
ところで、戦後、日本政府は米の原爆投下に対して米国政府に抗議したのであろうか。
2007年7月3日付読売新聞は、次のような内容の記事を掲載している。
「政府は、長崎に原爆が投下された翌日の1945年8月10日、中立国のスイスを通じて『本件原爆(原子爆弾)を使用せるは人類文化に対する新たな罪状なり』と米国に厳しく抗議した」
「しかし、終戦後は、原爆投下について『米国に対して正式に抗議したことはないはずだ』(外務省筋)」
(出典:衆議院「米国による原爆投下に対する日本政府の対応に関する質問主意書」)
戦後、自国の安全保障を米国の核抑止力に頼ってきた日本政府は、核兵器の使用そのものが国際法上違法とは言えなかったのであろうと筆者は見ている。
さて、原爆裁判に戻る。
1955年4月、広島の下田隆一氏ら3人が岡本尚一弁護士を代理人として、国を相手に束京地裁に損害賠償と米国の原爆投下を国際法違反とすることを求めて訴訟を提起した。
岡本尚一弁護士は訴訟を起こす前に、原爆投下は国際法違反であり、米政府や関わった指導者に損害賠償を求める民事訴訟を起こせるという持論を『原爆民訴或問(みんそわくもん)』と題する9ページの冊子にまとめ、「原爆裁判」を呼びかけるために広島および長崎の弁護士会員全員に郵送した。
「原爆裁判」に関して束京地裁は、1963年12月に判決を言い渡した。
判決は、原告の損害賠償請求を棄却したが、「米軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とするものであった。
この裁判はその後、被爆者援護施策が前進するための大きな役割を担ったとされる。
訴訟提起後の1957年に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が制定され、判決後の世論の高まりもあり、1968年9月には「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」が施行された。
ところで、原爆裁判(東京地裁判決1963年)と同じように、シベリア抑留訴訟(最高裁判例1993年)や東京大空襲訴訟(最高裁判決2013年)においても国は、国の賠償責任は認めなかった。
その背景には、「戦争という国の存亡をかけた非常事態のもとでは、すべての国民は多かれ少なかれ生命、身体、財産の被害を耐え忍ぶことを余儀なくされるが、それは国民が等しく受忍しなければならないやむを得ない犠牲であり、国家は被害を補償する法的義務を負わない」とする「戦争被害受忍論」がある。
以下、初めに岡本尚一弁護士が執筆した『原爆民訴或問』について述べ、次に原爆裁判における原告及び被告の弁論の内容について述べ、次に、「戦争被害受忍論」について述べ、最後に核兵器の威嚇または使用の合法性に関する国際司法裁判所(IJC)の勧告的意見について述べる。
1.原爆民訴或問
極東国際軍事裁判(東京裁判)の判決から5年後の1953年、極東国際軍事裁判に主任弁護人の一人として参加していた弁護士の岡本尚一氏は、「原爆民訴或問(みんそわくもん)」と題する9ページの冊子をまとめた。
原爆投下は国際法違反であり、米政府や関わった指導者に損害賠償を求める民事裁判を起こせるという研究の末抱いた持論を伝えるためだった。
以下は、岡本尚一氏が執筆した『原爆民訴或問』(1953年5月)の抄本である。
(出典:ヒロシマ遺文、岡本尚一『原爆民訴或問』(抄))
「拝啓 人類と文明の為一書を敬呈することを御許し下さいませ。私は1946年(昭和21年)6月から2年有半に亘り東京に於ける極東国際軍事裁判に主任弁護人の一人として参加していました」
「其間終始私の念頭にありましたことは、戦勝国側の極めて重大な国際法違反が勝てるが故に何等その責任を問われない不公正でありました」
「然し私は、講和条約が発効した暁には、戦勝国側の指導者から広島・長崎に対する原爆投下については、悔恨の情を披瀝されるであらうと心ひそかに期待しつづけてきたものであります」
「然るに、それより既に1ケ年を経た今日に於て、未だかかる言葉の片鱗だに聞くことを得ないのであります」
「これが基督教を以て普遍的な宗教となし、ヒューマニズムを以て民主主義の基調とする米国・英国の態度であることは遺憾の極みであります」
「私は当時から講和条約が発効した後においては、尠く(すくなく)とも広島及び長崎に対する原爆の投下についてはこの責任を民事不法行為の面において採りあげて原爆投下の決定に参与した指導者及び国家に対して不法行為の管轄裁判所に対し提訴致し度いと念願し、これを親友にも語ってまいりました(後略)」
岡本氏は、次の理由から訴訟が可能と説いた。
(以下の出典は、中国新聞「ヒロシマの空白 未完の裁き」(2024年4月24日)である)
一つは、原爆の類をみない残虐性、猛烈な爆風と熱線は膨大な地域を破壊してあまたの市民を殺傷し、放射線が苦しみをもたらし続ける。
ハーグ陸戦条約が禁じている無差別攻撃や「不必要な苦痛を与える兵器」の使用に当たり、国際法違反は間違いない。
もう一つは、人権の尊重。
全人類の尊厳を掲げた世界人権宣言(国連で1948年採択)や、1947年施行の日本国憲法が定める基本的人権の尊重を請求の根拠に位置付けた。
岡本氏の訴訟の構想は1953年1月、新聞で報じられた。すると原爆被害者から次々と激励の手紙が届いた。
若い頃から短歌を続け、歌集を出したこともあった岡本氏は、当時の思い出を読んでいる。
「夜半に起きて被害者からの文読めば涙流れ声立てにけり」
2.原爆裁判における原告および被告弁論内容
本項は、日本反核法律家協会ホームページの「資料1原爆裁判基礎データ」を参考にしている。
(1)原爆裁判の経過
1945年8月6日 広島に原爆投下
8月9日 長崎に原爆投下
8月15日 終戦
1952年4月28日 講和条約発効
1953年2月 岡本弁護士(1892-1958)は、広島・長崎の全弁護士に対して、被爆者を原告とし、米国政府およびハリー・トルーマン(大統領)を被告として、原爆投下の国際法違反を明確にし、被った被害の賠償を求める「原爆裁判」を呼びかけるため「原爆民訴或問」を広島および長崎の弁護士会員などに郵送した。
米国での裁判について、米国の法律家からこの裁判には法律的根拠がない、日米親善に有害であるとして、全面的に反対され、さらに高額な弁護士費用最低2万5000ドル(1ドル360円換算で900万円)が必要との回答を受け、米国での裁判を断念した。
1954年5月 戦勝国の裁判所で原爆投下の違法性を問う裁判は断念
1955年4月25日 原爆訴訟提起 東京地裁、大阪地裁の裁判は東京に併合
1958年4月5日 岡本弁護士死去
1963年3月5日 最終弁論
1963年12月月7日 東京地裁判決(裁判長裁判官:古関敏正、裁判官:三淵嘉子、裁判官:高桑昭)
原告側は、敗訴判決であったが、国際法違反などを認定した内容を評価し、控訴せず判決は確定した。
(2)裁判における弁論の内容
ア.原爆訴訟提起(1955年4月25日)
(ア)原告
原爆訴訟は、1955年4月25日に東京地方裁判所原告3人、そしてその翌日に大阪地方裁判所原告2人により提訴された。
原告代理人は、両裁判所とも岡本尚一氏、松井康浩氏ら10人(大阪4人、東京5人、広島1人)であった。
1960年2月に東京地裁で第1回口頭弁論が開かれ、東京地裁と大阪地裁の訴訟が併合がされて一緒に審理されることになった。
(イ)請求の趣旨
被告国は、原告下田に対して金30万円。原告多田、原告浜部、原告岩渕、原告川島に対して各金20万円を支払え。
(ウ)請求の原因
・米国は、広島と長崎に原爆を投下した。
・原爆は人類の想像を絶した加害影響力を発した。
・原爆投下は、戦闘員・非戦闘員たるを問わず無差別に殺傷するものであり、かつ広島・長崎は日本の戦力の核心地ではなかった。
しかも、フランク委員会の勧告を無視して無警告で投下した。この投下は、防衛目的でも報復目的でもないことは明らかである。
・原爆投下は、実定国際法に違反する。
・仮に、原爆投下が戦闘行為であると仮定しても、国家免責規定の適用はあり得ない。実定国際法に違反するのみならず、その加害影響力の性質上、投下は許されないからである。
・広域破壊力と人体に対する特殊加害影響力は人類の滅亡をさえ予測せしめるものであるから、人類と人類社会の安全と発達を志向希求する国際法とは相容れない。
仮に、実定国際法が適用されないとしてもその使用は自然法ないし条理国際法が厳禁するところである。
・国家免責規定を原爆投下に適用することは人類社会の安全と発達に有害であり、著しく信義公平に反する。
・米国は平和的人民の生命財産に対する加害について責任を負う。被害者個人に賠償請求権が発生する。
・対日平和条約によって、日本国民個人の請求権が雲散霧消することはあり得ない。
憲法第29条第3項(筆者注:第29条第3項:私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる)により補償されなければならない。
・補償されないということであれば、吉田茂全権たちは、日本国民の請求権を故意に侵害したことになるので、国家賠償法(筆者注:国家賠償法第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、 故意又は 過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる)による賠償義務が生ずる。
・人類の経験した最大の残虐行為によって被った原告らの損害に対して、深くして高き法の探求と原爆の本質に対する審理を行い、その請求を認容していただきたい。
イ.被告国の答弁書の内容(19551年10月21日)
・原告の請求を棄却する。
・被告らに対する補償義務または賠償義務は否認する。
・原爆使用が、国際法に違反するとは直ちには断定できない。したがって、原告らに賠償請求権はない。
・原告の主張する権利は、各国の実定法に基礎を有することなく、したがって、権利の行使が法的に保障されていないもの、権利として実行されるべき方法ないし可能性を備えないものである。
・講和条約によって請求権が認められるとしても、それは講和条約によるものである。敗戦国の国民の請求が認められることなど歴史的になかった。
原告らの請求は、法律以前の抽象的観念であるというだけではなく、講和に際して、当然放棄されるべき宿命のもの。
・原告が請求権なるものを有するとしても、それは何ら権利たるに値しない抽象的観念でしかない。そのような観念の存在や侵害を前提とする請求は失当である。
・原告らの権利は、平和条約によって、はじめて実現できなくなったものではない(元々ないのだ)。
・憲法第29条は、これによって直ちに具体的補償請求権が発生するわけではない。具体的立法が必要だ。
・国は、原告らの権利を侵害していない。平和条約は適法に成立しているので、締結行為を違法視することはできない。被告に国家賠償義務はない。
・被告は、被爆者に対して深甚の同情を惜しむものではないが、慰藉(いしゃ)の道は、他の一般戦争被害者との均衡や財政状況等を勘案して決定されるべき政治問題である。
ウ.原告による被告への釈明要求(1955年10月22日)
・被告は原爆投下が国際法に違反することを否定しているが、1945年8月10日、日本政府は、スイス政府を通じて、米国に対して原爆投下が国際法に違反するとの抗議を行い、非人道的兵器の使用放棄を申し入れている(岡本弁護士は、「世紀に残る大抗議」としている)。
この抗議と矛盾するではないか。
・被告は、原告の主張は法的権利ではないというが、それは的外れである。
・「講和に際して当然に放棄される宿命」とは法律的にどのような意味か。
エ.被告の釈明(1956年2月8日)
・当時交戦国として新型爆弾の使用の放棄を求めたが、それは、新型爆弾の使用が戦時国際法の原則および人道の根本原則を無視したものであったからである。
しかし、交戦国という立場を離れて客観的に眺めると、原子兵器の使用が国際法上違法であると断定されているわけではない。
・原告は、原爆投下を国内法上の不法行為としているようだが、原爆投下は害敵手段としてのものであり、国内法の不法行為として取り上げられる問題ではない。原告の主張は的外れである。
・古来、敗戦国が戦勝国に賠償を請求した例はない。戦勝国に国際法違反があった場合も請求した例がない。
賠償請求権が放棄される例もある。これは国際慣例である。よって、「放棄される宿命である」
オ.東京地裁判決(1963年12月7日)
・米軍による広島・長崎への原爆投下は、国際法が要求する軍事目標主義に違反する。かつ原爆は非人道的兵器であるから、戦争に際して不必要な苦痛を与えてはならないとの国際法の基本原則に違反する。
・しかし、国際法上の権利をもつのは、個別の条約で認められていない限り、国家だけである。被爆者は国内法上の権利救済を求めるしかない。
・日本の裁判所は米国政府を裁くことはできない。
・米国法では、公務員が職を遂行するにあたって犯した不法行為については賠償責任を負わないのが原則とされている。
・結局被爆者は、国際法上も国内法上も権利をもっていない。対日講和条約で全権団が権利を放棄しても、被爆者には何の影響も与えていない(元々権利がない)。
・被爆者が十分な救済策をとられなければならないことはいうまでもないが、それは裁判所の職責ではない。政治の貧困を嘆かざるを得ない。
(3)筆者コメント
この原爆裁判の判決では原告個人の損害賠償請求権は認めなかったものの、原爆投下(核兵器使用)が国際法違反であることを認めた最初の公権的判決として極めて有名である。
その後、1996年の国際司法裁判所(IJC)における勧告的意見において核兵器の使用または威嚇は一般的に国際法に違反するとの判断がなされた。この原爆裁判の判決が、その先例的意味を持つとされる。
また、既述したが、国の結果責任の可能性や政治の貧困を嘆いたことから、原爆特別措置法に道を開いたともいわれている。
3.戦争被害受忍論
(1)戦争被害受忍論の経緯
本項は、九州大学准教授直野章子氏著「戦争被害受忍論‐その形成過程と戦後補償制度における役割」(2016年)を参考にしている。
戦争という国の存亡をかけた非常事態のもとでは、すべての国民は多かれ少なかれ、生命、身体、財産の被害を耐え忍ぶことを余儀なくされるが、それは国民が等しく受忍しなければならないやむを得ない犠牲であり、国家は被害を補償する法的義務を負わない。
これは「戦争被害受忍論」(以下「受忍論」)と呼ばれるロジックである。
戦後補償関連訴訟で引用されることが多いため、受忍論を「国家無答責の法理」(国家無答責とは、国の権力行使によって個人が損害を受けても、国は損害賠償責任を負わないとする明治憲法下の原則である)と勘違いしている向きもあるようだが、そうではない。
戦後処理によって戦後生じた損害(在外財産損失)に対して日本国憲法を根拠に補償を請求する権利(第29条第3項)を否定する論理として、1968年に在外財産補償請求事件において下された最高裁判決によって誕生し、80年代後半以降、戦時中に生じた損害への補償請求権を斥(しりぞ)ける判決において拡大適用されていったために、国家無答責の法理であるとの誤解が広まった感がある。
- 在外財産補償請求事件
さて、受忍論のリーディング・ケース(先例)となった在外財産補償請求事件をみてみる。
1968年に最高裁判決が下されることになる事件である。次に1968年に在外財産補償請求事件において下された最高裁判決を見てみる。
ことの始まりは1941年12月8日まで遡る。
戦争が勃発し、交戦国となったカナダに在住していた原告は、所有財産を残したまま日本に引揚げることになった。
原告は現地に残していた財産の所有権を失うことになった。
そこで、所有財産が賠償の一部として処理されたことは公用収用にあたるとして、憲法第29条第3項(「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」)の適用を主張して、日本政府を相手に訴訟を起こしたのである。
判決文で打ち出された受忍論は次のようなものであった。
「ところで、戦争中から戦後占領時代にかけての国の存亡にかかわる非常事態にあっては、国民のすべてが、多かれ少なかれ、その生命・身体・財産の犠牲を堪え忍ぶべく余儀なくされていたのであって、この犠牲は、いずれも、戦争犠牲または戦争損害として、国民のひとしく受忍しなければならなかったところであり、右の(対日平和条約による)在外資産の賠償への充当による損害のごときも、一種の戦争損害として、これに対する補償は、憲法の全く予想しないところというべきである」
「(中略)在外資産の喪失による損害も、敗戦という事実に基づいて生じた一種の戦争損害とみるほかはないのである」
「これを要するに、このような戦争損害は、他の種々の戦争損害と同様、多かれ少なかれ、国民のひとしく堪え忍ばなければならないやむを得ない犠牲なのであって、その補償のごときは、さきに説示したように、憲法29条3項の全く予想しないところで、同条項の適用の余地のない問題といわなければならない」
- 東京空襲訴訟
在外財産補償請求事件の受忍論が、最高裁判決が戦争損害補償請求事件の判決のなかで初めて援用されたのは、妻と幼子を東京空襲で失った遺族が1979年に起こした訴訟においてである。
旧軍人らに対しては補償があるにもかかわらず、一般民間人の戦争被害者には何の措置も講じられていないことを取り上げて、原告は国に対して損害賠償と損失補償を請求した。
国側は「空襲による死亡は、一般の戦争災害であるところ、戦争という国家存亡にかかわる非常事態においては、国民のすべてが多かれ少なかれその生命・身体等の犠牲を余儀なくされるのであり、その損失を被告が当然に補償しなければならないというものではなく、その補償は憲法のまったく予想しないところというべきである」と、上記のリーディング・ケースを引用して国の補償責任を否定した。
東京地方裁判所は国の主張を採用したうえで、原告の家族の死を「公法的受忍義務の範囲内」と位置づけて、それに対する補償については「立法政策の問題」であるとする判決を1980年1月に下して原告の訴えを退けた。
第2審の東京高裁も同年5月に地裁の判決を擁護し、判決が確定した。
日本国憲法下において、生命の損失に対する受忍義務が説かれた初めての司法判断である。
- 原爆被爆者対策基本問題懇談会意見書
訴訟事案ではないが、受忍論が最も規範的な形で適用されたのが、原爆被爆者対策基本問題懇談会(基本懇)の意見書である。
基本懇設置の直接の契機は、韓国人被爆者・孫振斗が被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の最高裁判決(1978年3月)であった。
最高裁は原爆被害を招いた戦争に対する国の責任を指摘し、国家補償が適当であると示唆したが、それは、被爆者対策を社会保障制度の枠内に収めることで被害に対する補償責任を否定してきた政府の見解に再考を迫ることになった。
最高裁判決を受けて、被爆者対策の「基本理念および基本的在り方」を検討するために、79年5月に厚生大臣の私的諮問機関として基本懇が設置され、1980年12月に意見書が提出された。
意見書では、被爆者対策の基本は「被爆者の福祉の増進を図る」ための社会保障対策であるとして、被害に対する国の法的補償責任は否定された。
そのうえで、放射線による晩発性の健康被害のみが「特別の犠牲」、つまり「広い意味における国家補償の見地」から補償する対象として認められた。
加えて、国民は戦争被害を受忍すべしとの規範論が展開されたのである。
- 東京空襲集団訴訟・大阪空襲訴訟
2008年3月に東京地裁で、2008年12月に大阪地裁で提訴された2つの空襲訴訟において受忍論が争点となった。
戦後60年を過ぎてから上記の2つの集団訴訟が提起された背景には、旧軍人軍属との援護上の格差が憲法違反の域に達しているとの認識があった。
サンフランシスコ講和条約発効以降、旧軍人軍属とその遺族に対する援護と補償の総額が約50兆円以上に上るのに対して、非戦闘員の空襲被害者には何ら援護や補償の措置がなされていないという差別的扱いについてである。
しかし、名古屋空襲訴訟の最高裁判決(1987年6月26日の最高裁判決は、被告側の主張通り、受忍論と立法裁量論を併用しながら原告の訴えを退けた)が大きな壁となっているために、受忍論の克服が一つの重要課題として取り組まれた。
2009年12月14日の東京地裁判決、2011年12月7日の大阪地裁判決および2012年4月25日の東京高裁判決では受忍論が採用されなかったが、2013年1月16日に下された大阪高裁判決においては引用された。
(2)筆者コメント
「在外財産補償請求事件を通して生み出された受忍論は、その後の戦後補償関連訴訟で繰り返し援用されることによって、判例としての地位を確たるものにした」
「そのため、いかにも法律論であるかに映るが、上記で示したように、受忍論は法律論を装った政治論であると結論づけることができる」
これは、九州大学准教授直野章子氏の結論である。筆者も同感である。
筆者は、受忍論が生まれた背景には2つの事情があったと見ている。
一つは、「一人ひとりに補償していたら、国家財政がもたない」という敗戦国日本の財政上の事情もあったのであろう。
もう一つは、戦前の我が国においては、公権力の行使について国が責任を負わないという国家無答責の法理が有力であったということの影響が当時も残っていたのであろう。
戦後、日本国憲法の施行に伴い、国家賠償法(昭和22年法律第125号)が制定され、従来、国の権力行為については、国の公務員が職務上違法に損害を与えた場合でも国は責任を負わない(いわゆる国家無答責の法理)とされていたが,このような行為についても,損害賠償の請求が可能となった。
受忍論により原告の請求を棄却してきた司法だが、必ずしも被害者救済の必要がない、と言っているわけではない。
「立法によって解決すべき問題」という指摘が大抵なされている。
そして、戦争被害者を救済する措置法としては、原爆特別措置法や空襲被害者等援護法、沖縄戦時被害援護特措法などが成立している。
4.核兵器の威嚇または使用の合法性に関する国際司法裁判所(IJC)の勧告的意見
(1)IJCの勧告的意見
以下、日本の原爆裁判の判決が先例として影響したとされる1996年のIJCの勧告的意見について述べる。
1994年12月、国連総会が「核兵器による威嚇やその使用は、何らかの状況において国際法の下に許されることがあるか」について、国際司法裁判所(IJC)に対して勧告的意見を要請する旨の決議を採択した。
この国連総会の諮問に対して、IJCは、1996年7月8日に勧告的意見を提出した。1940年代に核兵器が開発されて以降、国際的な司法機関が核兵器の威嚇または使用の合法性(違法性)について判断を下した初めての事例である。
IJCの勧告的意見(出典:https://www.un.org/law/icjsum/9623.htm)は次の通りである。筆者の翻訳による。
- 核兵器の威嚇や使用を特段認可する慣習法も従来の国際法も存在しない。
B.核兵器の威嚇や使用そのものを包括的かつ普遍的に禁止する慣習法も従来の国際法も存在しない。
- 国連憲章第2条第4項(注1)に反し、第51条のすべての要件(注2)を満たさない核兵器による威嚇または武力行使は違法である。
注1:武力による威嚇または武力の行使を慎む。
注2:個別的または集団的自衛の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
- 核兵器の威嚇または使用は、武力紛争に適用される国際法の要件、特に国際人道法の原則と規則の要件、ならびに核兵器に明示的に対応する条約およびその他の約束に基づく特定の義務とも適合するものでなければならない。
- 上記の要件から、核兵器の威嚇または使用は一般に、武力紛争に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に違反することなる。
ただし、国際法の現状と、自由に使える事実の要素を考慮すると、裁判所は、国家の存続そのものが危険にさらされるような自衛のための極端な状況において、核兵器の威嚇や使用が合法であるか違法であるかを最終的に結論付けることはできない。
(2)各国の意見陳述
さて、IJCの勧告的意見の審理にあたっては、1995年5月15日から9月20日に間に22か国の政府が意見陳述を行い、そのうちの20か国は文書での意見提出も行った。
またさらに22か国の政府が文書での意見提出のみを行った。
したがって44か国の政府と世界保健機構(WHO)が核兵器使用・威嚇の合法性について意見表明を行った。
中国を除くフランス、英国、ロシア、米国の4つの核保有国は、状況に応じて核兵器使用が合法的であることも主張した(筆者注:中国は意見陳述も文書での意見提出もしていないようである)。
これに対しては他の大多数の諸国が、核兵器使用・威嚇の違法性を主張した。
日本政府は、文書および口頭での意見陳述において一貫して核廃絶への政治的意思を強調しつつ、法的判断に関しては必ずしも明確ではない態度をとった(出典:広島大学平和科学研究センター篠田英朗准教授著「核兵器使用と国際人道法」)。
(3)筆者コメント
上記のIJCの勧告的意見E項の後半の「国家の存亡そのものが危険にさらされるような、(中略)裁判所は最終的な結論を下すことができない」という部分は、統治行為論を反映していると筆者は見ている。
ところで、前述した原爆訴訟で岡本弁護士は、サンフランシスコ平和条約で、日本が連合国に対する賠償請求権を放棄したことが、吉田茂全権たちが日本国民の請求権を故意に侵害したのであるから国家賠償法により賠償責任が生ずると主張しているが、これには無理がある。
戦争を始める、戦争を終結する、平和条約を締結するなどは、国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であり司法審査の対象から除外されるべきものであると筆者は考える。
また、前項で述べた戦争被害受忍論であるが、戦後生じた損害への損害請求権を否定する論理としては、統治行為論も使用できたであろうが、戦後の新しい民主国家日本として受忍論という新しい論理を生みだしたのだろうと筆者は見ている。
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。

