中国の歴史は権力闘争の歴史です。決して民主化することはありませんでしたし、これからも長期に亘って民主化することはないと思われます。為政者側の腐敗がひどく、権力を握れば必ずや富を独り占めしようとします。人民は収奪の対象でしかありませんし、侵略の先兵として弊履の如く捨てられる運命にあります。中国人に高貴な精神を求めても無駄と言うもの。“対牛弾琴”というやつでしょう。孔子だって世の中に受け入れられなかったというのは中国社会が如何に弱肉強食で動いているのかを表しています。日本も徳川幕府時代、朱子学を武家の道徳と定めたので、論語の影響を受けて、中国人というのは公共道徳を守る優れた民族との思い入れがあったと思います。小生が中国から帰国した11年前に中国の実態を話したら、「国粋主義者」とか「人種差別主義者」とか罵られたものでした。今は日本にも中国人が沢山来て、その民度の低さが目に見えるようになったので、今話せば誹謗されることはないと思います。日本人が如何にメデイアという権威に弱いのかと言う証左にもなります。メデイアは左翼・リベラルの巣窟で自分の都合の悪いことを主張されると声高にラベル貼りをするか、完全に無視します。左翼人士は須らく、スターリンや毛、ポルポトの人民虐殺の歴史を直視すべきでしょう。そうすれば、左翼ではいられなくなるはずなのに。誠実さが足りない連中で、軽蔑・唾棄すべき人間です。
習近平は狡猾で、敵を打倒するのにいろんな手を打つでしょうが、敵は日本人のように甘くはありません。足をどのようにして引っ張るか知恵を巡らしている筈です。人事の問題こそが彼が権力を握れるかどうかの分水嶺になるのは間違いありません。①王岐山の定年延長②習自身の定年・任期延長です。でも本文にありますように、下剋上はありますし、下台(=step down)すれば、韓国大統領のように法の裁きを受ける可能性が高いと思われます。反腐敗運動をやりすぎ、恨みを沢山買ったためです。言ってみればこれも易姓革命の一つなのかも。権力者が如何に法を守らず、人治で政を行ってきたかという事です。人民の生命など鴻毛の如く考えているのでしょう。こういう国に生まれなくて良かったと思い、中国のような国にしないためには、中国の侵略に対抗して、日本の防衛を強化しなければなりません。左翼が良く言っています「中国が攻めてくることはない」というのは尖閣の現実を見ない議論です。騙されないように。何時も言っていますように中国人の基本的価値観は「騙す方が賢く、騙される方が馬鹿」と言うものですから。
記事
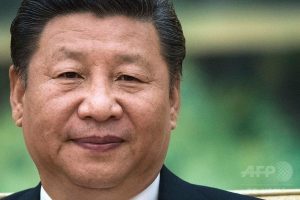
中国・北京でジャンマルク・エロー仏外相(写真外)と会談を行う中国の習近平国家主席(2016年10月31日撮影、資料写真)。(c)AFP/FRED DUFOUR〔AFPBB News〕
習近平政権は来年秋の第19回党大会に向け、内政・外交ともに正念場を迎える。
内政では10月に開かれた「6中全会」(中国共産党第18期中央委員会第6回全体会議)で党における「領導核心」の座を手に入れ、権力基盤をさらに固めた。とはいえ、党大会で自分の裁量による指導体制を作り上げるために、やるべきことはまだ多い。
外交では、米国で誕生するトランプ新政権への対応が重要な課題となる。習近平政権にとっては、トランプ新政権の外交・安全保障政策がどう変化するかを見極め、トランプ新政権とどう折り合いをつけていくかが問われることになる。
(参考・関連記事)「習近平がどうしても『核心』の座が欲しかった理由」
トランプ新政権への期待
米大統領選挙でのトランプ候補の当選は、中国でも予想外の事態であった。しかし、同候補の掲げた「アメリカ・ファースト」に基づくTPP(環太平洋パートナーシップ協定)の否定や、同盟関係の見直しといった政策が中国にとって好ましい部分があることは確かであり、トランプ政権の誕生は中国で好意的に受け止められている。
たしかに、TPPや「アジア・リバランス」といったオバマ政権の政策は、中国の台頭を経済と軍事の両面から封じ込めようとするものだった。それを否定するトランプへの期待が中国で湧き上がったとしても不思議ではない。
しかし、トランプ新政権が中国の都合のいいように動く保証はない。オバマ政権の政策の逆を目指すにしても、トランプ政権がオバマ政権よりもむしろ中国に厳しい対応を取る可能性は排除できないからだ。
習近平政権が求心力を高めるために「愛国主義」というナショナリズムを称揚しているように、トランプ新政権も「米国を再び偉大な国にしよう」というナショナリズムを表面に押し出してきた。トランプのナショナリズムが「孤立主義」とイコールであるとは限らないのである。
トランプ政権の対中外交がどのようなものになるかは、時間が経つにつれて明らかになっていくだろう。しかし、それがどのようなものであれ、習近平政権は、オバマ政権に提示してきた、米中が対等の立場に立つ「新型大国関係」の構築を目指すことになろう。
主席制の復活を画策か?
習近平政権にとって、むしろ問題なのは内政である。
習近平は10月の6中全会で、党における「核心」の座を手に入れ、1980年に鄧小平が主導して作られた「党内政治生活に関する若干の準則」(以下「準則」)を大きく書き換えた。
1980年の「準則」のキーワードは「集団指導(集体領導)」であった。毛沢東の個人独裁がもたらした「文化大革命」の過ちを繰り返すことのないよう、「集団指導体制」が謳われたのである。これに沿って、翌1982年に開催された第12回党大会では、「党中央委員会主席」が廃止され「党中央委員会総書記」となった。
中国では1949年の建国以来、「党中央委員会主席」が党における最終的な意思決定者だった。毛沢東は、まさにその役割を担ってきた。しかし、「党中央委員会総書記」は党中央委員会の最高指導者と位置づけられるものの、意思決定は党中央政治局常務委員会における多数決に委ねられる。主席制を廃止することによって、党中央で毛沢東のような独裁を再現できないようにする工夫であった。
習近平は、10月の6中全会で新たに採択された「新情勢下の党内政治生活に関する若干の準則」で、この個人独裁回避のための「集団指導」を大きくトーンダウンさせてしまった。
より正確に言えば、1980年の準則では独立した項目として「集団指導」を取り上げていたのが、新しい準則では「集団指導」を「民主集中制」を構成する要素の1つとしている。この書き換えは、「領導核心」を「集団指導」よりも優先したと受け止めることもできる。
それをもって、習近平が主席制の復活を画策していることは十分に考えられる。領導核心に位置づけられた以上、自分が党における最終意思決定者であることの制度的保証として、総書記ではなく主席の呼称こそがふさわしいと判断しても不思議ではないからである。
江沢民派を一掃したい習近平
しかし、主席制の復活には当然のことながら党内に強い抵抗が予想される。おそらく、そこまで露骨な権力の集中を進めることはないと考えるのが自然である。
党内で権威を増した習近平が目指すものは、他にあるはずだ。それは第1に、個人の権限強化による「内規の改定」であろう。
内外の報道によると、「七上八下」という内規(いわゆる「潜規則」)、すなわち党中央政治局常務委員に選任される人物は「67歳以下ならOKだが68歳はダメ」という原則を見直すべきだとの声があがっているという。たとえ68歳を超えていてもその人物が余人を持って代えがたい能力があるなら、任務を継続できるという論理である。その「余人を持って代えがたい能力」を持つ人物とは、習近平のもとで反腐敗に辣腕を揮う王岐山である。
もう1つ目指すものがあるとすれば、党中央政治局常務委員会の人事刷新であろう。
胡錦濤時代は9名の常務委員がいたが、習近平時代になって7名に減った。理由は明示されていないが、裏で画策したのが「第3世代の核心」であった江沢民だとすれば、江沢民派のための多数派工作で人事を動かした可能性が高い。
胡錦濤時代、常務委員の中で純然たる「非江沢民派」は、胡錦濤総書記と温家宝総理だけだった。習近平時代にしても、江沢民の息のかかっていないのは共青団出身の李克強総理だけである。次期党大会で2期目を迎える習近平にとって都合のいい常務委員会人事とは何かといえば、まずは江沢民派を一掃することであり、反腐敗で辣腕を揮った王岐山の留任であろう。
王岐山の留任が実現すれば、「次の次」である2022年の第20回党大会を69歳で迎える習近平自身の「3期続投」の可能性も出てくる。習近平は3期続投を現実のものとするために、かつて鄧小平が1982年に現行憲法を決めたように国家主席の「2期10年」という憲法の定めを書き換えるかもしれない。
後継者を決めなければ求心力を保てる
もし「3期続投」を目指すとすれば、習近平はさらなる権威確立のために、“次期常務委員会で後継者を指名しない”ということも考えられる。
胡錦濤や習近平は、ともに総書記の後継者として国家副主席と中央党校の校長を兼務する形で常務委員会入りし、4中全会ないしは5中全会で中央軍事委副主席となり、総書記に就任するための研鑽を積んだ。もし習近平が後継者を決めるなら、同様の処遇で対応することになる。
しかし、後継者を決めれば習近平への求心力が徐々に低下するのは間違いない。そこで、あえて後継者を決めないままにしておき、求心力を保つというわけである。
しかも、それはきわめて簡単にできる。政治局常務委員のポストを5つに絞り、総書記、国務院総理、全人代常務委員長、全国政協主席、紀律検査委書記に限定することによって、後継者の入る余地をなくしてしまえばいいのだ。
同時に、習近平、李克強、王岐山が留任するとして、残りの2ポストの1つを習近平の側近である栗戦書・党中央弁公庁主任にあてがえば、それで習近平側が3名となり過半数を占めることになる。そうすることによって、習近平は「領導核心」の権威を振りかざすことなく、従来の「集団指導体制」を維持して多数決で意思決定をすることが可能になる。「個人独裁」を批判されることなく、自分の思うような政権運営が可能になるというメリットもある。
誰かに剥奪されても不思議ではない核心の座
しかし、このようなシナリオ通りに物事が進むかどうかは分からない。
そもそも習近平自身が、「領導核心」の座を江沢民から奪い取っているからである。
具体的に言えば、習近平は領導核心の座を得るために、「腐敗撲滅」を理由に周永康や徐才厚、郭伯雄といった江沢民につながる人脈を摘発することで江沢民の権力に挑戦し、ついに核心の座を奪い取った。
だが、このことによって、中国共産党の指導における核心の位置づけは「絶対的」なものから「相対的」なものになってしまった。もはや、核心は、誰も挑戦できない権威の象徴ではなくなっている。これは習近平が想定していなかった現実だろう。
振り返ってみれば、江沢民の核心の座も自らが絶対的な権力を行使して手に入れたものではなかった。鄧小平が「毛沢東が第1世代の核心であり、第2世代は自分が核心なのだろう」と言ったとき、その「核心」は、誰もが挑戦することをはばかる権威の象徴だった。だが、「第3世代の核心」はそうではない。鄧小平は、1989年の天安門事件後、軍歴も権威もない江沢民を党中央の指導者に祭り上げるため「第3世代指導部の核心」に任じた。江沢民が核心に値する指導者であるかどうか以前に、天安門事件で大きく動揺した中国共産党の指導体制に求心力をもたせる必要があったからであろう。
習近平は、その江沢民から核心の座を剥奪し、自分が取って代わった。その核心の座を、また他の誰かが剥奪してもけっして不思議ではない。その意味で言えば、習近平の権力闘争はまだまだ続くことになる。
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。

