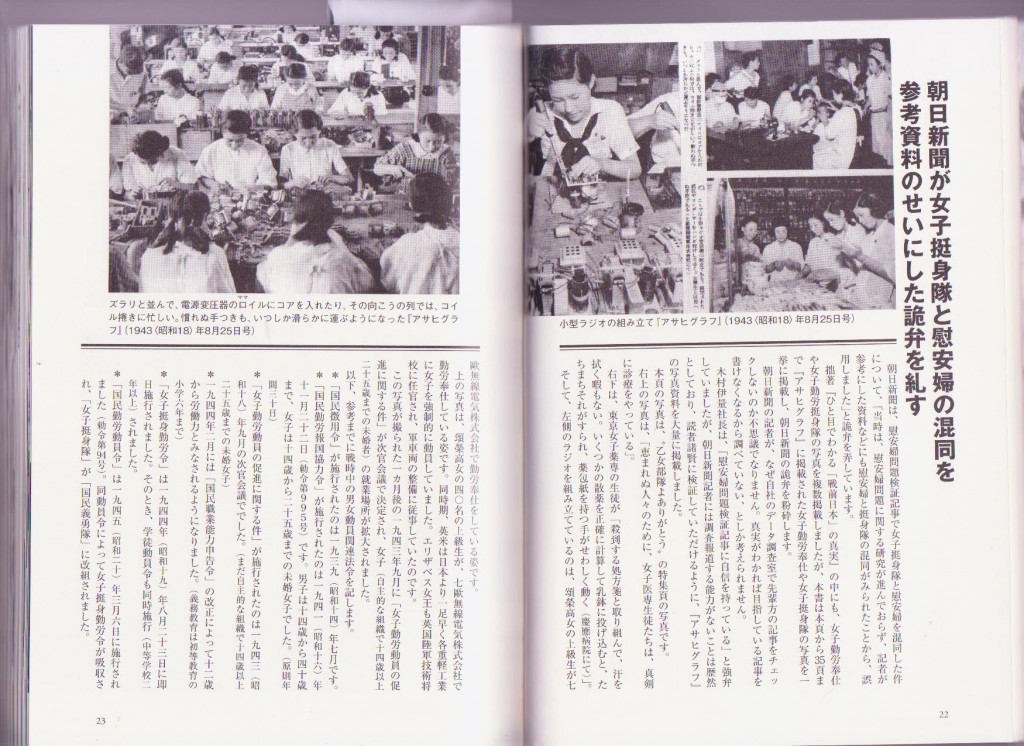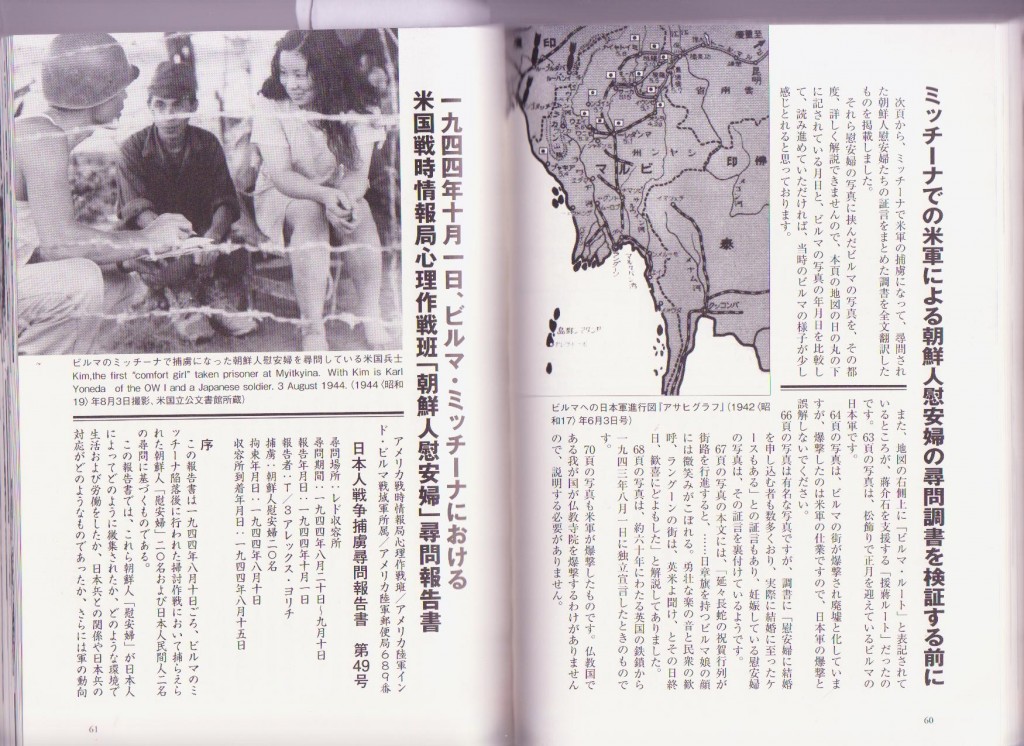ネットで知ったのですが、2月1日放映の「サンデースクランブル」(テレビ朝日系)の中で黒鉄ヒロシ氏が「悪い予測ではあるかなと思っていたんですけれど、ここまできてもね、まだ『イスラム国』という名前を使うのが勘違いのもとで…」と発言。 そして、黒鉄氏は、呼び替えの案として「アラブの山賊たち」と続いて発言。
ところが、その瞬間、突然画面と音声が切り替わり、報道フロアからのニュースになり、そこから約10分間、ISIL関連の臨時ニュースが続き、一瞬スタジオに戻るも、すぐにきょう1日の動きを振り返るVTRに切り替わったとのこと。
中国共産党を笑えません。中国でもNHK ワールド放送は見れますが、天安門事件等共産党にとって不都合な報道が始まると画面がまっ黒になって見れないようにします。そうするために電波をキャッチしてから2秒後に放映しているのだそうで。姑息ですね。それとTV朝日は同じことをしています。内部は共産党シンパが多いので発想が似るのかも。
これもネットの記事。1/31読売新聞によれば「イスラム過激派組織「イスラム国」とみられるグループによる日本人人質事件で、外務省が退避するよう求めているシリア国内に、朝日新聞の複数の記者が入っていたことが31日分かった」とのこと。共産党シンパの高遠達がイラクに入って捕まり、「自衛隊撤退」を叫んだようなことを考えているのでしょう。でも政府は身代金はビタ一文も出しません。捕まったら自力救済してください。彼らが嫌う自衛隊や日本政府のお世話にはなりたくないでしょうから。
また本日(2/3)の時事通信によれば「政府が過激組織「イスラム国」によって殺害されたとみられる後藤健二さんに対し、昨年9~10月に3回にわたってシリアへの渡航を見合わせるよう直接要請していたことが2日分かった。関係者によると、外務省職員が昨年9月下旬と同10月上旬に電話で、同月中旬には面会して渡航中止を求めたが、翻意させるには至らなかったという。」とのこと。これは「外務省に罪はありません」というアリバイ作りかも。朝日新聞と同じで戦後日本を悪くした張本人ですから。まあ、友人を助けるためとはいえ、危険地帯に行くのですから、ガイドが信用できるかどうかは良くよく調べた方が良かったでしょう。
本記事で菅原氏は「2つの目的を達するため、カサスベ中尉はまだ生きている」と読んでいるようですが、生きていれば時間をかけずに人質交換すると思います。他にも要求があれば別ですが。でも少なくとも生きている証拠を見せると思います。小生は亡くなっているので出せないと思っています。
記事
2月1日、過激派「イスラム国(以下IS)」が後藤健二さんを殺害したとする動画をインターネットに投稿した。後藤さんの救出のために尽力していた日本政府や、一刻も早い解放を願っていた日本国民にとって最悪の事態となった。
なぜこのタイミングでISが後藤さんを殺害したのか?ISは何をしたかったのか?
日本人は今回の事件をどのように捉えなければならないのか?一連の事件を振り返り、これらの疑問に対する私なりの分析をお伝えしたい。
ビデオ映像から見えるISの狙い
1月20日にイスラム国による日本人の人質2人の殺害を予告する映像が配信されて以来、日本政府はISに翻弄され続けた。2億ドルの身代金要求の期限にあたる72時間を過ぎてから1日以上が経過した25日に、インターネット上で湯川遥菜さんを殺害したとする写真を持つ後藤健二さんの音声付画像が流れ、続く26日には、ISが運営するラジオ局が湯川さんの殺害を認める内容を放送した。
25日に公開された画像では、当初の2億ドルの身代金要求は取り下げられ、新たに後藤さんの解放条件として、ヨルダンで死刑判決を受けて収監中のサジダ・リシャウィ容疑者の釈放が挙げられた。当初身代金を要求し、次にリシャウィ容疑者の釈放を要求してきたISの狙いは何だったのだろうか?
日本に対する初めての声明が発表されたのは1月20日であり、この時は過去に米国や英国人の人質を殺害する時にもたびたび登場したイギリスなまりの英語を話す「ジハーディ・ジョン」らしき男が、安倍首相と日本国民に対し、以下のように述べた。
「女性や子どもを殺し、イスラム教徒の家を破壊するために1億ドルを供出したので、この日本人の命は1億ドル」「イスラム国の拡大をとめるために新たに1億ドルを拠出したので、この日本人の命は1億ドル」と述べて、ISに対して2億ドル(約236億円)の身代金を72時間以内に支払うよう要求した。
すでに各種報道で伝えられているように、これは中東歴訪中だった安倍総理が1月17日に、日エジプト経済合同委員会でのスピーチで、「イラク、シリアの難民・避難民支援、トルコ、レバノンへの支援をするのは、ISIL(編集部注:IS、イスラム国の別称)がもたらす脅威を少しでも食い止めるためです。地道な人材開発、インフラ整備を含め、ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します」と述べていたことに反応したものであろう。
ビデオには、ジハーディ・ジョンが登場し、これまでに米英人を公開処刑してきたのと同じスタイルをとっており、ビデオにはISの公式プロダクトであることを示すロゴマークが付いていた。つまりISの公式声明であることが明白であった。
不自然だった「2番目のビデオ」
ISはこれまでも公式声明で発表した内容は全て実行してきており、公式声明で発表した以上は「言ったことはやる」原則を貫いてきた。それゆえ、72時間以内に身代金の支払いがない場合、もしくは支払うというメッセージが届かない場合、何らかの行動がとられる可能性があった。
多くのマスコミは72時間が経過したらすぐに何かが起こると考えたようだが、実際にはタイムリミットが過ぎた後に人質を処刑し、その模様を映した動画などを編集し、メッセージを練り、その後ISに都合の良いタイミングで公開するので、72時間が経過してから1日とちょっとのタイミングで次の画像が公開されたのであろう。2つ目の画像が出されたタイミングに特に不自然さはなかった。
しかしこの2番目のビデオは、これまでISが制作、発表してきたものとは、スタイルもデザインも異なる、はっきり言ってクオリティの低いものだった。
これは本物?いたずら?
それゆえこのビデオを初めて観た時の筆者の印象は「本物ではない、いたずらだ」というものだった。すでに多くの識者がコメントしているように、このビデオにはISの広報部が制作したことを示すロゴが付いていなかった。世界中の誰もが認知しているマークが付いていないということは、通常、ISが制作した正式なビデオではないことを意味する。そうでなければわざわざロゴマークなど付ける必要はない。素人でも簡単に高度なビデオが制作できる現代において、当然ISを装った画像や映像をその気になれば誰でもつくることができるからである。
それに静止画であるというのも極めて不自然だった。人質をとっている犯行グループが脅迫をする際には、自分たちが確かに人質をとっている正真正銘の犯行グループであることを示さなければそもそも脅しにならない。「今ここで生きている人質を押さえている」証拠を示す必要があるのだ。
ISは2番目のビデオでは静止画と共に後藤さん本人のものと思われる音声メッセージを付けてきた。またこのメッセージの中で、後藤さん本人に聞かなければ分からない奥さんの名前などの個人情報を含めることで、「生きている人質を押さえている」ということを示したのであろう。
これまでとビデオのスタイルが違うことやオフィシャルなロゴが付いていなかった理由は、おそらく「これはIS広報部の公式発表ではないので、そこで発表された内容をそのまま実行するとは限らない」、つまり「多少条件を変更したり、実施を遅らせる可能性がある」ということである。
言い換えれば、公式声明より一段階重みの低いメッセージという位置づけで発表したのではないか、と筆者は見ている。ISは相手の出方を見ながら新たな揺さぶりを考えようとしていたため、自分たちが自身の「公式声明」に縛られずに柔軟性を維持するためロゴを付けたり、付けないで発表するなどの使い分けをしたのではないかと思われる。
ただ、2番目のビデオ・メッセージが本当にISからの要求なのかどうか、信憑性に疑問が付けられたため、ISは25日に自分たちが運営するアルバヤンというラジオ局を通じて正式に湯川さんを殺害したことを認め、後藤さんの釈放と引き換えにヨルダンで拘束されているリシャウィ死刑囚を釈放することを要求し、日本政府に対してヨルダン政府に圧力をかけることを求めるメッセージを発信したのであろう。
なぜ要求内容が変わったのか?
では、なぜ当初2億ドルの身代金を要求しておきながら、リシャウィ死刑囚との交換に要求を変えてきたのだろうか? そもそも2億ドルという法外な金額は身代金の額としては尋常ではなく、非現実的な要求であったことは間違いない。ISはすでに後藤さんの家族にeメールで20億円の身代金要求を送っていたと伝えられている。その身代金要求が満たされずにいる中で、安倍総理が中東訪問で2億ドル支援を表明したので、「我々の敵に2億ドルも支払う用意があるのなら、連中ではなく俺たちに払え」という恫喝として身代金要求の最初のビデオを公開したのではないか。
ISはとてつもない外交戦略のプロだと勘違いしている人がいるようだが、彼らの本質は恐喝屋に過ぎない。相手が嫌がること、相手が困ることをとことん突き詰めて相手から搾りとれるものなら何でもとろうとする恐喝である。いかに相手を脅し、そこからとれるものをとるか、その点においては他に類をみない非道さと狡猾さを備えた残忍な集団である。
彼らが、手中に収めていた2人の日本人を使ってどう利益を得るかと考えていた矢先に、日本政府が自分たちの敵対勢力に2億ドルを支払うことが分かったので、「だったらその2億ドルを戴こう」と考えた。単なる盗人の発想である。もちろん2億ドルは法外な金額だが、その10分の1 だとしても、もともと後藤さんの家族に要求していた金額に相当するのだ。日本を揺さぶってみてとれるものならとってしまおう、そう考えたのではないか。
しかし、当然日本政府として身代金要求には応じられず、何らかの条件を提示することもできない。「後藤さんのご家族の下に送られたeメールを通じた直接のコミュニケーション・ラインがあるではないか」と思われる方もいるかもしれないが、これは水面下であくまで後藤さんのご家族が使う分にはいい。だが、日本政府が「○○の条件なら応じます」などと政府としての条件や要求に応じるかどうかのメッセージを、記録の残るメールなどで発信できるはずがない。ISがそうしたメッセージをインターネットで公開してしまう可能性だってあるからだ。
そこで政府としてはヨルダン、トルコやイラク政府やそれぞれの国々の部族や宗教関係者を通じてISとの交渉チャンネルを開こう、もしくはそうした間接的なチャンネルを通じてメッセージを伝えようとしたのだと思われる。
「カネはいい」「仲間は見捨てない」のメッセージ
ISの恫喝を受けた日本政府は、対策本部をヨルダンのアンマンに置き、現地での情報収集や交渉チャンネルの開拓に努めた。この動きをみたISは「ヨルダンと日本を絡めることで、両国を揺さぶりより多くの利益を得ることができる」と計算したのであろう。もともと第2段階ではヨルダンを絡めようと計画していた可能性もある。安倍総理は中東を歴訪した際、エジプトのカイロで例の「2億ドル支援」のスピーチをした後、ヨルダンを訪れ、そこでも同じような声明を発表し、ヨルダンには1億ドルの円借款供与も発表している。
恐喝屋ISの目には「日本からヨルダンに1億ドルが支払われる」という点だけが焼きついたのではないだろうか。調べてみると日本はヨルダンへの最大支援国の一つである。
当然日本はヨルダンに対して多大な影響力を持つ国だとISが単純に考えたとしても不思議ではない。そこで、日本にヨルダンに圧力をかけさせ、ヨルダンからとれる限りのものをとろうとしたのではないか。そもそも日本は交渉のチャンネルもなくコミュニケーションをとるのが難しいので、ヨルダンに窓口を一本化した方が物事を進めやすいと考えたのかもしれない。
それともう一つ、ISが最初のビデオで公然と身代金を要求したことにより、欧米メディアで「やはりISは劣勢に立たされて資金難に陥っているのではないか」との観測が広がった。ISはこうした見方を打ち消したいと考えたのではないだろうか。そこで「もう金は欲しくない」と後藤さんに言わせ、リシャウィ死刑囚の釈放を要求した。仲間の釈放を実現できれば、「仲間を見捨てない」というメッセージを与えることで、ISメンバーの士気は高まるし、イスラム過激派コミュニティ全体としての評価も上がるはずである。
なぜ、リシャウィ死刑囚と後藤さんの交換を要求したのか?
ではなぜISに拘束されているヨルダン人パイロットとリシャウィ死刑囚ではなく、後藤さんとリシャウィ死刑囚の交換をISは要求したのだろうか?
リシャウィ死刑囚は、ヨルダン政府にとってISに拘束されているパイロット、モアズ・カサスベ中尉を解放させるための切り札であり、ヨルダン政府が後藤さんの解放のためにリシャウィ死刑囚を釈放させるというのは極めて困難なことである。ISは非常に厳しい条件をヨルダン政府に突きつけたわけだが、彼らは後藤さんとカサスベ中尉という2つの「カード」を使って最大限とれるものをとるという発想で動いていたものと思われる。
日本はヨルダンに影響力があるのだから、その影響力を行使して圧力を加えれば、ヨルダン政府はリシャウィ死刑囚を釈放せざるを得ない。だからまずは後藤さんとの引き換えにリシャウィ死刑囚を取り戻す。残ったカサスベ中尉という「カード」を使ってヨルダン政府からさらに何かをとることができる。そうISは考えたのではないか。
もともと日本はヨルダンに支援を表明していたのだし、日本人解放のために貴重なリシャウィ死刑囚の釈放に応じたヨルダン政府に対し恩義に感じるはずだから、日本がさらなる支援をヨルダンに供与することも当然見込んでいただろう。そうなれば、ISはカサスベ中尉という「カード」の値段をさらに釣り上げ、さらなる仲間の釈放や日本からヨルダンに供与される援助金の一部を巻き上げることができるはずだと計算した可能性もある。またヨルダン政府に対し、米国への支援の停止も要求する、などということを考えていたのかもしれない。
しかし、当然ヨルダン政府はリシャウィ死刑囚という切り札を後藤さんの解放のためには使いたくない。ヨルダン国内でも、「リシャウィ死刑囚の釈放はカサスベ中尉の解放のために使うべきだ」という世論が一気に盛り上がり、ヨルダン政府に大きな行動の制約を与えることになった。
こうした動きをみたISは27日、再度、後藤さんと思われる男性の音声付画像声明を発表。24時間という制限時間を設定し、しかも後藤さん解放の障害になっているのは、ヨルダン政府がリシャウィ死刑囚の釈放を遅らせていることだとして、あくまで後藤さんとリシャウィ死刑囚の交換がISの条件なのだという点を強調した。
同時に日本政府にヨルダン政府に対して「あらゆる政治的圧力」をかけるよう命じ、これ以上リシャウィ死刑囚の釈放が遅れれば、まずカサスベ中尉を殺害し、続けて後藤さんも殺害するというメッセージを加えたのである。
ヨルダン政府にとってみれば、リシャウィ死刑囚を釈放しなければカサスベ中尉は殺害されるが、釈放してもカサスベ中尉が解放される保証はないという、到底受け入れ難い条件を突きつけられたのである。
ヨルダン政府側もリシャウィ死刑囚を移動させたり、釈放に応じる様なそぶりを見せながらも、カサスベ中尉の解放を優先させる方針を明確にして、ISと水面下で交渉を続けていた。ヨルダン政府はリシャウィ死刑囚とカサスベ中尉の交換のための条件についてしきりにIS側に働きかけをしたはずだが、ISとしては後藤さんとカサスベ中尉という2つの「カード」を順番に使って最大限の利益を得ようという作戦を立てていたので、「後藤さんとリシャウィ死刑囚の交換なのだ」という彼らの条件を重ねて強調する必要に迫られたのだろう。
28日の時点でISが設定した「24時間」の期限は過ぎたが、29日に後藤さんを名乗る男性による新たな声明が出され、「現地時間の29日日没までにトルコ国境で後藤さんとリシャウィ死刑囚の交換に応じる準備ができないのであればカサスベ中尉を殺害する」というメッセージが発信された。しかもイラク北部モスル時間の日没であるという点まで明確に示された。さらに駄目押しのように後藤さんの妻にロイター通信を通じて、「後藤さん解放に残された時間は少なく」「ヨルダン政府と日本政府に命運が委ねられている」ことを伝えさせたのであろう。
3回も繰り返した意味
ISは3回も彼らの要求する条件、すなわち「後藤さんとリシャウィ死刑囚の交換」という条件を繰り返し伝えた。これまでISが発表した映像は、20日の1回目のもの以外はすべてオフィシャル・ロゴのついていないメッセージだったから、一定の柔軟性を持たせた要求だったのだが、自分たちの要求の柱であるこの条件だけは「間違えるなよ」という意味で、3回もの機会を使って繰り返したのではないだろうか。
また、ここまで期限を延ばしたのは、リシャウィ死刑囚を解放させ、さらにカサスベ中尉を使って新たな利益を獲得するという最大限の利益をとることに、ISはギリギリまで拘ったのではないか。ISとしては2 つの「カード」を使ってとりたいものがとれなければ、最終的には人質を殺害して世界に恐怖を与え、「自分たちの要求を飲まなければこのような結末になるのだ」ということを示すことで宣伝として使うという方法をこれまでもとってきた。
今回も、ヨルダン政府がISの提示した条件を飲まなかったことで、最終的な手段、すなわち恐怖の宣伝に出たのだと考えられる。
恐喝屋「イスラム国」の交渉術
ISは、このように人の命を「カード」として何のためらいもなく使う極悪非道な集団である。彼らは米国人ジャーナリスト、ジェームズ・フォーリー氏を拘束していた時も、まずは身代金を要求し、米国が身代金要求に一切応じないことが分かると、ビデオで空爆作戦を中止するという政治的な要求を掲げ、その裏では米国政府が拘束しているISの仲間の釈放という「捕虜交換」を要求し、最後にそれも叶わないと判断した時点でフォーリー氏を殺害し、さらに同氏の遺体を家族に売ろうとまでした。利用できるものは徹底的にすべて利用し、金や彼らの要求する何かと交換して利益を得ることを貪欲に求めてくる連中である。
彼らは相手を脅し、恐怖心を与えることで、自分たちの交渉力を強めている。今回万が一ヨルダンが提示した条件にISが応じてカサスベ中尉とリシャウィ死刑囚の交換に応じたとすれば、将来同様な人質交渉においてISの交渉力は決定的に弱まるであろう。
そもそも交渉とは、双方が相手から欲しいものを持っている、すなわち双方が相手に弱みを握られている場合に、双方が歩み寄って妥協点を探ろうという行為である。通常の身代金誘拐の場合には、誘拐犯は人質と交換に身代金を得たいと思っている。それが唯一の目的である。人質を解放させたい側は、誘拐犯が身代金目当てであることが分かっているので、「身代金が欲しければこうしろ」という条件を付けることができ、「人質には絶対に危害を加えるな」とか、「もう少し身代金額を減らせ」という点まで含めて一定の交渉が可能となる。誘拐犯にとっても、人質を殺してしまえば一銭にもならず、目的を達成できないことになるからだ。
しかしISの場合には、最終的には人質を殺害して世界に恐怖を与える宣伝に使えばいいため、圧倒的に交渉における立場が強い。人質をとられている側がISの弱みを握っているわけではないので、ISに対して条件を提示することが事実上できなくなるからである。
今回のケースで言えば、ヨルダン政府はカサスベ中尉をどうしても取り戻したいが、ISにとってのリシャウィ死刑囚は、もちろん釈放を実現できれば望ましいがヨルダン側が同中尉を取り戻したいと思うほど、是が非でも取り戻したい対象というわけではなかったのだろう。
そうであれば、ヨルダン政府が「リシャウィ死刑囚の釈放」の条件としてカサスベ中尉の解放という彼らの条件を提示しても、ISとしてはその条件を飲んで妥協する必要はなかったはずである。逆に相手の条件を飲むという弱さを見せてしまえば、ISは将来の交渉力も落とすことになり大きなマイナスである。
とは言え、ISはそれでも当初の期限を2回も引き延ばしたことから、リシャウィ死刑囚の釈放も実現させたいと思っていたのであろう。しかしこれ以上言ったことをやらずに期限をさらに伸ばしたり、また新たな条件を提示するならば、今後ISが発信する脅しのメッセージの効果は低くなる。「やると公言したけれどやらないではないか」と思われれば、恐喝屋としてはおしまいであり、次の恐喝ができなくなるのだ。
「弱体化」「内部分裂」説を一掃
実際、筆者も「もしISがここでさらに条件を変えたり期限を延長してきたら、ISは組織として相当弱体化しており、内部分裂が進行していることの証左である」と分析したであろう。筆者でなく、世界中のISをウォッチしている分析家が、そのような判断をしたと思われる。そのような点からすれば、ISは「公言したことを実行した」ことで、弱体化や内部分裂が噂される中で、自分たちの組織がいまだに健在で強いものであることを、世界に示したと言えるであろう。
それでも疑問が残る。ヨルダン人パイロット、カサスベ中尉はどうなったのかという点である。ISは声明の中で、リシャウィ死刑囚が釈放されなければ、後藤さんの前にカサスベ中尉を殺害すると予告していた。もしこの言葉通りならば、公開していないだけで、すでにカサスベ中尉も殺害されているということになる。時間をおいて新たなビデオが公開される可能性は否定できない。
しかし、これまでもみてきた通り、ISは後藤さん、カサスベ中尉という2つの「カード」を使い、リシャウィ死刑囚と何か別のものという最低2つの「もの」を獲得することを狙っていた。リシャウィ死刑囚の釈放を実現したいとISが考えていたであろうことは、彼らが期限を2回引き延ばしたことからも推測できる。
もし後藤さんの前にカサスベ中尉も殺害していたとするならば、ISは、人質を使って得たいと狙っていたものは得られず、最終手段としての「宣伝効果」しか得られないことになる。もし宣伝効果以外にも何か実のある収穫物を得たいとIS側が考えており、やはりリシャウィ死刑囚を取り戻したいと考えているのだとすれば、すでに後藤さん殺害で「宣伝効果」という目的を達成したと見なして、カサスベ中尉とリシャウィ死刑囚の交換を進めるかもしれない。そもそもこれまでの要求はあくまでオフィシャル・ロゴの付いていない非公式の声明であり、条件を変える柔軟性を持たせてあるのだから。