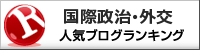4/22The Gateway Pundit<BREAKING: Gorsuch and Roberts Side with Liberal Justices — Illegal Alien Can Ignore Deportation Deadline If It Falls on a Weekend or Holiday=速報:ゴーサッチ判事とロバーツ判事、リベラル派判事に同調 — 不法移民は国外退去期限が週末や祝日であれば無視できる>
司法が立法行為(法解釈を広げることによる法の創造、或いは法解釈の誤解)をするのは三権分立の侵害では?
移民法執行へのさらなる打撃として、最高裁判所は本日、モンサルボ・ベラスケス対ボンディ事件で、連邦移民法に基づいて自主出国を許可された不法移民は、裁判所命令による出国期限が週末または法定休日に当たれば期限を過ぎても米国に滞在できるとの判決を5対4で認めた。
ニール・ゴーサッチ判事が多数意見を執筆し、ロバーツ、ソトマイヨール、ケイガン、ジャクソン各判事が賛同し、法の支配ではなく強制送還対象者の都合に合わせて「60日間」の自主的出国期間の意味を事実上書き換えた。
この事件の中心人物は、約20年前に米国に不法入国し、60日以内に出国するよう命じられたメキシコ国籍のウーゴ・モンサルボ・ベラスケス氏だ。
彼の出国期限は土曜日だったが、彼は出国する代わりに翌週の月曜日に事案を再考する申し立てを行った。
移民審査委員会と第10巡回控訴裁判所は、いずれも彼が期限を過ぎたと判断した。しかし、最高裁判所はこれを覆し、かつては厳格だった移民期限に曖昧さをもたらした。
クラレンス・トーマス判事は、アリト判事、カバノー判事、バレット判事とともに、強い反対意見を述べ、多数派が法律の明確な条項を超えて適用範囲を広げていると激しく非難し、「60日というのは60日を意味するのであって、外国人がいつでも法の網を逃れられるわけではない」と主張した。
「本件の本質的な問題、すなわち請願者が2021年10月12日から『60日』以内に米国を出国したかどうかは明白だ」とアリト判事は判決文に記した。
2021年10月12日から60日目は、2021年12月11日土曜日でした。そして、請願者はその土曜日までに国を出国しませんでした。…[2日間の延長]には正当な理由はありません。」
彼は続けて、「2021年10月12日から60日目は、2021年12月11日土曜日でした。そして、請願者はその土曜日までに国を出国しませんでした。土曜日は単なる曜日であり、請願者がその日もしくはそれ以前に国を出国できなかった理由は存在しません。請願者は、母国メキシコへの道路が閉鎖されていたと信じる理由を全く示しておらず、私もそのような理由を知りません。そのため、彼は車やバスで国境を越えることができたはずです。また、メキシコや彼を受け入れてくれる他の国へ飛行機で行くこともできたはずです。」と述べた。
「それにもかかわらず、裁判所は、自主退去期限の最終日がたまたま週末に当たったため、彼には2日間の延長を受ける権利があったと判断しました。この決定には正当性はありません」と彼は付け加えた。
「関連する法定条項、合衆国法典第8編第1229c条(b)(2)は期限を定めており、期限をどのように計算したとしても、1日かそこらで期限を過ぎてしまう人は必ず存在する。…請願者への同情は、裁判所の決定を正当化するものではない。」
この判決は1950年代に遡る規制解釈に基づいており、大多数は期限を週末や休日を超えて延長すべきだと主張していた。
「議会が『長年にわたる行政解釈』を背景に新しい法律を採択する場合、最高裁は一般的に、新しい規定が従前の規定と調和して機能すると推定する」とゴーサッチ判事は判決文に記した。
少なくとも1950年代以降、移民法では、期限を計算する際に「日」という用語に特別な意味を持たせ、期限が日曜日と法定の祝日(およびそれ以降の土曜日)のいずれかに当たる場合は、これらの日を除外することを定めています。議会は、この一貫した規制の背景を踏まえ、1996年不法移民改革および移民責任法(IIRIRA)第304条の一部として、第1229c条(b)(2)を制定しました。
「政府は、IIRIRAの同じ条項に定められている他の期限、例えば再審理または再考の申立ての期限もこの規則の対象となることを認めている。特に、これらの規定が同法の同じ条項で同時に制定された場合、同一の「日数」という用語には、第304条全体を通じて同一の意味が与えられるべきである。」
しかし批評家は、最高裁が行政上の申請規則と、強制退去を遅らせるのではなく、早めることを意図した法的に義務付けられた期限を混同していると指摘している。
この判決の影響は広範囲に及ぶ。今後、期限を操作したり、技術的な理由をつけて異議を唱えたりする無数の移民案件が起こり、既に逼迫している移民執行システムがさらに弱体化する可能性がある。


https://x.com/i/status/1914492069294354779


(翻訳)鍾祖康 22時間
リー・シェンロン(李顯龍)首相の妻でシンガポール国営石油会社テマセクの元代表である何晶はシンガポールで著名な人物だが、実はシンガポール在住のポーランド人評論家(マイケル・ペトレイアス)がフェイスブックで書いた記事を転載した。その記事は、習近平主席をギャングと罵倒し、彼にいじめられているASEANの小国に恥も外聞もなく助けを求めていると非難していた。この記事は論理的で、よく構成されており、習近平を揶揄することに全力を尽くしている。何晶がこの記事を転載したところ、何百ものコメントが寄せられ、そのほとんど (どうやらほとんどがシンガポール人からのコメントのようだ) は、ギャングの注目を集めないように投稿を削除するよう何晶に懇願したが、何晶は今日に至るまで動いていない。何晶の目には習近平はただのひどい愚か者でしかないようで、何晶がようやくそうする勇気と見識を得たという事実は、国民が世界についてより認識するようになり、彼女が泥に染まっていない模範であることを示すものなのかもしれない。
4/22Rasmussen Reports<Earth Day: Just 33% Think It’s Helping=アースデー:効果があると考える人はわずか33%>
今日はアースデーですが、地球環境に変化をもたらすと考える米国人は3分の1にすぎません。
ラスムセン・レポートによる最新の全国電話・オンライン調査によると、米国人の成人の33%がアースデーが米国人の環境意識の向上に役立っていると考えている一方で、38%は役立っていないと回答し、29%はわからないと回答しました。アースデーが環境意識の向上に役立っていると考える人の数は、 2021年の38%から減少し、 2011年 に初めてこの質問を行って以来、最低となりました。


4/23阿波羅新聞網<川普祭出史上最严新规!小弟集体围剿习帮主=トランプは、史上最も厳しい新規制を導入!小国たちは集団で習ボスを包囲・弾圧している。>
中国の輸出を阻止せよ!米国は史上最も厳しい原産地検証を開始し、東南アジアのいくつかの国は緊急に米側に立つ。
米国は、東南アジア諸国を経由して再輸出することで脱税する中国製品を取り締まるため、新たな原産地検証システムを導入した。ベトナム、シンガポール、タイは監視メカニズムを構築し、原産地証明書の審査を強化するための行動を採りだした。中国商務省は緊急警告を発し、輸出企業に対し、東南アジア諸国の引き締め政策に警戒し、原産地偽造による罰金や貿易制限を避けるよう呼び掛け、米中貿易摩擦の中、世界的なサプライチェーン監視が強化されていることを強調した。
- 米国は相互関税を実施した後、第三国を経由する積み替えに対抗するために原産地確認の新たなシステムを有効化した。
WHは、第三国への積み替えに対抗するため、次のような一連の措置を計画していると報じられている:
- 世界的な貨物追跡システムを確立する。
- 再輸出貿易に対する「連帯式処罰」の実施。
- 棚上げされていた貿易執行強化法案が、この機会に再提出される可能性がある。
この法案の規定は史上最も厳しいものであり、次のような内容が含まれている。
- 「関税詐欺」を連邦法上の重罪とし、企業幹部には最長20年の懲役刑を科す。
- 輸入業者は、ネジ1本あたりの原産地や仕向地も含めた、商品のサプライチェーン全体に関するデータを提出する必要がある。これによりコンプライアンスコストが大幅に増加し、コンテナ 1 個あたりの文書認証料金が 5,000 米ドルを超える可能性がある。
- 連帯機制:企業が再輸出貿易に従事していることが判明した場合、その国の関連会社すべてから米国への輸出を直接停止することができる。
- 高額の罰金:脱税額の300%+10年間の企業利益を追徴。
- シンガポールは、他国の企業がシンガポールとのつながりを利用して他国の輸出規制を回避することを容認しないと主張。
- ベトナムは中国製品の管理を強化するため、「中国製品再輸出監視システム」を設立することを約束。
- タイ商務省対外貿易局は、貿易迂回行為に対抗するため、42品目の原産地証明書の審査を強化すると発表。
- 中国商務省は警告を発した:多くの東南アジア諸国は原産地証明書の偽造を厳しく調査する。
抜け駆けが見つかったら、見せしめで厳罰を食らわすのが良い。
https://www.aboluowang.com/2025/0423/2208701.html
4/23阿波羅新聞網<习近平国师:川普还有“2张王牌”未出手=習近平の国師:トランプにはまだ「使われていない切り札が2枚ある」>トランプ米大統領は中国に対し関税戦争を開始し、中国は「最後まで付き合う」と強調し、両大国間の競争は激化している。中国の国際問題専門家で中国人民大学国際関係学院教授の金燦栄は17日、トランプにはまだ使われていない「二枚の切り札」があり、中国株を米国資本市場から排除し、米国内の中国資産に課税する手に対し、反撃の準備をしなければならないと書いた。
記事によれば、トランプは今や関税戦争を戦う決意をしており、それは短期間ですぐに収まることはないだろうという。一方で、米国は多額の負債を抱えており、バイデン政権時代には政府支出が巨額となり、財政基盤はほぼ空っぽになってしまった。トランプがバイデンを嫌うのも不思議ではない。こうした状況下で、トランプは歳入を増やし、支出を減らそうとしている。彼は関税を通じて数千億ドルを徴収し、「政府効率化省」に頼って経費の一部を削減することで支出を削減したいと考えている。
さらに、トランプ大統領は製造業の米国回帰を促し、戦略レベルで中国を孤立させ、打ち負かそうとしている。こうした動機を踏まえると、トランプの関税戦争は国内外で多くの障害に遭遇しているにもかかわらず、依然として前進を主張し、今後も事態をエスカレートさせ続ける可能性が高い。
記事は、米国が今後中国に対してさまざまな行動を取る可能性があると指摘している。第一に、課税対象範囲をより多くの分野に拡大する;第二に、米国資本市場から中国株を排除する;第三に、米国内の中国を含む一部の国の資産に税金を課すことである。資産の直接的な没収は過激すぎるが、課税は比較的実行可能である;第四に、米国企業による中国への投資をさらに制限する。
このうち、2番目と3番目の点は中国に比較的大きな影響を与える。スコット・ベセント米財務長官は最近のメディアのインタビューで、「米国で中国株が上場廃止になる可能性は排除できない」と述べた。これは冗談ではない。しかし、この問題は米国に大きすぎる影響を与えるため、実際には実施されないだろうと見ている専門家もいる。
トランプだから何が起きるかは分からない。
https://www.aboluowang.com/2025/0423/2208689.html
4/23阿波羅新聞網<贝森特预计美中关税战将降温 但过程艰难=ベセントは、米中関税戦争は沈静化すると予想するが、その過程は困難>米メディアは火曜日(4/22)、米財務長官が投資家との非公開会合で、米中関税戦争は「近い将来に沈静化する」と予想されると語ったと報じた。
スコット・ベセント財務長官は火曜日、ワシントンDCでJPモルガン・チェースが主催した個人投資家サミットに出席した。同氏はワシントンと北京の交渉はまだ始まっていないが、交渉プロセスは「困難」になると述べた。このイベントは一般やメディアには公開されなかった。
ブルームバーグとCNBCは事情に詳しい関係者を引用してこの件を報じた。
CNBCは事情に詳しい情報筋の話として、財務長官が「北京との次のステップは、現在の現状(関税水準)が持続可能だと誰も考えていないということだ」と述べたと報じた。
ベセントの発言が初めて報じられた後、米国株は前日の売りから脱し、正午に急騰した。午後12時28分時点でS&P500は2.9%上昇した。
事情に詳しい関係者によると、ベセントは、経済大国間の緊張緩和の見通しは「世界と市場にとって安心材料となるはずだ」との考えを示した。
米財務長官は、国際通貨基金(IMF)と世界銀行の春季会合でこの発言をした。この会合では財務相や中央銀行総裁らが集まり、米国の貿易戦争の影響を評価する。
ベセントは、世界の二大経済大国(米国と中国)が実際に貿易禁輸措置を講じていると指摘した。
同氏は、中国との交渉は「困難」かもしれないが、双方とも「現状は持続不可能」であることを認識していると指摘した。
中共とはずっと我慢比べしてほしい。
https://www.aboluowang.com/2025/0423/2208833.html
4/23阿波羅新聞網<被日官方认证危险国家! 北京批恶意炒作 却被“反日夏令营”打脸=日本政府が公式に危険な国に認定!北京は悪質な誇大宣伝だと批判したが、「反日サマーキャンプ」で反撃された>報道によると、日本外務省は最近、公式ウェブサイトで「安全に関する注意喚起」を出し、中国の社会治安が劣悪であることを指摘し、日本の学校に対し、中国への修学旅行の実施を決定する前に安全を十分に確認するよう求めている。中国側は、自国は常に開放的で寛容かつ安全な国であると述べ、日本に対して厳粛な抗議を行った。しかし、「中国のある場所で開催された反日サマーキャンプ」を映した動画が流出し、すぐに中国側の主張を打ち消した。

中国外務省の郭嘉昆報道官は定例記者会見で、「日本の警戒警報の根拠は分からない。この動きは中国の安全上のリスクを悪意を持って誇張するものであり、政治的な意図がありありである。中国側はこれに強い不満と断固たる反対を表明し、日本側に厳重な抗議を行った」と述べた。
しかし、Xの「のらいぬ」というアカウントが、中国のある場所で「反日サマーキャンプ」が行われている様子を映した動画を投稿した。大人も子どもも抗日武装勢力の八路軍の役割を演じ、日本軍に占領された県城を攻撃した。これにより、中国の声明はすぐに反証され、中国は「オープンで寛容、そして安全」であるという偽りの仮面が剥がされた。
中国人は嘘つきと言うのが分かる。岩屋は外相たる資格がない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1f7329b863f12cbc4383e8f27d2a24b31974846c
https://www.aboluowang.com/2025/0423/2208626.html

何清漣 @HeQinglian 1時間
遅ればせながらの覚醒:汪海林(著名な脚本家、代表作に『銅雀台』『楚漢伝奇』など)が昨日10時48分に投稿:
【機会があるので体系的に話しする。 1990年代以降、西側諸国は中国におけるLGBT活動をどのように体系的に計画し、促進し、奨励してきたか。私は文芸界に身を置いており、比較的早い時期からLGBT活動に触れていた。当時は進歩的かつ文明的だと考えられていた。知識人は寛容さ、理解力、適応力を示すことに積極的だった。
もっと見る
何清漣 @HeQinglian 4時間
米国の複数の主要メディアは1時間前から次のように報じている:ベセント財務長官は中国との関税戦争は持続不可能であり、近い将来に緩和されると期待していると述べた。
bloomberg.comより
何清漣 @HeQinglian 2時間
ブルームバーグが最初に報じたこのニュースについて、もっと詳しく知りたい。ロイター通信によると、ベセントはJPモルガン・チェース(JPM.N)主催の非公開イベントでこの発言をした。中国との関税をめぐる対立は持続不可能であり、状況は緩和しつつあり、協議はまだ始まっていないものの合意は可能だと付け加えた。
もっと見る
何清漣 @HeQinglian 8 時間
米国人は苦しんでいる。民主党に投票するのは、半分狂っていて半分愚かな人たちで苛まれている。トランプに投票したのは、元々最初の任期のときと同じように経済運営を行えると期待されていたから。難易度は1.0よりはるかに大きいが、4月の最初の1か月間で関税戦争が最初の10日間で3回変化し、株式、債券、通貨のトリプル安を2回経験するとは予想していなかった。
引用
L JM @zhixiangziyou 16時間
4人の民主党員が、MS-13テロ組織のメンバーで妻を虐待した容疑者の釈放を求めるためにエルサルバドルに到着したばかりだ。
ロバート・ガルシア下院議員(カリフォルニア州)
マックスウェル・アレハンドロ・フロスト下院議員(フロリダ州)
ヤサミン・アンサリ下院議員(アリゾナ州)
マキシン・デクスター下院議員(オレゴン州) x.com/libsoftiktok/s…
もっと見る

何清漣 @HeQinglian 1時間
トランプ米大統領は「我々は中国に対して非常に友好的である」と述べた。 https://thehill.com/homenews/administration/5261948-trump-optimistic-china-trade/
凡て派は確認・検証をお願いする。多くの米国メディアがこれを広めている。
引用
BRICSニュース @BRICSinfo 3時間
速報:🇺🇸🇨🇳 トランプ米大統領は中国に対して「我々は非常に優しくするつもりだ」と述べた。
何清漣 @HeQinglian 1時間
米国ではトランプのルールなき関税戦争に対して強い反対がある。凡て派と反共派がコメント欄を汚すのが嫌なので、アップロードしなかった。
多くの中小企業は原材料のほとんどが中国から来ているため、これに反対している。米国で原材料を生産している数社は反対せず、むしろ事業に満足しているが、これらの企業は極めて小規模であり、生産を拡大することさえ容易ではない。この2種類の企業経営者は基本的にトランプ支持者である。
もっと見る

何清漣 @HeQinglian 19 分
米国と合意を目指す日本、枠組み合意に署名したインド、その他署名準備を進めている国々は、現状では日和見主義者であり、米中関税協定が署名されてから実際の行動に出るのではないかと強く疑っている。
何清漣 @HeQinglian 33 分
昨日は解雇すると言い、今日は解雇しないつもりだと。資本市場が安定した後、再び問題を起こさないでください。
引用
日経中国語ウェブサイト @rijingzhongwen 51分
【トランプはFRB議長解任否定、円は急落】トランプ米大統領は4/22、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長を「解任する予定はない」と述べた。円の対ドル相場は急落し、一時1ドル=143円台前半まで下落した。前日午後5時と比べると、円はドルに対して3円近く下落した・・・。
https://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/stockforex/58644-2025-04-23-08-53-12.html
もっと見る
何清漣 @HeQinglian 35 分
「145%というのは非常に高い数字だが、そこまで高くはならない。かなり下がるが、ゼロにはならない。かつてはゼロだったのですから。」
ここに原文があるので、自分で読んでみてください。
引用
麗園 @miyugreer 44分
返信先:@HeQinglian に
トランプの当初の発言は、ずっと145%だったのでは。
何清漣 @HeQinglian 48 分
フォックス:トランプ大統領は中国に対する関税を引き下げると述べた。145%は高すぎで、下がるが、ゼロにはならない。
引用
メガトロン @Megatron_ron 2時間
速報:
🇺🇲🇨🇳 トランプが対中関税の引き下げを発表:
「145%というのは非常に高い数字だが、そこまで高くはならない。かなり下がるが、ゼロにはならない。かつてはゼロだったのですから。」
もっと見る
トランプの対中関税緩和の話は、上述の中国語記事を読めば、リップサービスだけなのでは。
神津氏の記事で、やっと米側の立場に立って経済を見た、真面な議論が出てきたという感じがします。左翼グローバリズムに汚染されたオールド・メデイアは殆どトランプ非難ばかり。国民を守ることがどうしていけないのか、彼らの考えが分からない。米国は双子の赤字(財政赤字+貿易赤字)にずっと悩んできた。財政赤字はDOGEの無駄や詐欺摘出(議会の予算化が必要)で削減し、貿易赤字は関税で削減するというのは米側に立って見れば、至極真っ当な話。今までそれに甘えてきた国やそれを利用してきた国(中共の軍拡)がやり方の見直しを迫られるのは当然の話。
氏は「 得意・不得意で分業を進めていく考え方は、経済学ではしばしば比較優位の原則とも呼ばれる。それは、ヒト・モノ・カネの生産要素が低コストで部門間を移動できることを暗黙の前提としている。
現実問題としては、比較優位の原則の貫徹は決して低コストではできないし、さらにそのコストには金銭に換算できないところもある。」と説明しているように、理論と現実は違う部分が出て来ると。そもそもリカードの比較優位説やアダムスミスの見えざる手は重商主義の英国の経済政策を、学問の分野で支援するためと渡辺惣樹氏が書いていたような気がします。
日本は固定観念に染まったままでなく、神津氏の言うように、トランプ関税は機会でもあり、新鮮な思考で未来に挑戦しないといけない。貿易問題だけでなく、防衛問題についても、同盟国とじっくり話し合って、日本の自立化を図っていくべき。
記事

トランプ政権が打ち出す関税政策は世界経済に打撃を与えると考えられている(写真:ロイター/アフロ)
トランプ米大統領による一連の関税政策の発表で、金融市場は日々大きく動いている。最終的に何をしたいのかが良く分からず、金融市場の評価が振れている面もある。しかし、「そもそも論」として、この政権は自国にとって何が良かれと考え、何をしようとしているのか。トランプ政権は、どういう意味で米国をもう一度偉大にしようとしているのか。元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。(JBpress編集部)
(神津 多可思:日本証券アナリスト協会専務理事)
これまで進んできた分断を逆回転させる
トランプ政権の関税政策は、自由貿易を破壊するものだと言われる。だから、グローバル経済の成長率は低下するとみられている。
自由貿易でグローバル経済の成長率が高まるのは、それぞれの国の経済が得意な分野に特化していくことで、全体としてみて経済活動の効率性が改善し、したがってより高い生産性が実現できるからだと言える。
しかしこれは、一つひとつの国の経済を、全体としてみた場合の評価だ。「得意な分野に特化する」と言えば、聞こえは良いが、その反対側には不得意な分野がある。その不得意な分野を諦めることで、経済全体としてはより高い成長できるかもしれないが、諦められた分野で暮らしてきた人々はどうなるのか。
米国の錆び付いたベルト(Rust Belt)と呼ばれる五大湖周辺の地域の製造業が、その諦められた分野の一例であり、そこで働く人々の不満をも背景に、トランプ大統領が再選された。
他方、米国経済の現在の強みの1つは、明らかにデジタルサービスの分野にある。プラットフォーマーと呼ばれるデジタル企業は、ほとんどが米国から生まれており、欧州も日本もそれに追い付けていない。
デジタルサービスの供給に関連する分野での急拡大が、米国経済全体としての高成長を実現してきたが、その陰には実質所得が増えない労働者がいて、貧富の差は拡大し、社会の分断が進んでいる。トランプ政権が明確にしているのは、米国としては不得意分野になった産業を重視し、これまで進んできた分断を逆回転させるという意思なのではないだろうか。
成功・不成功のコントラストを弱めたい
以上のように、今日、トランプ政権が全方位的に貿易収支を均衡させようとしているのは、これまでの各経済の得意・不得意に従って分業化するという動きを逆回転させるものだ。そもそも、米国経済が強いデジタルサービスは、貿易収支の話ではなく、サービス収支に入ってくるので、「それは横に置いて」ということになる。
広範な関税により、国際比較の中では米国が不得意な分野の国内での経済活動が保護され、そのウェイトが拡大することになる。したがって、これまで起こらなかったイノベーションが急に起こるようなことがない限り、米国経済全体の生産性の改善度合いは遅くなる。
これは、詰まるところ、米国経済の潜在成長率が低下するということだ。それでも、これまで諦めてきた製造業に政府が手を差し伸べることにはなる。
マクロでみた成長率が低下しても良いから、国民経済における成功・不成功のコントラストを弱めたい——。それが現在トランプ政権の意図していることだとしたら、それはそれで他国が「愚行」といった表現で非難するような話ではないのではないか。
要するに、これまでの日本のような経済に少し米国を近付けたいということだとしたら、日本としても何を根拠におかしいと反論するのだろうか。

トランプ大統領らとの会談後、手渡された「MAGA」帽子をかぶる赤沢経済再生相(写真提供:Molly Riley/White House/ZUMA Press/アフロ)
自給自足化が可能な国・不可能な国
ただし、米国と日本が決定的に違うのは、天然資源の賦与や耕作可能な国土の広さである。
米国のように、エネルギー自給率、食料自給率が高い国は、製造業分野で少し自給自足化が進んで成長率が低下しても、経済全体として困る度合いは、日本に比べかなり低いだろう。
一般的に言って、天然資源に乏しく、人口も少ない経済にとって、自由貿易の維持は、経済を繫栄させる上で欠かせない。米国のように、すでに繫栄した国と、そこにまで至っていない新興国では事情は違う。
したがって、米国がモノの生産について自給自足化しようとすることが、よく考えるとあまり非難できないとしても、これまで米国への輸出で経済を発展させてきた国にとっては大問題となる。
米国からすれば、それは米国内の分断というコストの上に生み出された貿易相手国の発展なので、割り負け感が強いと言われてしまえば、何と言い返して良いのか困るところがある。実際、現在トランプ大統領は、この「割り負け感」のメッセージを色々なかたちで発している。
これまでのグローバル化は速過ぎたのか
今日、グローバル経済がこうした状況に陥っているのは、そもそも、これまでのグローバル化のスピードが速過ぎたからなのかもしれない。
1990年代から始まり今日に至るグローバル化は、先進国、新興国を問わず、その経済環境を大きく変えた。そこには光の部分もあるが、影の部分もある。どの国も、程度は違うがそのコントラストどうするかという問題を抱えている。
日本の場合は、米国には追い付けず、中国には追い越され、というような感覚の中で、もっと成長率を高めてかつての栄光を取り戻さなくてはといったところもある。
しかし、先頭を行く米国で今回のような一種の歯車の逆回転が起こっているということは、必ずしも日本が結果的に実現してきたバランスも、全く駄目ではなかったのかもしれない。
得意・不得意で分業を進めていく考え方は、経済学ではしばしば比較優位の原則とも呼ばれる。それは、ヒト・モノ・カネの生産要素が低コストで部門間を移動できることを暗黙の前提としている。
現実問題としては、比較優位の原則の貫徹は決して低コストではできないし、さらにそのコストには金銭に換算できないところもある。
長い目でみて経営を続けられない企業を存続させることは、結果的にマクロ的な成長力を低下させるが、しかしそこにある生活を守ることでもある。比較優位の光の部分と、比較劣位の影の部分をどうバランスさせていくかは、結局、その社会の問題であり、予め変化の最適スピードが分かる訳ではない。
トランプショックをどう受け止めるか
日本の場合は、このグローバル化を、バブルの崩壊とリーマンショックという大きなストレスと並行して経験したので、どうしても現状維持の感覚が強くなり過ぎたように思う。
影の部分を意識するにしても、周囲の経済環境が急速に変わっていくのだから、変化自体はしないといけない。変わりたくはないが、もっと高い成長はしたいという、ないものねだりがあったような気がしてならない。
日本では、いまだに経済の「回復」という言葉も聞かれるが、それも、現在の環境における日本経済の実力、経済成長の巡航速度を見誤った表現なのではないか。そういう感覚が残る下での今回のトランプショックなので、何らかの対策によって望ましいところへ経済を戻すという議論になりがちだ。
しかし、上述のように、米国経済の基本的なあり方の変化が起こっているのだとすれば、それ自体は日本の経済政策では克服できない。
せいぜい実質で1%程度の成長が現状の日本経済の巡航速度であり、そこにまだはっきりはしないが、トランプショックでマイナス1%未満の下押し圧力が加わりそうだ。
だとすれば、マイナス成長にはならないものの、「かつかつの実質プラス成長」というのが新しい日本の経済成長の巡航速度ではないか。それを引き上げるためには、トランプ政権下の米国を前提とした新しい世界秩序の下で、どう生産性を引き上げるかに腐心しなければならない。
単に減税をしたり、金利を下げたりというのでは、これまでと同じで、生産性改善への道筋はみえてこない。まずは、再び日本経済の置かれた経済環境が大きく変わってしまい、そのため経済成長の巡航速度が低下したという不都合な事実を直視するところから考えを組み立ていくべきだろう。
歴史は韻を踏む
これから将来、トランプ政権がずっと続く訳ではない。しかし、トランプ政権的な要素が米国内で支持されるようになったということは、程度は別として今後も変わらないのだろう。米国経済にとってさえ1990年代以降のグローバル化は速過ぎたのかということなのかもしれない。
近代の歴史を振り返ると、世界の経済は統合と分離の2つの力が、交互に強くなり弱くなりを繰り返している。どれくらいの時間経過が必要かは分からないが、また変化は起こるだろう。それが、歴史が韻を踏むということではないか。
しかし、それでも世界中の国が自給自足化に舵を切るということはなさそうだ。まだ発展余地のある新興経済が、自由貿易の途を閉ざすということないだろうし、日本のように天然資源の乏しい国は、自由貿易なくしては現在の生活水準でさえ維持できない。
さらに言えば、日本経済の高度成長は東西冷戦という対立構造の中で実現されたものである。米国が自給自足化へ少し動いたからと言って、全く経済成長できなくなってしまうことにはならないはずだ。
日本としてできることは、まずは対米交渉において、日本へのダメージができるだけ少なくなるよう努力することだろう。ただ、もし今回の米国の要求に、上述のような、「これまでのつけを返せ」という面があるとすれば、米国の譲歩は限られ、日本には追加的な負担が生まれる。
そこで日本は、新しい国際秩序の中で、できるだけ広い自由貿易圏を確保し、その中で成長していくという課題に直面する。今回の米国のあり様をみれば、国内の比較劣位分野に配されている経営資源を、いかに円滑に比較優位分野へと移動させるかという点をより意識することが大事だろう。
さらに、変わらないと思ってきた米国が変わってしまったのであるから、新しい貿易関係を構築していく際にも、どう安定性を担保していくかという点を忘れてはいけないだろう。
世界の中で、日本と似たような立場にある先進国と言えば、それは欧州しかない。また、地理的な環境を考えれば、アジア・太平洋地域は引き続き日本にとって重要だ。中国という、必ずしも社会の安定に関する価値観を完全に共有できない経済大国が隣国だという点も熟慮しなければならない。
しかし同時に、これらはみな日本にとっての機会でもある。新鮮な思考で未来に挑戦しなければならなくなったようだ。

著者の新著『「経済大国」から降りる ダイナミズムを取り戻すマクロ安定化政策』(日本経済新聞出版)
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。