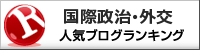10/17Rasmussen Reports<67% Support Ending ‘Corporate Welfare’= 67%が「企業福祉」の廃止を支持>
あらゆる政治的傾向を持つ有権者の大多数が、企業に対する政府の補助金に反対している。
ラスムセン・リポーツとウッドフォード財団が実施した全国規模の電話調査とオンライン調査によると、米国の有権者の67%が「企業福祉」の廃止に賛成し、政府は企業への補助金を出すべきではないと考えていることが明らかになりました。反対はわずか17%、16%はどちらともいえないと回答しました。企業福祉への反対は、2024年1月に64%の有権者が反対したのを受けて、増加しています。



マイク・ペンスはポールライアン(2人とも共和党)と組んでトランプ追い落としを図った。ペンスが大統領になるために。
10/18阿波羅新聞網<敦促世界银行停止支持共产中国!贝森特撂狠话—贝森特促IMF和世银采取对中共更强硬立场=世界銀行に共産中国への支援停止を強く求める!ベセントは強硬— ベセントは、IMFと世界銀行に対し、中共に対するより強硬な姿勢を取るよう求める>スコット・ベセント米財務長官は、国際通貨基金(IMF)と世界銀行(WB)に対し、中共の国家主導の経済活動に対してより強硬な姿勢を取るよう明確に求めた。また、国際金融機関が本来の使命に再び焦点を当てる必要性も強調した。
ベセント財務長官による声明では、IMFは「客観的かつ公平な」方法で国別監視活動を強化すべきであると述べた。また、ベセント財務長官は、世界銀行は中国への支援を停止し、より支援を必要とする国々に資源をシフトすべきだとも述べた。
世界銀行について、ベセントは声明の中で、「卒業」政策の実施をより重視し、各国の自立を支援し、そして最も支援を必要とし、最も大きな影響を与える貧困国や信用力の低い国に世界銀行の資源を集中させることに、より一層注意を払う必要があると述べた。
「これには(共産)中国への支援を終了し、開発ニーズが最も切迫した国々に職員と行政資源を移転することが含まれなければならない」と米財務長官は中共を名指しして述べた。
IMFの監視は、中共の過剰生産→デフレの輸出、債務を抱える途上国の債務再編交渉での負担分担について。
https://www.aboluowang.com/2025/1018/2292699.html
10/18阿波羅新聞網<帮习反扑失败?9名上将一口气被开除—习提拔的9名上将一口气被开除 网络炸锅=習近平の反撃は失敗?9人の大将が一斉に除名――習近平が昇進させた9人の大将が一斉に除名され、ネット上で怒りが爆発>中共第20期四中全会の前夜、中共政治局委員で中央軍事委員会副主席の何衛東を含む9人の大将が党と軍から除名された。全員が習近平によって大将に昇進したため、このニュースはネット上で広く嘲笑された。
中共国防部は本日(10/17)、中央軍事委員会副主席の何衛東と中央軍事委員会前政治工作部主任の苗華を含む9名が「極めて巨額」の職務上の重大犯罪の疑いで党から除名されたと発表した。国防部はまた、中央軍事委員会がこれ以前に9名を軍から除名したと述べた。
党と軍から追放されたのは、何衛東、苗華、何宏軍(中央軍事委員会政治工作部常務副部長)、王秀斌(中央軍事委員会統合作戦指揮センター常務副部長)、林向陽(東部戦区司令官)、秦樹桐(陸軍政治委員)、袁華智(海軍政治委員)、王厚斌(ロケット軍司令官)、王春寧(人民武装警察部隊司令官)の9名であり、彼らは中共の重大な規律違反、極めて巨額の金銭を伴う、極めて深刻な性質と極めて有害な結果を伴う重大な職務犯罪の疑いがあるとされた。
2023年にロケット軍司令官に昇進した王厚斌を除いた将軍は全員、第20期中央委員会委員であり、来週開催される四中全会で除名が承認される予定だ。注目すべきは、9人全員が習近平自身によって大将に昇進し、彼が権力を握ってから昇進し続けていることだ。何衛東、苗華、林向陽など、多くは習近平直属の部隊である福建省駐屯の第31集団軍に所属していた。
民主中国陣線会長の秦晋博士は以前、これは習近平のいわゆる自主的粛清ではないと述べた。 「誰が自分の右腕を切り落としたいと思うだろうか?中共はブラックボックスの中で活動しており、カードを引っ繰り返して初めて状況が分かる。しかし、分析によれば、習近平が権力を自らの手に集中させた上で、左右の腕を切り落とすようなことはしないだろう。そんなことはあり得ない。」
秦晋博士の言う通り、今度の軍人事は反習派によってなされたと見るべきでは。
https://www.aboluowang.com/2025/1018/2292738.html
10/17阿波羅新聞網<俄罗斯的真实情况 比普京说的还要凶险=ロシアの実情はプーチンが言うよりもさらに危険>ロシア経済について言えば、現状はプーチン大統領が吹いているほどバラ色ではない。プーチンはロシア経済が堅調であると繰り返し強調し、西側諸国による制裁はロシアに打撃を与えず、むしろ強化しただけと主張している。しかし、実際のデータを見れば、これらの主張は誇張されていることが分かる。
2025年も半ばを過ぎた現在、ロシアの経済成長率予測は、年初2.5%から1.5%へと繰り返し下方修正されている。国際通貨基金(IMF)でさえ、2025年の成長率予測を0.9%に、さらに2026年にはわずか1%へと引き下げている。これは、プーチンが昨年末に「ロシア経済は日本を抜いて世界第4位の経済大国になった」と言ったこととは大きく離れている。当時、プーチンは購買力平価で算出したGDP数値を用いており、一見人を驚かせるが、詳しく見てみると、そこには多くの虚構が隠されている。
まずは表面的なデータから見ていこう。ロシア当局は、2024年のGDP成長率が4.3%、2023年が3.6%と、世界平均を上回っているとずっと喜んで報告している。しかし、これらの数字はどのようにして出てきたのか?その原動力となっているのは主に軍事産業であり、戦費はGDPの6%以上を占め、経済を戦時体制へと移行させている。短期的には、これは生産を刺激し、工場は戦車や弾薬の生産のために残業し、失業率は2.4%まで低下し、賃金も上昇した。しかし、率直に言って、これは持続可能な成長ではなく、単に金を燃やしているだけである。
攻撃を受けて滅失した資産もある。
https://www.aboluowang.com/2025/1017/2292423.html
10/17阿波羅新聞網<神秘装置?俄军和徒弟中共无地自容😎😂北约秘书长讲大实话=謎の装置?ロシア軍とその徒弟である中共は恥ずべき存在😎😂 NATO事務総長が真実を語る>ヨーロッパで開催されたNATO会議において、NATO事務総長のマルク・ルッテは本日、衝撃的な発言を行った。演説の中で、彼はロシア軍を揶揄わずにはいられなかった。
「ロシアの能力を過大評価してはならない。ロシアの戦闘機パイロットが飛行機を操縦できないことは誰もが知っているが、海軍の艦長はどうだろうか?もっとまともでない。彼らは錨を下ろすことさえできないのだ!」
ルッテはまた、ロシア軍の「謎の海底装置」を愚痴り、ロシア軍が様々な「水中作戦」で多くの失態を犯してきたことを示唆した。
喵のコメント:NATOの最新評価:ロシア軍はまさにトランプ大統領が言う「張り子の虎」だ!ルッテの率直な発言は、ロシアの邪悪な息子であり徒弟である共匪を恥じ入らせている。😎😂
ペスコフは「張り子の熊」はロシアにない、本物の熊だと。
https://www.aboluowang.com/2025/1017/2292485.html

何清漣 @HeQinglian 3h
WSJ:「中国の対米戦略:「夷の優れた技を習い、以て夷を制す」
米国は長年、先端半導体における優位性を活かし、中国指導部の技術面への野心を抑制してきた。今、北京は米国のアプローチと酷似した戦略を策定しており、事実上、ページをめくり参考にしている。
もっと見る
何清漣 @HeQinglian 3h
WSJ:「『革命的司令官』トランプは、内政・外交政策を再構築するも、中国問題が依然として大きな試練として残る」
トランプのように、これほど短期間でこれほど多くの成果を上げた米国大統領は他にいない。国内における左派の「目覚めた」文化を列挙して攻撃した後、著者は「革命的司令官」トランプが国際舞台で引き続き成果を上げていると主張する。
もっと見る
山上・外薗・丸谷氏の記事では、山上氏は外務省の語学スペシャリストの優秀さを語っていますが、それが本当に外交に役に立っているのかどうか?ネットの世界では害務省と揶揄され、日本の国益を毅然として守ることができない、軟弱外交しかできない組織と見られている。幣原喜重郎以降そうなって、お公家様になってしまったという自覚はあるのかな?松岡洋右のように暴走するのも危険ですが。今の時代は戦うべき相手を間違えず、打倒共産主義を掲げたらよい。立憲君主制の国と共産国は真の友好国にはならない。日本の伝統文化を守る天皇を打倒するのが共産主義なので。
外国での子供連れ去り問題は、キチンと手続してからと分かっていても、DVが起きれば、日本に連れて帰って来るのでは。欧米は共同親権、日本は単独親権の違いもある。
2020年8月11日<日本人の親による「子供連れ去り」にEU激怒──厳しい対日決議はなぜ起きたか>
A記事
欧州の日本の捕鯨問題への批判が根強い。特定の価値観によって“野蛮な日本”というイメージを定着させ、「異質論」として展開した反捕鯨団体の国際的なキャンペーンは、まさに情報戦・認知戦の側面を持っている。
これに対し日本国内では、捕鯨問題を「文化の問題」のみで議論され、「情報戦」の視点では語られない。そこで今回は、前駐オーストラリア特命全権大使の山上信吾氏、第30代航空幕僚長の外薗健一朗氏、危機管理コンサルタントの丸谷元人氏が、「情報戦・認知戦に打ち勝つためのインテリジェンス」についてを明かす。

書影:山上信吾、外薗健一朗、丸谷元人著『官民軍インテリジェンス』(ワニブックス刊)
※本記事は、山上信吾、外薗健一朗、丸谷元人の共著『官民軍インテリジェンス』(ワニブックス:刊)より一部を抜粋編集したものです。
日本人が知らない「捕鯨問題」ウラの顔
丸谷元人(以下丸谷): 私が捕鯨問題で感じていたのは、あれが日本のイメージを破壊することに、非常によく機能していたことです。
実際、国際社会、特に欧米諸国において、日本の商業捕鯨は「残酷」「野蛮」といったイメージで報じられることが多く、日本の国際的な評判に少なからず悪影響を与えていました。反捕鯨団体による抗議活動がメディアで大きく取り上げられることで、日本の「捕鯨国」としての側面が強調され、国家ブランドの毀損につながっていた。

私と議論したオーストラリア人はよく「クジラは高度な知能と社会性を持つ生物であり、神から食べ物として与えられた生き物ではない」と主張していました。それに対して私は「では、インド人があなたに『神聖な牛を食べるな』と言ったら食べないのか」と反論しました。
そう言い返されると、誰も答えられない。日本が国際社会で包囲されそうな時にはこういった反論をしっかり用意しておく必要があると思います。
山上信吾(以下山上): 非常に重要なご指摘です。日本では一般的な認識ではありませんが、捕鯨もまさにインテリジェンスが直接的に関わる問題なんですよね。
反捕鯨団体によるキャンペーン、メディアを通じたイメージ戦略、特定の価値観の国際的浸透などは、まさに情報戦・認知戦の側面を持ちます。しかし、日本の社会では、捕鯨問題がそのような「情報戦」の文脈で語られることはほとんどありません。
欧米社会の一部には、日本の特異性を強調して叩きにかかる風潮が存在しています。日本人はまずそのような現実があるという認識から始めなければいけないのですが、そこに対するインテリジェンスもまた不十分です。

反捕鯨活動家ポール・ワトソンの支持者たちは、彼が拘留された後にフランスへ到着した翌日の2024年12月21日にパリのレピュブリック広場で集会を開いた(写真:gettyimages)
反捕鯨運動が強烈に展開されていた頃、外務省の中には「国際社会の潮流に逆らって捕鯨を頑なに続けることは日本の国益を損うのではないか」と物知り顔で説く先輩が少なからずいました。まさに、情報戦・認知戦との意識が欠如している証左です。
実際、「IWC脱退」のオペレーションにあたっても、当時の国家安全保障会議事務局(NSS)の大幹部の間でも、こうした意識を鋭敏に持っていた兼原信克次長のような人物もいれば、「とにかく捕鯨問題には関わりたくない」という態度を露骨に出す人物もいました。
欧州にいまだ残る「日本異質論」
山上: 日本の特異性が批判の対象となるのは、捕鯨問題だけではありません。典型的なのは死刑制度です。欧米諸国はほとんど廃止しているのに、なぜ日本は主要先進国でありながら死刑制度を維持しているのか、やっぱり日本人は異質ではないか、という意識は欧米人の底流にずっと存在しています。
外交の場でも人権に関する話題になるとたびたびそれが噴出し、欧米の報道や人権団体のキャンペーンにおいても、繰り返し批判の対象になってきました。つまり、日本の死刑制度は、欧米の一般市民の意識の中に、日本の特異性の象徴として刷り込まれている側面があるわけです。
外薗健一朗(以下外薗): 欧米人からすると「日本人はなんて“時代遅れ”で“非人道的”なんだ」ということですね。
山上: おっしゃる通りです。だからこそ死刑制度を維持している日本のロジックや日本人の心情をしっかりと説明しなければいけないのです。でも法務省や外務省の広報は受け身に終始している感があります。あえて言えば、アメリカの幾つかの州で死刑制度が維持されていることに大いに助けられている面が大です。
それからもうひとつ、私が大使の時に「最大の爆弾」だという危機意識を持って取り組んでいたのが、日本人の親による「子供の連れ去り問題」です。
日本人は国際結婚をしても、結婚生活が破綻すると、配偶者の同意を得ることなく、子供の手を引いてそのまま日本に帰ってしまいます。これは特にお母さんが日本人である場合に多い話なのですが、当然、残された父親は子供との接触を断たれて悲嘆にくれることになります。
つまり、父親側からすると「我が子が日本に連れ去られた」という認識であり、子供が日本にいる限り外国の裁判所の返還命令が執行できないという問題が生じていたのです。

日本をはじめ、ハーグ条約に加盟している国は120ヵ国を超える(写真:gettyimages)
これに対して、国際社会、特にアメリカ、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリアなどの欧米諸国からの批判が高まりました。そして、その圧力から、日本は2014年にハーグ条約(正式名称は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」。国境を越えた子供の不法な連れ去りや、国際的な子供の返還に関する問題を解決するための国際条約)に加入することになったのです。
この問題もまた「日本人はなんて非人道的なんだ。なぜ裁判で争わず子供を勝手に連れ去るのか。やはり日本人は異質だ」という議論に結びついていきました。
まずは「世界標準」のルールを知るべき
このように国際社会では日本異質論がいまだに残っていて、個別具体的な問題をきっかけに一気に燃え上がることがあります。捕鯨問題もまさにその一つだったわけです。
以前からこういう物事の捉え方をしていれば、日本の異質性を強調するような議論をもっと有効にハンドリングできていたと思います。しかし、日本では真正面から「鯨肉を食べて何が悪いのか」「日本の伝統的な食文化を壊すな」と感情的に反論してしまう人がよくいます。
子供の連れ去り問題も「夫のDVが原因なんだから仕方ないでしょ」と開き直るお母さんがいっぱいいます。しかし、国際結婚をして相手の国に移住して生活していたのであれば、まずはそこでの救済手続を追求するのが世界標準なのです。
日本人異質論が日本外交の手枷足枷にならないよう、どのように国際的な議論をコントロールしていくべきか――そういう観点からも、インテリジェンスで相手国や国際世論の背景にある意図、価値観、情報操作の動きなどを正確に把握するインテリジェンス能力が不可欠になるわけです。
「子供の連れ去り」で私が一番懸念したのは、その問題を英語で表現する時に「abduction」という単語がしばしばもちいられることです。ハーグ条約上は「removal」という表現もあるのに。ご存知の通り、北朝鮮による拉致は「abduction」と表現されてきました。
人道にもとる国家による組織的・計画的な犯罪と一家庭内の親の不仲に基づく子供の転居に同じ言葉を当てはめる不条理です。これこそ、拉致問題の重要性を損い、日本の主張を貶める情報戦、認知戦ではないでしょうか。
…つづく<じつはアメリカにとって、日本は「親友国ではない」…外務省がもたらした、知ってはいけない「日米同盟の真実」>でも、官僚、民間、自衛隊、それぞれの組織でのインテリジェンスの世界に迫ります。
B記事
戦後以降、日本は特定の国に偏らず、世界の主要国と対話できる信頼関係を築いてきた。欧米と対立する国とも対話チャンネルを維持しており、これは日本の大きな強みだ。一方、多くの日本人が感じている「アメリカと日本は大親友」という枠組みは大きな間違いだ。
日米同盟を基軸としながらも、多角的な関係を築いてきた戦後外交のあり方をさらに強化するにはどうしたらよいのか。前駐オーストラリア特命全権大使・山上信吾氏、第30代航空幕僚長・外薗健一朗氏、危機管理コンサルタント・丸谷元人氏が、「日本と世界の関係性」について語り合う。
外務省のインテリジェンスの「強み」と「弱み」
山上信吾(以下山上): 一般的なイメージとして、外務省は外交の最前線で外国情報に接する機会が多いため、職員もインテリジェンスの素養がある、あるいはインテリジェンスに精通している、と思われているふしがあります。しかし、実態は本当に千差万別です。つまり、「人」によります。
ただ、大前提として、インテリジェンス業務を経験する職員は、実はそれほど多くはいません。外務省のキャリアパスは多岐にわたるので、政策立案、経済協力、条約業務など、インテリジェンス部門とは直接関わらない部署でキャリアを積む職員もたくさんいます。
特に組織の中枢を歩んでいるような人は、インテリジェンスを通らないことも珍しくありません。「インテリジェンスなんてやったことがないからわからない」という人間の方が多いくらいです。そこはやはり外務省が改善しなければいけない点です。
一方、優秀な人材も間違いなくいます。私も国際情報統括官というインテリジェンス部門のヘッドになって初めてそれがわかりました。
かつて国際情報統括官組織は省内で「サナトリウム」と揶揄されていました。本来ならチャイナスクールやロシアンスクールの本流を歩んでいたのに、心身の不調や親の介護等の理由から仕事に専念できなくなった職員たちが、次々と国情組織に流れ着いていたからです。
とは言え、彼らはロシアや中国をはじめとする諸外国に長期留学し、在外公館勤務を何度も経験してきた人材です。生半可な大学教授やシンクタンカーよりもよほど任国の言語や文化、歴史、社会情勢、生活習慣、政府の人事に精通しています。つまり、人材の質としてはものすごく高いわけです。
しかし、いかんせん少数精鋭で、私が現役の頃にはわずか80名弱しかいませんでした。防衛省や警察、公安調査庁などと比べると、外務省のインテリジェンス部門は圧倒的に人数が少ないのが弱みです。
一方、外務省という組織全体で見た場合の強みは、やはり語学のスペシャリストを多数育成していることでしょう。ロシア語や中国語だけじゃなくて、アラビア語、ペルシャ語、トルコ語、ヒンディー語、ウルドゥー語、ヘブライ語、朝鮮語の専門家もいる。
現地の言語を理解し、情報源と直接コミュニケーションを取れる能力は、情報収集・分析の質を大きく左右します。語学力はインテリジェンス活動において極めて重要な要素。その語学の専門家を多数抱えているというのは、外務省の一番の強みだと言えます。
「対話チャンネル」の保有は、日本全体の強み
山上: 2つ目の強みは、日本という国そのものの強みだと思いますが、世界中のほぼすべての主要アクターと対話できる信頼関係を築いていることです。特定のブロックに偏らず、多角的な外交を展開し、多くの国と良好な関係を維持しています。

例えば中東地域では、日本は、イスラエルと外交関係を維持しつつ、パレスチナ自治政府への支援も継続しており、双方と対話可能な稀有な国の1つです。
また、サウジアラビア、UAE、カタールなどの湾岸諸国とも、エネルギー供給源としての関係だけでなく、経済協力や投資を通じて非常に良好な関係を築いています。トルコ、エジプトとも伝統的に友好的な関係を維持しているほか、イランやシリアも日本となら会って話をしてくれるという関係にあります。
特にイランは欧米諸国との関係が厳しく、核問題や地域情勢(中東の紛争への関与など)をめぐって対立が深まることが多いため、自由民主主義陣営の多くの国にとっては直接的な対話が困難な相手です。だから、日本がイランと比較的安定した関係を維持し、対話チャンネルを確保していることは、欧米諸国から見ると、時として懸念やフラストレーションを招く面もあるものの、期待値が高いポイントでもあります。
この日本の信頼度の高さ、世界のどこにでもアクセスできる強みは、私も現役時代に実感しました。この認識はおそらく外務省だけでなく防衛省や警察庁、あるいは政府全体でも共有されていると思います。

冷めた言葉で言えば、日本はどの地域に行っても“親友”はいないけど“そこそこの友達”ならいる、ということですね。相手から見れば利用価値がある国とも言えるでしょう。対立アクターの双方や、多様な政治体制の国々との関係を維持し、対話チャンネルを持っているという多角的・多層的な対話能力は、日本という国家全体の強みだと思います。
日本はアメリカの「最も親密な同盟国」ではない
山上: こういう話を聞くと、日本人の中には「いや、アメリカが日本の親友じゃないか」などと言う人たちが一定数います。
アメリカから見れば、日本程度の付き合いの国はいっぱいいるんですよ。その現実を日本人は本当に噛み締めないといけません。
ご存じの通り、アメリカとイギリスは「特別な関係(Special Relationship)」と呼ばれる歴史的な結びつきを持ち、外交・軍事・情報共有の面で深い協力関係にあります。でも、あるアメリカの識者が言うには、アメリカから見たイギリスは、時々自分たちに歯向かってきて言うことを聞かず、説教までしてくることもあるから、カチンとくるのだとか(笑)。
一方、オーストラリアは、アメリカからすると、自分たちが戦争する時には常に一緒に武器を取って戦ってきてくれた存在です。第二次世界大戦以降、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦争など、アメリカが関与した主要な紛争において、常にアメリカをサポートしてきました。
丸谷元人: イギリスはベトナム戦争に参加しなかったですからね。
山上: オーストラリアは2001年の9・11同時多発テロ事件でも、当時のジョン・ハワード首相が、アメリカへの攻撃がANZUS条約(太平洋安全保障条約)第4条に基づく集団的自衛権の対象となると表明し、対テロ戦争への全面的な支持と参加を表明しました。これはオーストラリアの対米コミットメントの強さを示す象徴的な出来事です。
そんなオーストラリアに対するアメリカの信頼感を日本人はあまり理解していません。日米同盟が最も緊密だと“信じて”います。でも、アメリカから見れば、オーストラリアもいれば、イギリスもいるし、日本もいる。そういう関係性です。ちなみに、そのアメリカの要人は日本について、「戦略的に最も重要な同盟国(strategically most important)」という面白い表現をしていましたね。

だから、日本も今後は日米同盟を基軸にしつつ、外交の裾野を広げていく努力がますます必要になってくると思います。その意味では、日本が世界の各地域に友達をいっぱいつくってきた戦後外交のあり方は、ひとつの強力な基盤になると思います。
やはり日米同盟の一本足打法では、あまりにも情けないし、頼りない。日本の国益の実現という観点から見れば不十分です。トランプ大統領のような個性とアクの強いリーダーが登場するたびに、振り回されるハメになります。
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。