8/30増田俊男氏記事<軍産の罠とトランプ(のバック)の罠>. この記事を読みますと何が真実か分からなくなります。またナショナリストVSユダヤ・グローバリズムとの戦いの話も加わりますと。
http://www.chokugen.com/opinion/backnumber/h29/jiji170830_1188.html
米国の二極分化がどんどん進んでいっているように思われます。別にトランプ時代から始まった訳でなく、クリントン時代に企業利益の還元が株主に大きくなってからのことと思います。貧富の格差は大きくなるにも拘わらず、アファーマテイブ・アクションで黒人層が優遇を受け、白人中流層の没落が続いてきたせいと考えています。このように動かしているのがグローバリストかどうか分かりませんが。
でも、黒人奴隷も善悪の判断は別にして、歴史の一コマでしょう。それをなかったことにはできません。歴史を顧みて、今は正しく生きられるようにしないと。像を壊せば、過去の歴史が消えてなくなる訳ではありません。況してやリー将軍は敗軍の将です。日本で言えば西郷さんの像を壊すようなものでしょう。日本人の感性から言えば、判官贔屓もあり、敗軍の将にも温かく声援を送るのが普通です。過去を現在の価値基準で断罪するのは間違っています。高山正之・福島香織両氏の対談集『アメリカと中国が世界をぶっ壊す』の中(P.32~33)に、高山氏が「戦後もこのメディアによる支配は続いた。ただ、支配者がホワイトハウスだけでなくウオ—ルストリートとかグローバリズムの賛同者とか余計な勢力が登場してきたが、基本的に支配層と密着したメディアが世論を操作する仕組みは変わっていなかった。
それが今回大きく変わった理由の一つはアレクシ•ド・トクヴイルの語った「アメリ力の民主主義」の形が変容したことが挙げられる。
それは彼の本の中にはっきり書いてある。彼は米国人が使う黒人奴隸や米国人があらたに資源を求めていく過程で次々殺していくインディアンなど有色人種について「彼らは家畜と同じだ。白人に労働力を提供し働く。しかし彼らが働かなくなったりすれば、それはもう用がない。殺してしまえばよい」。トクヴイルに限らずモンテスキユ―(三権分立を説いたフランスの哲学者) ですら「黒人が同じ人間とは考えられない。なぜなら彼らは貨幣よりガラス玉を喜ぶ」と語っている。つまりトクヴイルのご託宣も白人国家アメリカについて語られていて、その限りで民主主義は機能し、欧州のいい手本になると言っている。 しかし現実は違う。結局、黒人奴隷も黄色い奴隸苦力もヒスパニックも殺しつくせなかった。トクヴイルの描いた将来にはいないはずの有色人種が、いまや大きな投票権を持つ存在になってきた。
民主党政権はそれを薄々ながら知っていた。それでたぶらかしてきた。白人種優位を言葉の上だけでも否定して見せるポリティカル・コレクトネスとかマイノリティと称する本来なら淘汰すべき輩に一定枠の大学入学枠とか、就職枠を提供するアファーマティブ・アクシヨンとかを考え出しては、彼らを騙してきた。もちろんその先鋒として常にメディアがあった。
黒人大統領を選び出したのも、その騙しのテクニックの一つだったのだろうが、それもそろそろ限界にきていた。
その時期にマーク.レヴィンソンの言う1973年の亡霊が重なった。有色人種が能力以上に優遇され、社会保障が充実され、この国を支えてきたと思っていた働くアメリカ人がもはや何の夢も持てなくなった。これが今回の大統領選の過去とは大きく違う環境だった。しかし肝心のメディアだけはその環境変化を読めず、もっと言えば大統領選の結果もいまだに信じられない状況にある。我々が国を動かしてきたのに。世論をつくってきたのに。なぜ世論が背を向けたのか。」とありました。
モンテスキユ―は1700年前半、トクヴイルは1800年代前半の人間ですから、リー将軍の像を倒すデモに参加している白人は彼らの罪を償うべきとなるのでは。
中国や朝鮮半島が日本を歴史戦において糾弾するのにも同じ匂いを感じます。勿論彼らの言うことは歴史の事実ではなく、でっち上げですが。いつまでも過去に拘るべきではなく、そこから何を学ぶかでしょう。
高濱記事

米バージニア州シャーロッツビルで、車が人混みに突っ込んだ現場で、応急手当を受ける人たち(2017年8月12日撮影)。(c)AFP/PAUL J. RICHARDS〔AFPBB News〕
「シャーロッツビルの騒乱」で脚光を浴びた極右集団
ドナルド・トランプ氏が米大統領になって大きく変わったことがいくつかある。
その1つは、これまで社会の片隅で息をひそめていた白人極右集団が白昼堂々と集会やデモを始めたことだ。なぜか――。カリフォルニア大学バークレイ校の白人社会学者はこう一刀両断にする。
「黒人大統領オバマの8年間の政治下で不公平感・被害妄想を増幅させた白人極右のバックラッシュ(反動)だ。彼らはトランプに自分たちと同じ『体臭』を嗅ぎ取った。それで安心して隠れていた穴からぞろぞろ出てきたのだ」
米メディアが「White Supremacist」(白人至上主義者)と呼ぶ、「肌の白いことこそが唯一至高の存在だ」と主張する白人優越主義集団。
一般的には低学歴、低所得のプア・ホワイトが多いとされている。十代から高齢者まで年齢制限はない。ネット上で連帯感を培っている。かなりの会員を擁するものから個々人のものまでざっと500団体。ツイッターのフォロワーは約5万人。
主だったグループとしては、ネオ・ナチス、人種差別秘密結社のキュークラックスクラン(KKK)、そして今メディアから脚光を浴びている「オルト・ライト」がある。
このグループの旗艦的存在とされる超保守メディア「ブライトバート・ニュース」の会長兼編集主幹だったスティーブ・バノン氏は8月18日、事実上解任されるまでトランプ大統領の首席戦略官兼上級顧問を務めていた。
今回の「シャーロッツビルの騒乱」を巡るホワイトハウスの対応のまずさの責任を取ったとの見方も出ている。
大統領の側近中の側近が「オルト・ライト」となれば、白人至上主義者たちが「トランプ大統領に自分たちと同じ『体臭』を感じた」としても不自然ではない。
「白人至上主義者」に理路整然とした政策目標などない。何かトラブルがないかをネット上で探し回わって、面白いと思えば動員をかける。
その意味で、バージニア州シャーロッツビルのリー将軍の銅像撤去問題は「白人至上主義者」たちにとっては格好の「獲物」だったわけだ。
喧嘩両成敗を批判されたトランプが猛反発
トラブルはトラブルを呼ぶ。「白人至上主義者」を極右とすれば、今米国では極左も台頭している。代表格は「Antifa」(Anti-Fascism、反ナチス)と自称する無政府主義者たちだ。
極右が姿を見せる場に現れては武力衝突も辞さない構えなのだ。まさにヤクザ同士の抗争に似ている。
シャーロッツビルは、名門バージニア大学がある静かなカレッジタウン。南部とはいえ、リベラルな知識人が多く住んでいる。そこに極右や極左は住んでいない。
騒乱は、外から集まった極右と極左の武闘に端を発し、ネオ・ナチスに傾倒した20歳の白人男が何を思ったのか、群衆めがけて車を暴走させ、普通の中年女性が轢き殺された。負傷者も多数出た。
事件直後、トランプ大統領は「暴力沙汰は双方に非がある」とこうコメントした。
「集まった白人の大半はリー将軍像撤去への抗議が目的だった。(撤去の理由が同将軍が奴隷制度を支持したから像を撤去するのであれば)今週(撤去するの)がリー将軍なら来週は(奴隷を所有していた)ジョージ・ワシントン初代大統領で、次はトーマス・ジェファーソン第3代大統領か」
間違ってはいないが、バノン氏を超側近として侍らせている大統領の発言ともなれば、「白人至上主義者」に理解を示していると忖度できる含みのあるコメントだった。
この発言に主要メディアは「大統領は極右集団の言動に同情的だ」と一斉に集中砲火を浴びせた。大統領は、その後1週間経っても怒りが収まらないのか、発言を正当化し、主要メディアの偏向報道を激しく罵った。
銅像撤去を提案したのは黒人市議会議員
リー将軍銅像は1924年、シャーロッツビル出身でシカゴで財を成した篤志家、ポール・マッキンタイヤ―氏が全額負担して作ったリー公園内に建てた。当時反対する人はいなかった。ちょうど排日移民法が成立した年だ。今から93年前のことだ。
それがなぜ今頃、銅像の撤去となったのか。
撤去を言い出したのは5人いる市議会議員の1人、ウエス・ベラミーという教育学博士だった。市議会初の黒人議員だった。昨年3月のことだ。
これまで90年以上、誰も関心を示していなかったリー将軍像。撤去の理由は、「リー将軍の像は奴隷制度のシンボルだ」という黒人市民からの陳情だった。
リー将軍は南部に住む白人にとっては英雄だった。日本で言えば、「国賊」のレッテルを貼られた西郷隆盛のような人だった。
市議会はその後6か月にわたる公聴会を開いて撤去の是非について市民の声を聞き、最後に第三者委員会に是非を委ねた。最終決定は市議会だが、2月6日の採決では賛成3、反対2で辛くも承認された。
ユダヤ系市長は最後まで反対した。撤去した後どうするか、博物館内に移すか、私有地に設置するか、まだ決まっていない。
(参照=Charlottesville City Council votes to remove statue from Lee Park,” Chris Suarez, www.dailyprogress.com., 2/6/2017)http://www.dailyprogress.com/news/local/charlottesville-city-council-votes-to-remove-statue-from-lee-park/article_2c4844ca-ece3-11e6-a7bc-b7d28027df28.html
「異人種間結婚禁止法は白人至上主義を守るための盾」
今回紹介する新著、「Loving: Interracial Intimacy in America and the Threat to White Supremacy」。「白人至上主義」が本来どういう意味を持っているかを理解するうえでタイムリーな本である。
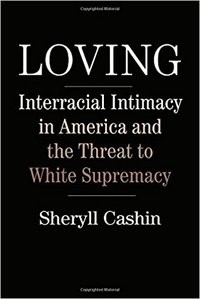
本書の内容を忖度してタイトルを意訳すればこうなる。
「黒人女性に恋をし、非合法な結婚をしたラビングという名の白人男性の物語」
副題は「米国内での異人種間の親密な関係と白人至上主義を脅かすもの」となる。
著者シェリル・キャッシン氏は白人の父親と黒人の母親との間に生まれた。ジョージタウン大学法科大学院教授。人種問題、公民権法の権威である。バンダービルド大学を経て、ハーバード、オックスフォード大学院で博士号を取得している。
本書の舞台は、今まさに全米が注視しているシャーロッツビルから170キロ南方のセントラル・ポイントという田舎町だ(今なら車で2時間かかる程度の距離だ)。
そこで生まれ、育ったリチャード・ラビング氏は子供の頃から隣接する黒人居住地に住む黒人の子供たちと遊び、人種的偏見など全くない子供だった。
地元の高校を出て大学では歯学部に進み、歯科医になる。幼馴染みのミルドレッドという黒人女性と恋に落ち、結婚しようとした。
当時バージニア州をはじめ南部17州には白人と黒人とが結婚することを禁じた「異人種間結婚禁止法」(Racial Integrity Act of 1924)があった。
そこでラビング氏はミルドレッドさんと175キロ離れたワシントン特別区で結婚。その後地元に戻ったが、戻って数日後、保安官が突然やって来て、「白人の男を夫にした」としてミルドレッドさんを逮捕、刑務所にぶち込んでしまった。
その後2人は事実上の「州外退去命令」を出され、ワシントンに居を移した。だが田舎育ちの2人にはワシントンは合わなかった。
同情する人権団体の支援を得て、2人は「異人種間結婚禁止」の州法が米国憲法に違反するとしてバージニア州政府を訴えたのだ。米史上に残る「ラビング対バージニア州」訴訟である。
そして最高裁は1967年、同法を違憲とする歴史的判決を下す。
著者によれば、「White Supremacy」(白人至上主義)という言葉が司法で最初に使われたのは、「異人種間結婚禁止法」判決だったという。
当時最高裁長官だったアール・ウォーレン氏がこのバージニア州法がなぜ制定されていたのかについて判決文で初めて明言化する。
「この州法は、厳格な人種分離政策を取ることで白人至上主義(体制)を守るために制定された法律である。これは明らかに違憲である」
つまり、もし白人と黒人とが結婚すれば白人は優越だと考え実施してきた体制を脅かしかねない。そのため法律で禁じたのが南部における奴隷制度や人種分離政策だったのだ。
奴隷制度はまさに白人至上主義思想を普及させるのに役立った。それは米憲法とは相いれない法律であり、違憲だ、というのがウォーレン長官の解釈だった。
「欧州から米国に移住してきた白人とその子孫だけが地球で至上な人種なのだ」とする「白人至上主義」。
それを支えてきたはずの「盾」は、時の流れとともに消滅していった。南北戦争で北軍が勝ったことで奴隷制度が廃止され、公民権法によってすべての国民は法の下に平等となった。
急ピッチで非白人化する多民族国家
「シャーロッツビルの騒乱」でにわかに脚光を浴びた「白人至上主義」だが、全米がそれに恐れおののいているわけではない。
ただ、オバマ政権の時と異なるのは、「トランプ大統領が『白人至上主義』に対しある種の親近感を持ち、共鳴はしないまでも理解しようとしていることが国民には薄々分かってしまっている」(前掲のバークレイの社会学者)という現実だ。
そのことが「白人至上主義者」を勢いづかせてしまっているわけだ。
少なくとも筆者の住んでいるカリフォルニア州など西海岸や東部では「白人至上主義者」の影はどこにもない。
特にカリフォルニア州の場合、人口構成は着実に白色から黄色、茶褐色へと塗り替えられ、異人種間結婚が加速することで「白人至上主義」の住み家はなくなりつつある。
自らのアイデンティティの拠り所を「白人至上主義」に求めた白人にとって、おそらくカリフォルニア州は住みずらいに違いない。
著者のキャッシン博士はこう述べている。
「私の両親の結婚が認められた1960年代後半の世論調査では、異人種間結婚を認める米国市民は4%にすぎなかった。しかし判決から50年経った現在、87%にまでなっている。『白人至上主義』を堅持するための道具だった異人種間結婚を禁じた法律も習慣も過去のものになってしまった」
「黒人だけでなく、アジア系、ラティーノの移民が集中豪雨のように入り込み、米国の人口構成を激変させている。『白人至上主義』などは大波に流される木くずのようなものだ」
「今後異人種間結婚は、異人種間の養子縁組や恋愛、新たな移民による人口構成の変化などと相まって増えるに違いない。新たな傾向に敏感な白人と肌の浅黒い人たちとの提携は深まることはあっても弱まることはない」
「白人至上主義者」たちのいら立ちなどどこ吹く風と言わんばかりに、多民族国家は急ピッチで非白人化していくことだけは間違いなさそうだ。
Economist記事
白人至上主義者と市民との衝突事件をめぐって、トランプ米大統領の発言は二転三転した。同氏には政治的な能力も道徳的な感性もなく、大統領にふさわしい資質を欠くことが明らかになった。今後、議会共和党は同氏に期待をかけるのをやめ、言動を厳しく抑え込んでいくべきだ。

米ボストンで8月19日、極右団体に反対する市民らがデモを行った。4万人が参加したとみられる(写真=Spencer Platt/Getty Images)
ドナルド・トランプ米大統領を擁護する人々は、2つの理由を挙げる。一つは、同氏はビジネスマンで、政府の行き過ぎを抑えることができるというもの。もう一つは、左傾化した既存のエリート層が作った「ポリティカリー・コレクト(編集部注:差別に基づく表現などをなくそうとする運動)」のタブーを打破し、米国を再び偉大な国へと高める力になる、というものだ。
これらの主張は、当初から希望的観測にすぎないとみられていた。そして、8月15日に行われた記者会見で、この希望は砕け散った。
白人主義への姿勢を二転三転
トランプ氏はこの日、米バージニア州シャーロッツビルで起きた衝突事件について、3度目の記者会見に臨んだ。同地では12日、白人至上主義者らが、南北戦争で南軍を率いたロバート・リー将軍の銅像を撤去する計画に抗議してデモ行進を実施。これに反対する人々(左翼を含む)と衝突した。
トランプ氏は14日に開いた2度目の会見で、白人至上主義者を非難する原稿を準備して読み上げたが、15日の会見ではその発言を後退させた。原稿のない発言の中で「双方に」非があったと荒々しい調子で強調したのだ。新任のジョン・ケリー大統領首席補佐官は、この会見を落胆した様子で見守っていた。トランプ氏の本心がどちらの側に近いか、疑いの余地はなかった。
同氏自身は白人至上主義者ではない。繰り返しネオナチを批判しているし、シャーロッツビルの衝突で、ヘザー・ハイヤーさんの命が奪われたことを非難する発言もしている。しかし、二転三転する発言から米国人が受け取ったメッセージは、恐ろしいものだった。「我々の大統領は、この国を救うどころか、政治的に無能で、道徳的に鈍感で、その職務にふさわしい気質を持ち合わせていない」
まず、無能さから見ていこう。トランプ氏は昨年の大統領選で、既存の政治家を攻撃する運動を展開し、大成功を収めた。しかし今回、「ナチスを非難する方法を見つける」という最も簡単な政治テストでしくじった。12日に行った最初の記者会見で曖昧な言葉を発した後、14日の会見では大統領に求められる発言をしたが、その成果を、翌日には台無しにした。
この結果、右派メディアの米FOXニュースと左派メディアの米マザー・ジョーンズが同じ批判を大統領に投げかける前代未聞の事態となった。米国の経済界を引っ張る経営者らも、トランプ氏の助言機関からそろって離反し、政府は助言機関の解散を発表した。
一方、白人至上主義組織クー・クラックス・クラン(KKK)の元最高指導者であるデービッド・デューク氏はトランプ氏への支持を表明した。今後、極右団体は活動を全米に広げるだろう。トランプ氏は、彼らの街頭活動を封じ込め、治安を維持するという課題を難しくしてしまった。これがもたらす悪影響はほかの政治課題にも及ぶ。
そもそも15日の記者会見は、米国のインフラ整備計画がテーマだった。インフラの整備には民主党の協力が不可欠だ。トランプ氏はこのための努力に無用の後退を強いた。
同様のことがこれまでも繰り返されてきた。6月の「インフラ週間」は、大統領選にロシアが介入した疑惑をめぐる捜査のため立ち消えになった。この捜査も、トランプ氏が腹立ち紛れに米連邦捜査局(FBI)長官を解任したことがきっかけで始まった。
公約だったオバマケア(医療保険制度改革法)の撤廃がかなわなかったのも、反対する共和党議員を説得するだけの知識とカリスマ性をトランプ氏が欠いていたことに一因がある。この敗北について同氏は、法案を可決するのに必要な協力を上院の共和党指導者がしなかったと非難した。トランプ氏がしてきたのは、この程度のことだ。
トランプ氏の政治的な無能さの根は、道徳面での鈍感さにある。極右団体の活動に抗議した人々の一部は、確かに暴力的だった。同氏が発言の中で、その暴力に対する厳しい言葉を差し挟んでもおかしくはなかった。だが、極右団体の活動と、それに反対する市民の活動を同列に論じたことは、同氏の考えの浅さを表している。
動画を見る限り、行進する者たちはファシズム的な文言が書かれた横断幕を掲げ、たいまつをかざし、杖や楯を振り回し、「ユダヤ人に追い出されはしない」と声をそろえて繰り返していた。一方、反対派の大半は一般市民で相手方に対して叫び返すのみだった。
市民がこうした行動に出たのは正しい。白人至上主義者やネオナチが実現を熱望するのは、人種差別に基づく社会だからだ。米国はまさにこれを阻止するために世界大戦を戦った。
トランプ氏は、南軍の将軍の銅像を守るために行進する人々を心から擁護しているように見える。このことは、同氏が持つ世界観の大きな部分を、白人の腹立ちや古くさい懐古趣味が占めていることを表している。
これらすべての問題の根本は、トランプ氏の気質にある。国が困難に直面している時、大統領がなすべき仕事は国民を一つにすることだ。トランプ氏は14日の記者会見でその努力をうかがわせたが、それを24時間続けることさえできなかった。
一国の大統領は、自分の点数稼ぎにとどまることなく、国益のために行動しなければならない。しかしトランプ氏は、つい最近自分に投げかけられたささいな非難にしか目を向けることができない。自分が受け継いだ大統領の職責を大切に守る必要があることを理解せず、自分の栄誉と、自らが成し遂げたと思ったことを手柄にすることだけを気にかけている。
歴代の米国大統領には様々な人物がいたが、みな大統領府を掌握していた。ロナルド・レーガン氏には道徳的な指針があった。自分の能力をわきまえ、個々の政策の詳細は部下に委任した。リンドン・ジョンソン氏は難しい人物だったが、多くの功績を残すだけのスキルを持ち合わせていた。しかしトランプ氏にはこのどちらもない。性格を変えられないことも明らかになった。
共和党はトランプ氏を抑えよ
これは危険な状態だ。米国は2つに割れている。トランプ氏が北朝鮮との核戦争の危険性に言及し、ベネズエラへの軍事介入を検討し、シャーロッツビルでの衝突について曖昧な言動を繰り返してもなお、共和党支持者の8割は同氏を支持している。この人気の高さが米国の統一を一層困難にしている。
ここで浮上するのは、公職にある共和党員はトランプ氏をどう扱うべきかという問題だ。政権内にいる者は難しい選択に直面している。辞任に傾く者もいるだろう。しかし、大統領に助言する立場にある人々、特に3人の将軍(ジェームズ・マティス国防長官、国家安全保障会議を率いるH.R.マクマスター大統領補佐官、ケリー首席補佐官)は、最高司令官(編集部注:米大統領を指す)が本能のままに取る行動を誰よりもうまく抑え込める立場にいる。
議会共和党が取るべき選択肢は明らかだ。多くの議員は、トランプ氏が共和党の政策を進めてくれるだろうと考え、同氏をしぶしぶ支持してきた。しかし、そのかいはなかった。トランプ氏は共和党員ではない。自分を主人公に据えたドラマのただ一人のスター俳優なのだ。共和党議員は、同氏に運命を託すことで、米国と共和党を傷つけている。
トランプ氏は、平易な言葉遣いをすべく粗野な努力を続けている。これは、国民生活を害することにしか役立っていない。経済改革から何か成果が得られたとしても、その代償は容認しがたいほど大きなものになるはずだ。確かに現在、米国の株式市場は好調で失業率は低い。だが、これはトランプ氏が取り組む政策が上げた成果というより、世界経済と米国のテクノロジー企業、ドル安のおかげである面が大きい。
共和党は、その気になればトランプ氏を抑え込むことができる。同氏が傍若無人な振る舞いに出た時は、何か望ましい成果が得られると期待して甘やかすのではなく、その行動をとがめなければならない。今回、共和党の中でも最も優れた者たちはそうした姿勢を見せた。ほかの者も見習うべきだ。
©2017 The Economist Newspaper Limited Aug. 19-25, 2017 All rights reserved.
良ければ下にあります
を応援クリックよろしくお願いします。

